神々とのコミュニケーション
キケロの占い論(とくに宗教と占いの関係や政治思想のなかにおける占いの役割)についてはぼくも勉強不足でこれからきちんと読んでいきたいとは思っているのだが、ここでとくに重要なのは、キケロのこの書でデヴィネーションを二種類に峻別していることだ。
この分類は、西洋における「占い」の哲学の根幹をなしてゆく。
とくにキリスト教は占いを禁止するわけだが、しかし、その「禁止」はそんなに単純なものではなく、また占星術をめぐるさまざまな論争の下敷きになっていくテーゼで、きわめて重要なものになっていくのである。
幸い、キケロの卜占論を一部、日本語に翻訳してくださっているサイトがみつかったので、ここでその部分を引用させていただこう。
Cicero, Div. 1.34 = LS. 42C
それだから、私が同調するのは卜占に2種類あると言っていた人々なのだ。つまり、その一つは技術に与り、もう一方は技術を欠いている。というのも、技術が存する人々は新しい物事には推理によって従い、古い物事は観察によって学ぶのだから。しかし、技術を持たない人々は観察され理解された徴候によって理性を働かせたり推理することもなく、魂のある種の衝動や勝手気ままな動きで将来のことを思い描くのである。こんなことは眠っている人々にもしばしば生じるし、狂気に陥って予言する人々にも時には起こる。
http://shin_ueda.tripod.com/stoics/cicerodiv.txt
この二種類の分類のキモは、要は「霊感」のようなものがかかわっているかどうか、ということになる。
前者は、「技術」によるもので、観察と推理によって、しるしを読んでいくようなタイプの占い。もうひとつは、理性や推論によらず、一種の狂気のような状態のなかで未来の予兆を感じ取るというものである。
前者を「推論的」デヴィネーション、後者を「霊感的」デヴィネーションということもできるだろう。
ただし、ここでいう「霊感」とは、「わたしって、レイカンあるのよねーー」なんていうような軽いものではまったくない。
狂気といわれているのも、今の病理的なものではなく、かのプラトンに出てくるような神的狂気(フレンジイ)、理性をつきぬけた心の状態を示しているといったほうがいいだろう。古代の哲学は、ドライな左脳的なものではまったくなく、シャーマニズムとか神秘主義にずっと近いのだ。
この二つの分類について、非常に詳しく違いを述べているのが、ギリシャの新プラトン主義者であるイアンブリコスだ。
イアンブリコスは哲学者であるだけではなく、一種の魔術師でもあって神々を動かす術テウルギーについて多くを書き残している。
オーソドクスな哲学史ではイアンブリコスはあまりにも怪しく、それまでの理性的なプラトン主義を「退行」させたと理解されている向きがあるけれど、いやいや、想像力の権利を重視する我らが星の信仰者にとってはむしろ、イアンブリコスは神秘主義者、神秘修行者としての哲学者の実践の痕跡をはっきりみせてくれる大きな手掛かりなのだ。
あーーそろそろ、疲れてきました。今回はこのあたりで、一休み。次回は、この分類について、もうちょっと詳しくみていくことにしようと思います。
<鏡リュウジのメルマガ『プラネタリー夜話』vol.1「占いの世界」より>


その他の記事

|
20世紀の日米関係がいまも残る基地の街(高城剛) |

|
『冷え取りごはん うるおいごはん』で養生しよう(若林理砂) |

|
次の食文化を左右するであろうアニマルウェルフェアネスと環境意識(高城剛) |

|
『つないだ手をはなして』主演川上奈々美さんインタビュー(切通理作) |

|
アマゾンマナティを追いかけて〜赤ちゃんマナティに授乳する(川端裕人) |

|
「相場下落」の冬支度、なのか(やまもといちろう) |

|
無意識の中にある「他者への期待」–その功罪(名越康文) |
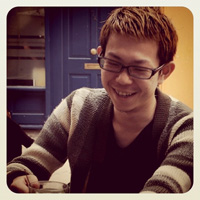
|
『ご依頼の件』星新一著(Sugar) |

|
歴史と現実の狭間で揺れる「モザイク都市」エルサレムで考えたこと(高城剛) |

|
シュプレヒコールのデジャブ感—大切なのは、深く呼吸をすること(名越康文) |

|
トヨタが掲げるEV車と「それは本当に環境にやさしいのか」問題(やまもといちろう) |

|
電気の「自炊」が当たり前の時代へむけて(高城剛) |

|
これから10年で大きく変わる「街」という概念(高城剛) |

|
なぜ母は、娘を殺した加害者の死刑執行を止めようとしたのか?~ 映画『HER MOTHER 娘を殺した死刑囚との対話』佐藤慶紀監督インタビュー(切通理作) |

|
やっと出会えた理想のUSBケーブル(西田宗千佳) |





















