マナーと対面コミュニケーション能力の増進
“5. iPhoneはあなたと一緒に学校には行けません。SMSをする子とは直接お話しなさい。人生のスキルです。注:半日登校、修学旅行や学校外活動は各自検討します。”
“11. 公共の場では消すなり、サイレントモードにすること。特にレストラン、映画館や他の人間と話す時はそうしてください。あなたは失礼なことをしない子です、iPhoneがそれを変えてはいけません。”
子どもは大半の時間を学校内で過ごしている。学校は閉ざされた世界であるが、対面のコミュニケーションや交渉を学べる重要な機会でもある。
日本の公立校は、文科省の指導により、原則的に携帯電話の持ち込みは禁止されている。その一方で、教材としてタブレットなどスマートデバイスの導入が進んできており、学校でネットを利用する機会は、今まで以上に増加していくと思われる。
一方私立では通学が遠いこともあって、携帯の持ち込みを禁止しているどころか、緊急時の連絡のために持たせるよう指導しているところもある。ただし授業中はクラスごとに担任がまとめて預かるか、電源を切るように指導している。
これはMIAUの契約書の、“食事中や人と話しているときにメールを打たない。”という項目に、ニュアンス的には近いだろう。目の前にいる人よりも、ネットの向こう側の人間の方を重視するのはマナー違反であると、多くの保護者は考えている。先ほどのMIAUのアンケートでは、家庭で指導しているマナーとして「人と話しているときに携帯電話をいじらない」が41%で最多となっている。
機材管理と責任
“6.万が一トイレや床に落としたり、無くしたり、破損させた場合はの修理費用は自己負担です。家の芝生を刈ったり、ベビーシッターをしたり、お年玉でカバーしてください。こういうことは起こります、準備していてください。”
これは僕もあまり気にしていなかった点だが、たしかに本体そのものは高価なものなので、破損のリスクはある。特に子どもに持たせていると、使い方が荒いので、落として破損したり、何日も見つからなくなったりというのはよくある。
このためにまず親は修理保証プランへの加入は必須なのであるが、値段が問題なのではなく、大事な情報が入ったものなので、紛失には特に注意したいところだ。自己負担とは言うが、お手伝いをしてそのぶんを返すというのは、いいアイデアだ。もちろん、それぐらいの労働でペイできる金額ではないことは承知の上で、自分の不注意の責任を感じてもらうことに、重点がある。

その他の記事

|
フジテレビ系『新報道2001』での微妙報道など(やまもといちろう) |

|
21世紀、都市の未来は「空港力」にかかっている(高城剛) |

|
腰痛対策にも代替医療を取り入れる偏執的高城式健康法(高城剛) |

|
アマチュア宇宙ロケット開発レポート in コペンハーゲン<前編>(川端裕人) |

|
どうなる? 小中学校へのスマホ持ち込み(小寺信良) |

|
「5類」強行の岸田文雄政権が僕たちに教えてくれたもの(やまもといちろう) |

|
2018年は誰もが信じていたことがとても信用できなくなる事態が多発するように思われます(高城剛) |

|
中進国の罠に陥って変わりゆくタイ(高城剛) |

|
同調圧力によって抹殺される日本式システム(高城剛) |

|
『寄生獣・完結編』の思わぬ副産物/『幕が上がる』は和製インターステラーだ!ほか(切通理作) |

|
あれ、夏風邪かも? と思ったら読む話(若林理砂) |

|
インド最大の都市で感じる気候変動の脅威(高城剛) |

|
クラウドの時代、拠点はシリコンバレーからシアトルへと移り変わるのか(高城剛) |
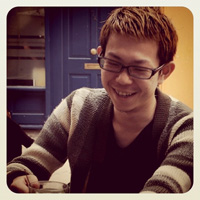
|
『時間の比較社会学』真木悠介著(Sugar) |

|
Amazon(アマゾン)が踏み込む「協力金という名の取引税」という独禁領域の蹉跌(やまもといちろう) |

























