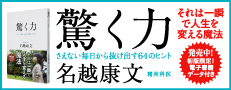「共感」の前には「驚き」がある
 社会がシステム化される中で「共感」から力が失われてしまうというのは、端的に言えばこういうことです。
社会がシステム化される中で「共感」から力が失われてしまうというのは、端的に言えばこういうことです。
「共感しましょう」「相手の立場になって考えましょう」
というときの「ルール」「ノウハウ」「正解/間違い」が、誰も気づかないうちに整備されていく。そして僕らはいつの間にか、そういった枠組みの範囲内でしか、「共感」できない生き物になっていく。
そうやってシステム化されればされるほど、「共感」はその本来の機能を失ってしまう。というのも「相手の立場になって考える」というルールに従うかぎり、僕らはどうしたって本当の意味で「相手の立場になって考える」ことができないからです。
システム化される以前の「共感」本来の力を取り戻すにはどうしたらいいか。それは僕にとって長年の問題意識でした。「共感」がなければ、暗く、淀んだ心を持つ人がもう一度前を向いたり、あるいは伸び悩んでいる人が次の世界に飛び立ったりするきっかけを得ることは非常に難しくなってしまう。それが僕の臨床的な実感でした。
しかし、「驚く力」は、その問題を解くひとつのカギとなると感じています。というのも、本来の意味での「共感」の前には、必ず心がハッと動き出すような「驚き」があるからです。
例えば「子供はほめて育てなければいけない」というのは、まったく正しい。ところが「ほめて育てなければならない」ということが「ルール」になった瞬間、「ほめること」が持つ本来の力が失われてしまう。
それは、「ほめること」がシステム化、ルール化された瞬間に「驚き」が失われるからです。子供が、自分たち大人が思ってもいないような成長を見せた。それに対する「うわ! すごい」という新鮮な驚きがあってはじめて、本当の「ほめ」が生じる。
そう考えると、「驚き」というものが人間の感覚世界に占めてきた役割の大きさがわかります。。「あなたの辛い気持ち、本当にわかるよ」という「共感」も、「すごい! よくできたね~」という「ほめ」も、いわば「驚きの名残」に過ぎないのです。
「ほめる」「共感する」といった感覚がシステム化され、ノウハウ化される中で失われていたのは実は「驚き」ではないか。これが、僕が本書をまとめる中で得た、大きな発見のひとつです。


その他の記事

|
「国際競争力」のために、何かを切り捨ててよいのか(やまもといちろう) |

|
昨今の“AIブーム”について考えたこと(本田雅一) |

|
VRコンテンツをサポートするAdobeの戦略(小寺信良) |

|
夏至にまつわる話(高城剛) |

|
不調の原因は食にあり(高城剛) |

|
「対面力」こそAIにできない最後の人の役割(高城剛) |

|
『「赤毛のアン」で英語づけ』(4) 大切な人への手紙は〝語感〟にこだわろう(茂木健一郎) |

|
アメリカでスクーター・シェアを「見てきた」(西田宗千佳) |

|
中島みゆきしか聴きたくないときに聴きたいジャズアルバム(福島剛) |

|
あたらしい知覚の扉を開く体験を多くの方々に(高城剛) |

|
バイデン政権移行中に中国が仕掛ける海警法の罠(やまもといちろう) |

|
「OP PICTURES+フェス2022」石川欣・髙原秀和 80年代デビューのピンク俊英たちが新しい時代に放つ爆弾!(切通理作) |

|
子供会にLINEを導入してみた(小寺信良) |

|
一から作り直した「非バッファロー的なもの」–『新おもいでばこ』の秘密(小寺信良) |

|
急成長女性向け風俗の蹉跌とホスト規制(やまもといちろう) |