歩き方は一人ひとり違う
ぼくは、朝家を出てから仕事場に着くまでの間が、一日のうちで最も頭が冴えている。このとき、考えごとをしていることもあるのだが、歩いている人たちを観察することも多い。
そうすると、歩き方というのは千差万別だというのが分かってくる。そうして、歩き方の上手い人と下手な人がいるというのも、よく分かってくるのだ。
この「歩き方の上手い下手」というのは、いろいろと考えをめぐらせるうちに、実はその人の人生に大きな及ぼすのではないかと考えるようになった。
そこで今回は、そのことについて書いてみたい。
観察力と恐れがその人の歩き方を変える
まず、そもそも歩き方の下手な人は、歩き方に「上手い下手」があると思っていない。それは、「歩く」という行為が人間にとって最も基本的なものの一つであるからだ。最も身近で、最も馴染み深いものゆえ、なかなか「それに巧拙がある」という考えに思い至らないのだ。
これが例えばゴルフだったら、上手い下手の存在は誰でも思い至るところだろう。あるいは、囲碁や将棋も同様だ。人は、そういう「誰もができるわけではなないこと」に関しては、上手い下手に目がいきやすい。
しかしながら、歩き方とか、あるいは日本語の使い方とか、そういう全ての人が一応はできることに関しては、その上手い下手の見分けがつきにくくなる。それゆえ、その上手い下手が、人生における大きな差異となって現れるのだ。
歩き方に「上手い下手」があると思い至らない人というのは、だいたい次の二つの能力が欠けている。
一つは「観察力」。
彼らは、観察力が欠けているから、歩き方の上手い下手が見分けられない。見分けられないがゆえに、結果として歩き方が下手なままでいるのだ。
この「観察力」というのは、人生を大きく左右する。
ぼくは先日車にはねられてしまったが、これなども、観察力の低さからくる事象だといえよう。ぼく自身、迫り来る車に気づけなかったのは観察力が足りなかったからだし、逆にはねた方も、道を渡ろうとした歩行者に気づくのが遅れたのは、やっぱり観察力の低さからくるものだ。
交通事故の場合、こうした観察力の低さはそのままその人の命運を決することとなる。はねられて死んだらそこで一巻の終わりだし、はねた方だっていろいろ大変な目に遭うだろう。
このように、観察力というのはその人の一生を大きく左右する、非常に重要な能力なのだ。
こうして考えると、「観察力」というのは、そのままその人の「能力」と言い換えることもできるかもしれない。古今東西、観察力が低くて能力が高いという人を、寡聞にして知らない。それほど、観察力は人間にとって重要な素養なのだ。
歩き方の下手な人に欠けているもう一つのことは、この世界――あるいは他者に対する「畏れ」である。
あるとき、「観察力は何によって養われるか」ということを考えていたのだが、そこで出た結論は、「畏れ」だった(あるいは「怖れ」と言い換えてもいい)。「観察力」の高い人は、世界――あるいは他者に対して、強い「畏れ」を抱いているのである。
マンガ「ゴルゴ13」の有名な台詞に、「殺し屋に最も必要なのは臆病さだ」というものがある。臆病な人間でなければ、殺し屋は務まらないというのだ。
人間は、臆病であるからこそ、用意周到になる。その反対に蛮勇の持ち主であれば、どこかに遺漏をきたし、ミッションを果たせなかったり、死んでしまったりするのだ。
「観察力が足りない」というのは、この臆病さが足りないのである。世界に対する「畏れ」が足りない。それゆえ、周囲のことが気にならないので、観察しなくなるのだ。
周りを観察しない人は、逆にいえば「自分に自信を持っている人」である。自分はこの世界を軽々と渡っていけるという「蛮勇」を持っている。
それゆえ、世界そのものや他者に対する「畏れ」が薄れる。「畏れ」が薄れると、その動向も気にならないので、観察力が低下するのだ。
ここで注意したいのは、周りが怖くて自分の殻に閉じこもってしまう人も、実は世界や他者に対する「畏れ」が足りないということだ。
世界や他者を本当に畏れていれば、人はそこから逃げ出すのではなく、それを見極めようとするはずである。なぜなら、いかに逃れようと、世界や他者とのかかわりを完全に断ち切ることは不可能なので、その怖さを本当に回避しようと思ったら、逆に立ち向かわさざるを得ないからだ。
それを知りながら目を逸らしているという意味で、殻に閉じこもっている人もやっぱり畏れが足りないということになるのである。
このように、歩き方の下手な人というのは、「観察力」と「畏れる力」が欠けている。そして観察力や畏れる力が欠けてしまうと、人生も上手く渡っていけないだろうから、不幸せになる確率が高くなるのだ。
その意味で、歩き方の上手い下手は、その人の人生を決めてしまうということもできるのである。
※「岩崎夏海の身辺雑記」はメルマガ「ハックルベリーに会いに行く」で連載中です!
岩崎夏海メールマガジン「ハックルベリーに会いに行く」
 『毎朝6時、スマホに2000字の「未来予測」が届きます。』 このメルマガは、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(通称『もしドラ』)作者の岩崎夏海が、長年コンテンツ業界で仕事をする中で培った「価値の読み解き方」を駆使し、混沌とした現代をどうとらえればいいのか?――また未来はどうなるのか?――を書き綴っていく社会評論コラムです。
『毎朝6時、スマホに2000字の「未来予測」が届きます。』 このメルマガは、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(通称『もしドラ』)作者の岩崎夏海が、長年コンテンツ業界で仕事をする中で培った「価値の読み解き方」を駆使し、混沌とした現代をどうとらえればいいのか?――また未来はどうなるのか?――を書き綴っていく社会評論コラムです。
【 料金(税込) 】 864円 / 月
【 発行周期 】 基本的に平日毎日
ご購読・詳細はこちら
http://yakan-hiko.com/huckleberry.html
岩崎夏海
1968年生。東京都日野市出身。 東京芸術大学建築科卒業後、作詞家の秋元康氏に師事。放送作家として『とんねるずのみなさんのおかげです』『ダウンタウンのごっつええ感じ』など、主にバラエティ番組の制作に参加。その後AKB48のプロデュースなどにも携わる。 2009年12月、初めての出版作品となる『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』(累計273万部)を著す。近著に自身が代表を務める「部屋を考える会」著「部屋を活かせば人生が変わる」(累計3万部)などがある。


その他の記事

|
僕が今大学生(就活生)だったら何を勉強するか(茂木健一郎) |

|
萩生田光一師匠、ガセネタを流し続けてきた深田萌絵を刑事告訴(やまもといちろう) |

|
うなぎの蒲焼は日本の歴史と文化が凝縮された一皿(高城剛) |

|
ニュージーランドに第二のハリウッドを作る(高城剛) |

|
津田大介×高城剛対談「アフター・インターネット」――ビットコイン、VR、EU、日本核武装はどうなるか?(夜間飛行編集部) |

|
孫正義さん、周りに人がいなくなって衰えたなあと思う件(やまもといちろう) |

|
人工知能の時代、働く人が考えるべきこと(やまもといちろう) |

|
2020年の超私的なベストアルバム・ベストブック・ベストデジタル関連アクセサリー(高城剛) |

|
ゲームにのめりこむ孫が心配です(家入一真) |

|
スマートフォンの時代には旅行スタイルもスマートフォンのような進化が求められる(高城剛) |

|
ヘッドフォンの特性によるメリットとデメリット(高城剛) |

|
タバコ問題を考えなおす(川端裕人) |
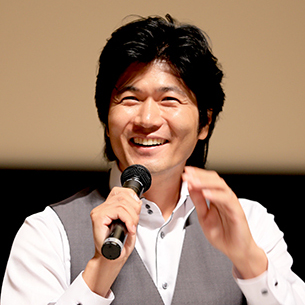
|
エッセンシャル・マネジメント(本質行動学)とは何か(西條剛央) |

|
貯まっても使う機会に恵まれないマイレージに思うこと(高城剛) |

|
季節の変わり目はなぜ風邪をひきやすい?(若林理砂) |





























