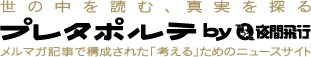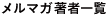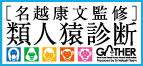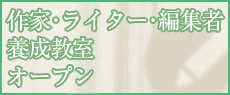川端裕人のメルマガ『秘密基地からハッシン!』Vol.059より「デンドー書店」をお届けします。
文章を書くのが「苦痛」だった僕を変えたきっかけ
石牟礼道子さんが亡くなった。
『苦海浄土』は、自分にとって大きなインパクトを与えられた作品であり、一時代の終わりを感じさせられる。
『新装版 苦海浄土』石牟礼道子 (講談社文庫)
http://amzn.to/2Bjyfgh
石牟礼さんが描いた水俣を訪ねると、石牟礼さんの功績を否定する人はおらず、ただ「患者を聖なる存在にしてしまった」というような批判はあったりはする。「現場」は様々な利害、便益が、交錯する場なのだなと思い知られたこともあった。

〈水俣病資料館から八代海をのぞむ〉
そして、自分にとっては、石牟礼道子さんの文章は、物書きになったきっかけの「ひとつ」なのだ。
実をいうと、子どものころ、文章を書くのは苦痛だった。また、言葉が持つ力を信じてもいなかった。いったいいつ、何が変わって、書くことを生業にすることになったのか。
もちろん、「その瞬間」というものが、誰の目にもはっきりと存在しているわけではないだろう。ただ、とりあえずのところ、もっともらしく感じられる出来事がひとつある。
「ゆき女聞き書き」の衝撃
高校2年生の1学期、国語の時間。花粉症で鼻水が止まらず、おまけにハンカチを持っていなかったため、ワイシャツの袖を鼻にあてて栓をするような姿勢で、机の上に覆い被さっていた。
もう四半世紀も同じことを教え続けて、喜怒哀楽も漂白されてしまったような教師の平坦な声がただ流れていた。退屈だった。あまりにも退屈なので、机の上の国語の教科書をぱらぱらめくっていた。
最後の方のページを読み始めて、鼻水に涙が加わった。まわりの連中が気付いて、奇異の目で見るのも気にせず、何度も読み返して、そのたびに泣きじゃくった。顔はくしゃくしゃ、ばりばりである。まいった。生まれてはじめての強烈な体験だった。
石牟礼道子さんの「苦界浄土」からの抜粋だった。「ゆき女聞き書き」という、まさに水俣病患者の聞き書きだけで成立している一章である。
言葉に力があった。「教科書、あなどるべからず」である。不意打ちをくらったぼくは、感情を揺さぶられ、これまで知らなかった世界に、強制的に連れて行かれたのである。
水俣病についてのいきさつを知っていたわけではなかった。水俣という町のこともほとんど知らなかった。それなのに、その時、水俣の町並みや、そこで暮らす人々や、さらに、水俣病の被害者たちの姿が、心の中でしっかりと形をとった。一冊まるまる読んだ訳でもなく、ただ、その一部を読んだだけなのに。
今、文庫版で同じはずの文章を読み返しても、どの部分でどう感じたのかを思い出すことは出来ない。なぜ、あの時、あれだけ強く感情を揺さぶられたのかも分からない。ただ、その時は、痛いほど心に突き刺さった。目の前の現実より、ずっとリアルだったと、たしかに言えた。
ものを書きたいと思い始めたのは、たぶんそれからだ。かなり漠然とした気持ちではあるけれど。
感想文を書いたものの、教師に「感想文ではない」と評される
なにせ高校生なので、とりあえず、夏休みに「国語の教科書」の感想文を書いてみた。もちろん「宿題」の感想文である。書くに当たって、文庫の「苦界浄土」も読んではみたが、この本の感想ではなく、授業中という圧倒的日常のさなか、教科書という超絶的退屈メディアの中から、突如、立ち現れた圧倒的リアリティについて、書きたかった。教室の日常に、ぽっかりと開いた異空間のことを。
「話題作」として国語教師の間で回し読みされたらしい。ある国語教師には、「感想文ではない」と批評された。それでも、「そもそも感想文とはなんぞや」と切り返すことができた。ぼくとしては、はじめて、書きたいという意欲と、こう書こうという戦略を持って構築した文章だった。自信はあった。書かれた言葉が時として持つ力を、その時ぼくは、素朴に信じていた。
そんな一種の興奮状態が続いたのは、せいぜい半年の間。やがてその熱意は薄れ、ふたたび文章を書くことが苦痛になった。
「自分が書いたものが誰かの心に届く」ということ
しかし、ちょっとした事件がおきる。何もかも悟りきったような、穏やかな諦観を表情に浮かべつつ国語教育に携わるベテラン教師が、それも学年が終わる頃になって、ぼくのところにやってきた。声だけは相変わらず漂白されたようなトーンで、「おもしろかった」と、半年も前に読んだ文章について伝えに来てくれたのだった。
「センセにおもしろいって言われたってねえ」なんて表情をつくりながら、実のところうれしかった。「自分が書いたものが誰かの心に届く」と確信できる瞬間が、脳の快感回路をいたく刺激するものだということを、ここで発見してしまう。
もっとも、プロの書き手になろうと本気で思うのはずっと後のことだし、実際にそれを生業にできる目処がついたのは、もっと後だ。それでもこの時の体験が、ぼくの中で、「ポジティブ・フィードバックの最初の一蹴り」になったのではないかと思っている。
小説もノンフィクションも書き、挿し絵のために動物写真まで撮る、無節操な書き手として、書くことに関して、自分の中で一貫したものを見いだすとしたら、「日常の中で突如あらわれる現実の亀裂を描きたい」というモチベーションであり、また、それを表現する手段として書き言葉への信任だ。とすると、あの花粉症の高校生を襲った出来事は、彼の関わるテーマと、表現の手段が、同時に開示された瞬間だったのかもしれない。
川端裕人メールマガジンの最新号・バックナンバーはこちらから。初月無料です!
川端裕人メールマガジン『秘密基地からハッシン!」
2018年2月16日Vol.058
<新型ロケット打ち上げ成功!「ファルコン・ヘビー」は我々のイマジネーションに点火した/雲を愛でる/21世紀の動物園を考えるために知っておくべきこと/石牟礼道子『苦海浄土』/ドードー/再読企画>ほか
目次
01:雲を愛でる:雪がとけるまでが積雪です
02:Breaking News
03:20年後のブロンクスから(1章)21世紀の動物園を考えるために知っておくべきこと
04:宇宙通信:新型ロケット打ち上げ成功!「ファルコン・ヘビー」は我々のイマジネーションに点火した
05:デンドー書店:『苦海浄土』石牟礼道子
06:連載・ドードーをめぐる堂々めぐり(58)チリュー・イクスペディション2017~ドードー発掘記
07:モノ語り:あま〜いみかんより、金柑!
08:著書のご案内・イベント告知など
09:「動物園にできること」を再読する:あとがき
お申込みはこちらから。
※購読開始から1か月無料! まずはお試しから。
※kindle、epub版同時配信対応!


その他の記事

|
ビッグマック指数から解き明かす「日本の秘密」(高城剛) |

|
今だからこそ! 「ドローンソン」の可能性(小寺信良) |

|
終わらない「レオパレス騒動」の着地点はどこにあるのか(やまもといちろう) |

|
ドイツでAfDが台頭することの意味(高城剛) |

|
脳と味覚の関係(本田雅一) |

|
レストランからバルへ、大きくかわりつつある美食世界一の街(高城剛) |

|
「脳内の呪い」を断ち切るには(西條剛央) |

|
東アジアのバブル崩壊と「iPhoneSE」(高城剛) |

|
ヘッドフォンの特性によるメリットとデメリット(高城剛) |

|
“YouTuberの質”問題は、新しいようでいて古い課題(本田雅一) |

|
人々が集まる場に必要なみっつの領域(高城剛) |

|
「日本の電子書籍は遅れている」は本当か(西田宗千佳) |

|
泣き止まない赤ん坊に疲れ果てているあなたへ(若林理砂) |

|
相場乱高下の幸せとリセッションについて(やまもといちろう) |

|
なぜか勃発する超巨額ワーナー争奪戦から見るNHK問題の置いていかれぶり(やまもといちろう) |