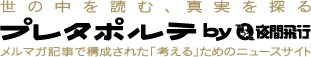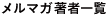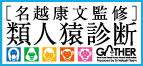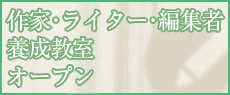◇政治家の感情を引き出す田原総一朗の功罪
そして大きな動きの三つめ。田原総一朗氏です。私は田原氏には功と罪の両方があると思っています。本来、政治家は政策に対して理性的にしっかりと熟慮する。言葉を選んでものを語るべきです。政治というのは基本的に理性の積み上げなのです。ところが、田原的手法は、わざと激昂させて動物的な感情をあらわにさせ、それを見事に編集してきました。遠い政治、密室のプロの政治だったものに人間味を出すことによって身近にしてきたという功績は大きいですが、その一方で、ある種の娯楽性というものを作り出した罪も大きい。結果、政治が消耗品になってしまいました。理性によって感情を抑えるということが政治なり統治の基本なのですが、むしろ理性を捨てて感情を剥き出しにした方がテレビ的には受けます。感情と感情のぶつかり合いを演出するようになったのです。人間の剥き出しの感情をあえて煽るのです。
剥き出しの言葉、表情は感情であり、それは政治ではありません。喧嘩になってしまうのです。感情と感情のぶつかり合いを見世物として消費することを田原氏は深夜の討論番組「朝まで生テレビ!」で文化人の出演者を挑発することで身に付け、日曜朝の「サンデープロジェクト」で、政治家相手に実践するようになったのです。
実は、私も、慶應義塾大学助教授の時代と選挙特番以来、2013年2月23日に久しぶりに「朝まで生テレビ!」に出演しましたが、政治家に対する田原氏の手法はまだ健在でした。イエスかノーかで田原氏は政治家に迫りますが、イエスかノーかを簡単に決められないところに政治があります。まさに、矛盾と葛藤とトレードオフ(二律背反)にあえて、結論を出していくのが政治ですから、そんな鮮やかな結論にはなりません。交渉に交渉を重ねて、妥協といわれても、利害関係が絡み合う多様な関係の中で「暫定的な個別解」を一つ一つ決めていく泥臭い仕事です。その案件に着目した一定の答えをまずは出し、それを常に修正していくしかない。イエスかノーかで簡単に答えられることなら、役人でもできるし、やればいい。イエスかノーかで決着しない話だからこそ政治家の所に話が来るのです。
政治決断をすれば、特に、政治の最高責任者は、ぎりぎりの判断を迫られるので、 意見を採用してもらえない側も最大49%いるわけです。採用してもらえなかった側にメディアがマイクを向ければ、なんてひどい政治家なんだろうと話すでしょう。意見を採用してもらった側は、もう決着したのだから、そっとしておいて欲しいはずです。
たとえば、重大な政治決断すべき案件が三つあったとして、政権が下す判断を三つとも支持する人々というのは、確率的には、二分の一を三回かけあわせた八分の一ということになります。八分の七の人々は、三つのうち、一つ以上は判断に異を唱える。政権を担うということはこういうことなのです。耐えることだということを、長年政権についていた自民党はよくわかっています。そうした不満への対処の仕方も含めて長けていたのです。
さらに政治家は交渉を有利に進めるために打つ手を残しておきたいわけです。ところが、田原氏の前では「イエスかノーかその場で決断せよ」と迫られます。多くの視聴者には、回答を留保した政治家は決断力がない人間に映ってしまうので、政治家側もできるだけ、政策に関しての前向きな態度を見せようとする。野党は、対決姿勢をテレビの前では強調する。すると、打つ手がどんどん過激になり、選択肢を減らされてしまうのです。一騎打ちが大好きな日本人の好みに合わせて、田原氏は、どんどん一騎打ちの枠組みに追い込んでいく。見せ物として面白く仕立てていくのです。
しかし、テレビ発言(言質)を取られていなければ、対外交渉の場合でも、与野党協議の場合でも、違う妥協とか知恵が出ていたかもしれません。事前にテレビに出ることで、テレビでの発言に縛られて自縄自縛に陥ったり、非常に中途半端なことになったり、むしろ現場に混乱を与えたりといったことになってしまうのです。
私は、超党派の議員連盟の幹事長や事務局長をかなり多く引き受けています。特に、自民党の会長から、直接、指名をいただくことが多いです。現に、いくつもの議員立法や超党派政策を実現しているので、本当にまとめなければならない案件は、よく声がかかります。与野党の妥協を行なううえで重要なのは、大事な政策はなるべくメディア沙汰にしないということです。
メディアに注目された瞬間に、敵と味方に分断されて、言質を取られ、どんどん手が狭まるからです。メディア沙汰にならなければ、与野党で前向きに知恵を出し合い、現場が抱えている問題を一緒に解決しようという雰囲気が醸成され、交渉は大変うまく進みます。たとえば、民主党の松井孝治氏らがまとめたNPOなどの公益法人に対する個人の寄付促進税制の実現などがその典型です。これは、新しい公共という政策がメディアからあまり注目されなかったがゆえに、与野党協調が成功しました。あまり報道されていませんが、本当は、与野党が協力して前向きな仕事をたくさんしていますし、一年間の国会で成立する法律は約100本あり、そのうち、7~8割に対して有力与野党は賛成しているのです。でも、今のメディアが求める物語は、与野党が仲良く日本のために努力している姿は、画にならないので、無視されるということです。
◇「いただき」主義の元祖は田原総一朗
「朝まで生テレビ!」「サンデープロジェクト」のプロデューサーで、亡くなった日下雄一氏が、私が主催するインターネットテレビ「スズカンTV」に出演していただいたときに、田原的手法についてこう語ってくれたことがあります。
「田原さんはリアルタイムで編集している。その編集力は天才的。普通は全部撮って、そのあとに美味しいところを編集するのだけど、それをリアルタイムで、話をしながら頭の中で編集をしているからすごい」といっておりました。感情を引き出すような圧迫面接をするのは、早く起承転結の結のところにいきたいからなのです。地上波はとにかく頭が重要だから、美味しいところをリアルタイムで編集しているのだそうです。美味しいワンフレーズを取るがために全部、詰め将棋のごとくそこに照準を合わせていろんなとこから攻めていく。美味しいところが取れれば、あとはその話題はいらないので、人の話を聞かずに打ち切ろうとするわけです。
テレビマンの共通言語には「いただき」というのがあります。「今のコメントいただきました」「今の表情いただきました」という具合に使うのですが、その瞬間瞬間をいただいて、あとは編集します(「つまむ」といいます)。自分の世界観、コンテクストでつないでいくというのがテレビ記者の姿ですが、その原型ともいうべきものが、田原スタイルだったのです。「いただき」主義の元祖というべきかもしれません。
その一方で、私は学生のときから作家としての田原総一朗氏の大ファンです。実に良いルポをたくさん書いています。ペンの田原氏は、熟慮、理性の積み重ねを丹念に描き出す。彼が書いた本を読むと、丹念な取材に基づき、非常に精緻に丁寧に理性的にまとめてある。書物を読む限り、私の大好きなジャーナリストの鑑としての田原氏がそこにいる。ところが、地上波になると、楽屋では温かく人懐っこい田原氏が計算づくで、敢えて感情をあらわにさせようとするのです。CS波とかBS波といったミドルメディアでの進行ぶりも地上波テレビとはかなり異なり、これも熟議をしっかりファシリテーションされていて好感が持てるもので私もよく見ます。
この点は、90年代にニュースの時代を作った「ニュース23」の筑紫哲也氏とも対照的です。筑紫氏はペン(文章)のときもテレビのときも変わらなかった。ところが田原氏はメディアによって豹変します。田原氏は、三つの人格を使い分けているのかもしれません。本というメディアの特徴、地上波というメディアの特徴、BS波・CS波というメディアの特徴を完全に理解してそれを見事に使い分けている。逆にいうと田原氏ほどマスター・オブ・メディアリテラシーな人はいないということかもしれません。このため、田原氏に続こうと考える人はいるが、誰もこの三つの人格を真似できる人はいないのです。その後のキャスターたちは、追及する姿勢は威勢は良さそうに見えても、中身がなさそうに見えてしまうのです。
◇ステレオタイプな田原的手法の限界
ただし、マスター・オブ・メディアリテラシーといっても地上波におけるいただき主義の田原的手法の罪は大きいものがあります。地上波では本質的な議論ができないのです。映像が必要だという制約もあるためか、誰かゲストを呼んで来て話を聞くことを優先する必要が出てくる。このため、政策、つまり本質的な部分が二の次になってしまうのです。
いただき主義はステレオタイプに準拠したシナリオになります。「いただき」の発言を編集してつないでいくので、結局は、ステレオタイプの強化になるわけです。ステレオタイプにハマっていくと見ている方も分かりやすい。要するに政治に分かりやすさというものを過度にも求めるようになってしまったのです。もちろん、政治家はその努力はしなくてはいけませんが、本末転倒になってしまったのです。
その政策の本質的な部分、政治の背景を説明せずに、いただき主義で美味しいところだけを流すようになります。政治でいえば、政局です。誰と誰がケンカした、誰と誰がくっついたという話だけが美味しいということになってしまうのです。これはその後、編集技術の発達とともに、「TVタックル」として過剰な姿で現われます。「朝まで生テレビ!」で感情をあらわにしていた作家の野坂昭如氏が「TVタックル」で同様のキャラクターとして認知されるのは、その象徴的な動きかもしれません。
また、「朝まで生テレビ!」の手法を引き継いだのが、私もその切れ味は評価している猪瀬直樹東京都知事といえるかもしれません。ジャーナリスト時代は常に一つの問題に焦点をあて、腰を入れて取材し、マスメディアに話題を提供する姿勢は田原氏に通底するものがあります。ただ、田原的手法は次の世代が換骨奪胎、縮小再生産されています。
ほかにも、剥き出しの感情をあらわにさせて視聴率を取るという手法は、「サンデープロジェクト」の司会をしていた島田紳助氏が本音で物事を語るということで人気を博したことにも共通しています。日本テレビ「行列のできる法律事務所」では、弁護士たちに感情を剥き出しにさせ、プライベートまで赤裸々にさせて、視聴率を稼ぐようになります。この番組で人気を得たのが、橋下徹大阪市長ですが、現われるべくして現われた、当然の流れなのかもしれません。
なお、田原的手法の最大の問題は、その後、取材する若い記者たちが、いただき主義に陥ってしまったことです。何か美味しいコメントが取れればそれでいい。その深い背景は特にいらないという姿勢になってしまいました。この点が、経緯も裏も表も中味も分かったうえで演出手法としてやっている田原氏と、中味も歴史も知らずに形だけマネしているテレビ記者との大きな違いです。さらに美味しいワンフレーズコメントであれば、政治家にとっては失言といったマイナスのものでも何でもいいという態度になってしまいました。中身の伴わない「ミニ田原化」です。記者の多くがミニ田原化して、ワンコメントの失言を追う時代になっていきます。


その他の記事

|
ハロウィン:あの世とこの世の境界線が曖昧になるとき(鏡リュウジ) |

|
最近ハゲ関連が熱い、あるいは新潟日報と報道の問題について(やまもといちろう) |

|
コデラ的出国前の儀式(小寺信良) |

|
日本の未来の鍵は「日韓トンネル」と「日露トンネル」(高城剛) |

|
コロワイド買収のかっぱ寿司が無事摘発の件(やまもといちろう) |

|
役の中に「人生」がある 俳優・石橋保さん(映画『カスリコ』主演)に訊く(切通理作) |

|
歩き方の上手い下手が人生を変える(岩崎夏海) |

|
【ダイジェスト動画】名越式仏教心理学を語る(名越康文) |

|
NAB2017でわかったHDRのインパクト(小寺信良) |

|
日本はポストウクライナ・ロシア敗戦→崩壊「後」に備えよ、という話(やまもといちろう) |

|
無意識の中にある「他者への期待」–その功罪(名越康文) |

|
『デジタル時代における表現の自由と知的財産』開催にあたり(やまもといちろう) |

|
オーバーツーリズムでニセコ化する草津(高城剛) |

|
中国マネーが押し寄せる観光地の今(高城剛) |

|
「蓮舫代表辞任」後の民進党、野党、ひいては反自民について考える(やまもといちろう) |