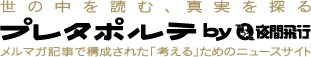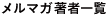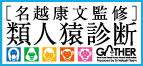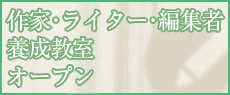「俺が責任を取る」ということ
平川:言葉狩りについては、実際には出版社にしても新聞社にしても、真剣に「これは差別にあたるだろうか」と考えて言葉を選んでいるわけじゃなくて、「あそこもやっているからうちも」ということで忖度してやっちゃう、ということだと思うんです。
そこで「大人」が必要なんだと思うんですね。「いや、責任は俺がとるから<障害者>で行こうよ」というふうに引き受ける大人がいないと、どこまでも「正義の横行」に対する歯止めがかからなくなってしまうんですよ。
小田嶋:実際「障碍者」とか「障がい者」なんて書くほうが、「障害者に気を遣ってますよ」というのが行間に書いてあるようで気味が悪いですよね。おばあさんに話しかけるときに、わざと小腰をかがめてしゃべる女子アナみたいで。「そんなに小さくならなくていいじゃないの」と思うんだけど。
「障害者」を「障がい者」と書くのって、そういう気持ち悪さがあるんですよね。
平川:小田嶋さんはそういうことに敏感だよね。でも、実際には、あらゆる言葉には侮蔑が入っているんだから、そんなこと言い始めたらしゃべれなくなるんだよね。
小田嶋:そうですよ。「八百屋」と口にしたとき、侮蔑のニュアンスがあるとしたら、それは言葉に宿っているんじゃなくて、それを口にしている我々の中に、八百屋という職業を軽んじている気持ちがどこかにあるんです。「八百屋」を「青果販売業」と言ったところで侮蔑がなくなるかというと、そんなことはない。
平川:むしろ、二重に侮蔑がこめられることになるんです。
小田嶋:だいたい、自分の中に相手を侮蔑する気持ちがあるときほど、それを隠すときに過剰な敬語を使うんですよね。「障がい者の方がいらっしゃいました」というふうに。「医者の方がいらっしゃいました」と言わないのは「医者が来た」が侮蔑にならないと思っているからです。
平川:言葉って常に両義的で、その都度、その言葉に込められたニュアンスとか、文脈をつかまなければ真意はつかめませんからね。
小田嶋:言葉狩りをする人って、その手間を省きたいんですよ。「ヘアヌード」なんかもそうですが、「毛が見えていたらダメだ」みたいな基準を作ったほうが、取り締まるのが楽ですからね。本当は毛が見えていても健全なものもあれば、毛が見えていなくてもまずいものもある。それは文脈からしか判断できませんが、手間がかかるし、文化的蓄積がなければ文脈を読む、ということができない。
平川:剃ってりゃいいのかって話だよね(笑)。
小田嶋:そうですよ(笑)。
こっそりと、息子の合格発表を見に行った
小田嶋 平川さんがご自分のお父さんを介護された体験を書かれた『俺と似た人』の中で、若い頃、お父さんにとにかく反発していた、ということを書かれていました。平川さんの世代までは、父親との対決というのは明確な主題だったと思います。親父っていうのは息子に対してすごく封建的で、強圧的で、押さえつけようとする。息子のほうも、そういう親父が嫌で嫌でしょうがないから、打ち倒そうとして反発する。
そういう父と子の葛藤があるなかで、大人って嫌なものだ、不愉快なものだって思うわけです。で、自分が大人の番になると今度は子供を抑圧したりするわけですが、とにかくそういう親子の葛藤みたいなものが、原体験としてあった。
ところが今は、そういう「父子の対決」みたいなものがほとんど消え去りつつあるのだと思うんですよ。
例えば、今の高校生は、大学受験でどこを受けるかを親父に相談するそうですよ。
平川:そうなんだよ。あれ、気持ち悪いんだよね。
小田嶋:「どうしようかな」「○○大はこうだから、こっちにしたらどうだい」っていう会話を親子でする、というのは本当に最近のことですからね。これは実は『困ってる人』の著者の、大野更紗さんから聞いた話なんです。彼女は東京に来たときに、同世代の人がみんないろんなことを親に相談しているのを知って驚いたらしいんですね。
もちろん彼女は若いから、私たちに比べれば親子の関係はずっとフラットだと思います。ただ、彼女は福島の山奥の生まれで、「親は田舎者で何にも知らないから全部自分でやらなきゃいけない」という意識が強かった。「親とは話が通じないものだ」と思っていたから、都会の大学生が、みんな親といろんなことを話しているのに驚いた、というわけです。
私たちとしては、大野さんの感覚のほうが当たり前のように思ってしまうけれど、そこはかなり変化があるのだと思います。
平川:僕の世代だと、大学の合格発表に親が見に来るなんてありえないことでしたからね。ただ、ずいぶん後になってから、実は僕の父親は、僕の合格発表をこっそり見に来ていた、という話を聞いてね。ずいぶん驚きました。
小田嶋:その「こっそり」というのがおもしろいところだと思うんです。親子の間に上下関係があって、超えがたい距離があったということは、別に子供のことに無関心であることを意味しない。むしろ今よりも強い関心を持っていた可能性すらあると思うんです。
例えば私の父親は高等小学校卒ですから「子供を大学入れる」ということには、執念に近いような感情を持っていたんだと思います。そのことを決して口には出さなかったけれど、子供心に親父の「無言の執念」みたいなものを肌で感じて嫌だなあ、と思っていたくらいです。
ただ、それだけ強い思い入れがあっても、私の親の世代だと「子供の大学受験ごときでいそいそと発表を見に行く」というのは大人として、照れくさかった。そういうことをするのは「大人ではない」と思っていたわけです。
私の世代は、平川さんに比べると親子関係はフラットになりつつあったので、合格発表を見に行くときに父親の車で送ってもらいました。でも、決して積極的ではないんですね。「合格発表? しょうがねえな。連れてってやるよ」みたいな雰囲気を出すわけです。今思うと、本当は親父のほうがワクワクしていたんですが。
そして、私自身が親になったときには、自分の子供の大学受験の合格発表を当たり前のように見に行くようになりました。もう大学に入ることは珍しくもないし、私の父親のように「なんとしても子供を大学に入れる」という執念を燃やしている人もそれほどいない。ところが、合格発表を見に行くか見に行かないかということでいうと、確実に私たちの世代のほうが見に行くようになった。
平川:それはとっても、おもしろい話だよね。
小田嶋:そうですね。つまり、親子関係がフラットになって、抑圧的なものじゃなくなってくるに従って、子供は親に進路相談するようになってきたし、親は子供の合格発表に足を運ぶようになってきた。でもそれは別に、親子の愛情みたいなこととは、関係ないっていうことなんですよね。

その他の記事

|
週刊金融日記 第283号 <ショート戦略を理解する、ダイモンCEOの発言でビットコイン暴落他>(藤沢数希) |

|
準備なしに手が付けられる、ScanSnapの新作、「iX1500」(小寺信良) |

|
効果がどこまであるのか疑問に感じるコロナ対策のその中身(高城剛) |

|
「キャラを作る」のって悪いことですか?(名越康文) |

|
パーソナルかつリモート化していく医療(高城剛) |

|
「リボ払い」「ツケ払い」は消費者を騙す商行為か(やまもといちろう) |

|
ソニーが新しい時代に向けて打つ戦略的な第一手(本田雅一) |

|
アフリカ旅行で改めて気付く望遠レンズの価値(高城剛) |

|
中部横断自動車道をめぐる国交省の不可解な動き(津田大介) |

|
「見るだけ」の製品から「作ること」ができる製品の時代へ(高城剛) |

|
子育てへの妙な圧力は呪術じゃなかろうか(若林理砂) |

|
受験勉強が役に立ったという話(岩崎夏海) |

|
「実は言われているほど新事実はなく、変わっているのは評価だけだ」問題(やまもといちろう) |

|
ママのLINE、大丈夫?(小寺信良) |

|
「ネットが悪い」論に反論するときの心得(小寺信良) |