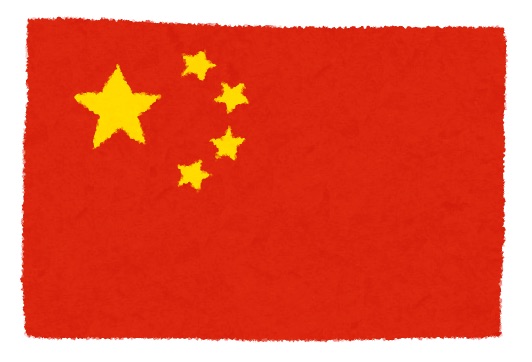
もうすでに多くの識者が指摘し始めている内容ではありますが、中国海警法が2月1日というややイレギュラーなタイミングで施行される運びとなり、日中間で曖昧な海域が残されていることもあって日本海や尖閣諸島が実質的なターゲットになっているのではないか、という議論が湧き起っています。
なぜか中央日報まで特報で出していて、何やねんと思うわけですが。
当然のことながら、我が国でも尖閣諸島の実効支配を守るためにどうするのか、あるいは、日本海の大和堆周辺の海上保安庁の活動強化をどうするかという議論が湧き起るわけですけれども、施行の時期はともかく国家主席・習近平さんが海警組織を政府管轄から人民解放軍傘下とし、実質的な第二海軍としたうえで武装解禁をするであろうことは充分に予測されてきたことを考えると、我が国の対応は「あまりにも遅い」と批判されても仕方がないところではあります。
カラクリとしては、中国の領海が曖昧なところはほぼ日本近海に限られるのは当然として、これらの中国海警組織は第一列島線から太平洋に張り出し実質的な中国の自由航行圏を広げるという非常に合目的で直線的な拡大戦略にあると言えます。
中国の拡大戦略は単純に領土・領海面ではなく、統治能力の質的強化に向いているのは明白です。おそらくは、中国はいままでの皇帝政治とあまり変わらないメカニズムで中国共産党が最上位に君臨し、習近平さんを実質的な皇帝としたうえで、いわゆる「国」が統治意思決定機関ではなく「皇帝が差配する党」が行う形です。党からすれば、極論ではありますが中国という国家がどうであろうが問題なく、その国の中で異民族や隣接する外国との紛争は党が支配する人民解放軍や海警のような武力組織が統括できればそれで良い、とも言えます。
感染症対策で中国が国民に対して思い切った隔離や都市封鎖ができるのも、国民が暮らす社会や経済よりも、まずは共産党の統治能力が確保され混乱や反動なく感染症が先に抑え込めればよいという中国らしい統治論が背景にあることは間違いがありません。
我が国は中国の隣国として、経済的な互恵関係を維持しつつアメリカとの軍事同盟をバックに地域での安全保障を担保してきました。しかしながら、アメリカが急速に中国との対立を深めていくなかで、中国人が考える「自衛」が結果として周辺への拡大戦略に直結し、いかに周辺地域や少数民族を圧迫するとしても、外交的にあそびのないジェノサイド認定まで踏み込んでいくことが日本の将来の外交的オプションを増やす一助になるのか、というあたりはもっと議論されて然るべきかと思います。
他方、今回の海警に関しては明らかに日本が主たる標的の一つである以上、積み残された議論はしっかりと踏まえていく必要があります。それもこれも、アメリカ・トランプ政権の東アジア外交が必ずしもアメリカのみならず日本、韓国ほか諸外国の安全や国益に資さない部分もあった、ということの裏返しでもあります。
そのトランプ政権が末期にあれだけの混乱を起こし、アメリカ政治に大きな分断の爪痕を残してバイデン政権に移行したことを考えると、中国からすれば「これはチャンス」と大きなポイントを着実に上げられるボーナスステージの総仕上げとして、海警法の策定、施行までもっていったことでもあります。その点では、日本にとっては痛い失点となったばかりでなく、ただでさえ財政的なリソースがコロナ対応などで逼迫していくところでコーストガードの予算までもが積み増される恐れがあるのだとすると、相当なことをこれから手がけていかなければならないという危機感を感じます。
やまもといちろうメールマガジン「人間迷路」
Vol.Vol.321 中国海警法という深刻な問題に危機感を覚えつつ、コロナ対策やITセキュリティを巡る迷走のあれこれを語る回
2021年1月30日発行号 目次

【0. 序文】バイデン政権移行中に中国が仕掛ける海警法の罠
【1. インシデント1】コロナ対策からワクチン接種へと動くムーブメントで露呈する官邸の「目詰まり」
【2. インシデント2】ITセキュリティとITリテラシー
【3. 迷子問答】迷路で迷っている者同士のQ&A
やまもといちろうメールマガジン「人間迷路」のご購読はこちらから



その他の記事

|
身体に響く音の道――音の先、音の跡(平尾文) |

|
参院選ボロ負け予想の自由民主党、気づいたら全党消費税減税を叫ぶポピュリズム政局に至る(やまもといちろう) |

|
寒暖差疲労対策で心身ともに冬に備える(高城剛) |

|
ドイツの100年企業がスマートフォン時代に大成功した理由とは?(本田雅一) |

|
急速な変化を続ける新型コロナウィルスと世界の今後(高城剛) |

|
なぜ人は、がんばっている人の邪魔をしたくなるのか(名越康文) |

|
急成長SHEINを巡る微妙で不思議な中華商売の悩み(やまもといちろう) |

|
ドラマ『ハウス・オブ・カード』〜古くて新しい“戦友”型夫婦とは(岩崎夏海) |

|
米国の変容を実感するポートランドの今(高城剛) |

|
「キモズム」を超えていく(西田宗千佳) |

|
「レゴとは、現実よりもリアルなブロックである」(宇野常寛) |

|
「スルーする」ことなど誰にもできない――過剰適応なあなたが覚えておくべきこと(名越康文) |

|
日本が抱える現在の問題の鍵はネアンデルタール人の遺伝子にある?(高城剛) |

|
温泉巡りで気付いた看板ひとつから想像できる十年後の街並み(高城剛) |

|
『心がスーッと晴れ渡る「感覚の心理学」』著者インタビュー(名越康文) |



























