寝転んで、お腹を掻きながら
「おとな学」なんていうタイトルで、原稿を書いているわけですが、じっさいのところ「おとな」を定義するものなどはないのです。
まさに、ヘーゲルがいうように「王が王であるためには、家臣がいるから」というほかはありません。「おとながおとなであるためには、こどもがいるから」ということですね。では、こどもとは何かということになりますが、こちらの方も定義することなどはできません。「こどもがこどもであるためには、おとながいるから」という他はないのです。
現代という時代は、このこどもとおとなの境界線があいまいになった時代だといえるだろうと思います。その理由は様々あるのでしょうが、わたしは市場経済の隆盛というものが、大きな理由のひとつではないかと考えています。
今回はそのことをご説明しましょう。
もともと、定義も公準もない「おとな」とか、「こども」といった言葉をめぐっての考察ですので、科学的な根拠のある話ではありませんし、何か答えが出てくるような問題でもありませんので、寝転んで、お腹でも掻きながら、お読みいただければ結構です。
寝転んで、お腹を掻きながら、書物を読むというのは、実はわたしが描いているおとなのイメージでもあるわけです。こどもはそんなことしませんからね。

その他の記事

|
雨模様が続く札幌で地下街の付加価値について考える(高城剛) |

|
米豪だけでなく日露も導入を見送る中国通信機器大手問題(やまもといちろう) |

|
「直らない癖」をあっという間に直す方法(若林理砂) |

|
僕がネットに興味を持てなくなった理由(宇野常寛) |

|
「試着はAR」の時代は来るか(西田宗千佳) |

|
世界遺産登録を望まない、現代の隠れキリシタンたち(高城剛) |

|
安倍政権の終わりと「その次」(やまもといちろう) |

|
チェルノブイリからフクシマへ――東浩紀が語る「福島第一原発観光地化計画」の意義(津田大介) |

|
あれ? これって完成されたウエアラブル/IoTじゃね? Parrot Zik 3(小寺信良) |

|
山口組分裂を人事制度的に考察する(城繁幸) |

|
“今、見えているもの”が信じられなくなる話(本田雅一) |

|
猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉 第6回:椅子に固定されない「身体の知性」とは何か(宇野常寛) |

|
宇野常寛特別インタビュー第4回「僕がもし小説を書くなら男3人同居ものにする!」(宇野常寛) |

|
ドラマ『ハウス・オブ・カード』〜古くて新しい“戦友”型夫婦とは(岩崎夏海) |
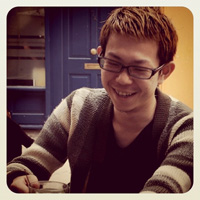
|
『エスの系譜 沈黙の西洋思想史』互盛央著(Sugar) |

























