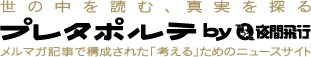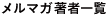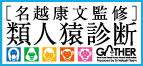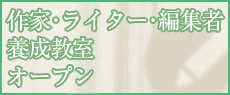◇イエスかノーかを迫る田原総一朗の新手法
88年にはリクルート事件が起き、政治の有力者が次々とテレビメディアから追及されるようになります。89年の昭和天皇崩御とベルリンの壁崩壊のニュースは、視覚的にも強い印象を与えた時代を象徴しています。
ニュースを流すことでも視聴率が取れるという時代に突入したわけです。政権に批判的なコメントをする久米宏氏がキャスターを務める「ニュースステーション」の成功から、わかりやすさを重視するとともに、それまでの政治への批判の姿勢が強まります。田中派(その後竹下派)への密室政治批判を展開していきます。
91年10月には象徴的な出来事として、「小沢面接」事件があります。自由民主党総裁選挙において海部俊樹首相の後継総裁を争った宮澤喜一氏、渡辺美智雄氏、三塚博氏を自らの事務所で面接を行なった小沢一郎氏は当時の竹下派の威光を傘にきた人物としてテレビメディアが批判的に報じたのです。92年には、東京佐川急便事件が発覚し、疑惑が取り沙汰された金丸信自民党副総裁をテレビメディアは激しく批判します。旧態依然たる田中派(竹下派)の密室政治を批判することで、視聴率を稼ぎ、政治にわかりやすさを求めたのです。この頃からテレビならではの二分法が始まったといえます。
この時代に人気を博したのは、89年4月にスタートしたテレビ朝日「サンデープロジェクト」です。当初は政治だけでなく、プロ野球選手や文化人のゲストも招くバラエティ番組でしたが、毎週、政治家を呼ぶ形式に変更されます。
政治家にインタビューをするのは田原総一朗氏。すでに田原氏は87年4月からスタートして「天皇制」や「原発」など様々なテーマを取り上げ、物議をかもしていた「朝まで生テレビ!」の司会をしていました。この番組では、映画監督の大島渚氏、小説家の野坂昭如氏、思想家の西部邁氏といった出演者を挑発し、本音を引き出すスタイルでしたが、それを「サンデープロジェクト」という形で政治家相手にもその手法を持ち込むようになったのです。
政治家を次々にスタジオに呼ぶ。政治の裏側を説明させて、政権にイエスかノーかを表明させる。出演依頼を断った政治家がいれば、「断られた」事実を公表する。「もし異論があるならば、スタジオに電話をかけるか、来週出演するか」を迫ったのです。
田原氏の質問は鋭く、93年には時の宮澤喜一首相に『総理と語る』でインタビューした際に、政治改革関連法案をめぐって、「今の国会でやるんですか?」と詰め寄り、「やるんです。何としても成立させたい」との発言を引き出しましたが、この発言は党内調整前の勇み足発言となり、これがきっかけで、党内分裂につながったほどです。
この時代の二分法は「自民」か「非自民」かでした。この二分法のロジックの中で颯爽と登場したのが、細川護熙氏です。93年の非自民8党派連立政権で首相となった細川護熙氏(首相在任期間93年8月~94年4月)は記者会見ではプロンプターを駆使し、記者をペンで指名する……さっそうとしたメディア戦略で「初代メディア宰相」とも評されました。
ただし、この動きには下野した自民党も反発します。9月21日、日本民間放送連盟の第6回放送番組調査会の会合でテレビ朝日報道局長の椿貞良氏が「非自民」側を利するような発言をしたと産経新聞が10月13日に報じ、政治問題化します。不偏不党を理念とする放送法に反するものではないかと、放送免許の取り消しさえも示唆されたほどです(最終的には行政処分となりました)。テレビ局が政治に対して影響力を行使するようになったのです。
◇時代を動かす広告代理店電通と小沢一郎
この時代の政治に対し、テレビが大きな影響力を持った理由は、三つの大きな動きが重なったためといえるかもしれません。その三つの大きな動きとは広告代理店電通、小沢一郎氏、田原総一朗氏です。
まず、電通はニュースで視聴率が取れるということを「ニュースステーション」で証明しました。広告代理店のテレビ局における役割はテレビ番組にスポンサーを連れてくることです。ニュース番組である「ニュースステーション」に多くのスポンサーを集めてくることに成功したのです。キャスターである久米宏氏は04年の「ニュースステーション」を辞める直前のコメントでは電通への謝辞を口にしたほどです。
これが成功例となり、各局でニュース番組が大々的に始まります。政治家をゲストに呼んで質問するというのも、一般的になってきたのです。ただし、この動きは政治家を消費する動きにつながっていきます。支持率が高い間は政治家をもてはやして視聴率を上げようとしますが、支持率が低くなると、バッシングをして視聴率を上げようとする動きにつながるのです。その象徴的な事例が細川護熙政権です。首相在任期間は1年に満たずに、最後はバッシングの対象となりました。まさしく消費の対象となったのです。
次に大きな動きの二つめ。小沢一郎氏です。もともとは、「小沢面接」事件に代表されるように、田中角栄氏の直系で竹下派でも大きな権限を持っていましたが、92年の東京佐川急便事件などで、有権者からの批判が高まり始めると、政治改革、選挙制度改革を打ち出し、自民党を離党します。このときに小沢氏は執筆論文の中で自らを「改革派」とし、反対する勢力を「守旧派」と二分法のレッテル貼りを打ち出し、各メディアがこのフレームワークに乗ったために成功します。その結果、自民党を下野させ、93年の非自民8党派連立政権を誕生させたのです。
その後、小沢氏は新生党、新進党、自由党、民主党と渡り歩きます。90年代まではメディア対応にも成功していたように見えますが、00年代以降はバッシングの対象になり始めます。
この頃には私も同じ民主党内にいました。民主党と自由党の合併後、小沢氏が直接関わっていない話まで、さも、すべてを牛耳っているかのように、小沢氏のステレオタイプがどんどんメディアによって虚像として広まっていきました。メディアには過剰に小沢発言が取り上げられた。なぜこんなに小沢発言が露出するのだろうかと考えたことがあります。
やはり、メディアとの関係が変わってきたのではないでしょうか。小沢氏は田中角栄氏の直系ですから、田中氏を見習い、47歳で自民党幹事長就任後、メディアとの間に関係を作っていったはずです。その頃は同年代だった記者たちも、90年代になると役職付きになり、社内で実力を持ってきます。しかし、00年代になると定年退職の時期を迎え、社内には小沢系の記者はどんどんいなくなっていった。このために00年代以降、小沢バッシングが強まったのではないでしょうか。
小沢氏と同年代を生きた代表的なテレビ局社員でいえば、元フジテレビプロデューサーの澤雄二氏(公明党元参議院議員)がいます。フジテレビ入社後、報道局政治部などに在籍し、プロデューサーとして「スーパータイム」や「報道2001」などを立ち上げます。「報道2001」では小沢氏を頻繁に出演させました。93年には報道センター編集長に就任します。しかし、00年代に入ると、国際局次長を務めたあとに、03年には公明党からの出馬要請を受け、フジテレビを退職するのです。04年7月の参議院議員選挙に東京選挙区から公明党公認で立候補しますが、「議員任期中に66歳を超えない」という理由で10年に引退しています。このように、同時代のメディア関係者が第一線から退きつつあるためにバッシングが強まったのでしょう。
また、小沢包囲網もあったようです。参議院議員を務めた平野貞夫氏は『平成政治20年史』(幻冬舎新書)で、96年に始まる小沢包囲網の動きを紹介しています。
【総選挙が終わると国会の内外で小沢潰しが活発化した。もっとも陰湿なのは、竹下元首相の指示で、『三宝会』という秘密組織がつくられたことだ。新聞、テレビ、週刊誌などや、小沢嫌いの政治家、官僚、経営者が参加して、小沢氏の悪口や欠点を書き立て、国民に誤解を与えるのが狙いであった。現在でもテレビ等で活躍している人物がいて、いまだにその影響が残っている】
この頃からメディアの小沢アレルギーは始まっていたのです。


その他の記事

|
ウクライナ問題、そして左派メディアは静かになった(やまもといちろう) |

|
大観光時代の終焉(高城剛) |

|
人間はどう生きていけばいいのか(甲野善紀) |

|
「まだ統一教会で消耗しているの?」とは揶揄できない現実的な各種事情(やまもといちろう) |

|
在宅中なのに不在票? 今、宅配業者が抱える問題(小寺信良) |

|
人生のリセットには立場も年齢も関係ない(高城剛) |

|
「あたらしいサマー・オブ・ラブ」の予感(高城剛) |

|
ドラッカーはなぜ『イノベーションと企業家精神』を書いたか(岩崎夏海) |

|
「見て見て!」ではいずれ通用しなくなる–クリエイターの理想としての「高倉健」(紀里谷和明) |

|
週刊金融日記 第274号 <小池百合子氏の人気は恋愛工学の理論通り、安倍政権の支持率最低でアベノミクスは終焉か他>(藤沢数希) |

|
Amazonプライムビデオの強みとは(小寺信良) |

|
「コンテンツで町おこし」のハードル(小寺信良) |

|
これからの日本のビジネスを変える!? 「類人猿分類」は<立ち位置>の心理学(名越康文) |

|
人は何をもってその商品を選ぶのか(小寺信良) |

|
本当の「ひとりぼっち」になれる人だけが、誰とでもつながることができる(名越康文) |