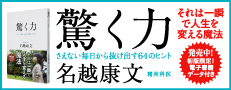驚きとは、システムのほころびを愛でること
驚きとはいわば、「意識と無意識の間に張られた糸が震える音」です。
意識を「システム化された世界」、無意識を「システム化される以前の世界」と言い変えれば、僕らが高度にシステム化された世界を生きる中で「驚き」を失ってきたことがわかります。そもそも、「社会をシステム化していく」というのは、社会から驚きの契機を奪っていく、ということにほかならないのです。
でも、ここがおもしろいところで、どれほど社会をシステム化しようとしても、人間のやることである以上、必ずそこに綻びが生じる。むしろシステム化すればするほど、システムはときに大きく崩れる危険をはらんでいくわけです。
その瞬間、システム化された世界とシステム化される以前の世界の間に張られた糸が「ビィィイン!」と鳴る。その音を耳にした人の心に生まれるのが「驚き」です。
つまり、驚きというのはシステムの崩壊を察知したときに生じる感覚であり、「驚く力」とは、その「音」にどれだけ注意深く耳を澄ませられるかということだといえます。これは、いまの高度にシステム化された社会の中で、僕らがどう生き抜くかを考えるときには避けることのできないキーワードです。
ではどうやって「驚く力」を取り戻していくか。多くの表現者が取り組んでいる課題は、実はそれだと僕はとらえています。そういう目でみると例えばビートたけしさんが『アウトレイジ』『アウトレイジビヨンド』で過剰な暴力を描くのも、松本人志さんが『R100』で、極端なSMの世界を描くのも、極限までシステム化された世界にどう対抗していくかという課題に対する模索であるように僕には思える。
彼らはおそらく、人間の感情の根幹である「共感」までもがシステム化されてしまう社会に息苦しさを感じ、危機感を抱いている。そして、そういうシステムから自由になるためには、「驚く」ということ、すなわち、瞬間的に「心」を崩壊させる必要がある、ということなんだと思うんです。


その他の記事

|
99パーセントの人が知らない感情移入の本当の力(名越康文) |

|
世界的観光地が直面するオーバーツーリズムと脱観光立国トレンド(高城剛) |

|
日本の音楽産業が学ぶべきK-POP成功の背景(高城剛) |

|
「表現」を体の中で感じる時代(高城剛) |

|
スーツは「これから出会う相手」への贈り物 (岩崎夏海) |

|
女の体を、脅すな<生理用ナプキンの真実>(若林理砂) |

|
J.K.ローリングとエマ・ワトソンの対立が示すトランスジェンダー論争の深刻さ(やまもといちろう) |

|
「深刻になる」という病(名越康文) |

|
責任を取ることなど誰にもできない(内田樹) |

|
宗教や民主主義などのあらゆるイデオロギーを超えて消費主義が蔓延する時代(高城剛) |

|
古くて新しい占い「ルノルマン・カード」とは?(夜間飛行編集部M) |

|
少ない金で豊かに暮らす–クローゼットから消費を見直せ(紀里谷和明) |

|
少子化問題をめぐる日本社会の「ねじれ」(岩崎夏海) |

|
心身を整えながら幸福のあり方を追求する新年(高城剛) |

|
教育にITを持ち込むということ(小寺信良) |