日常から「死」が排除されたことの弊害
そうやって「死」を看取った後、残された人は激しい喪失感に襲われます。近年、この問題は「グリーフワーク」として取り上げられるようになりました。グリーフワークというのは、身近な人を亡くした人のための心のケアです。最近特に、小さいお子さんや年若い兄弟など、予想外に早く亡くなってしまった人の死を受け止められない人へのグリーフケアが、注目を集めています。
僕は、それ自体は大切な取り組みだと思います。ただ、一歩引いたところから見れば、それだけではおそらく、十分ではないだろう、とも思うんです。なぜならこの問題は、そうした「一部の不幸な人」を対象としたものではなく、僕ら全員の「死に対する準備不足」に原因を持つ問題だと思うからです。
残酷なことを言うようですが、僕らはみんな、この「身近な人を喪う悲しみ」の問題への対応について「手遅れ」です。少なくとも「手遅れである」という認識からスタートしないといけない状態にある、と僕は考えています。
例えるなら、いま、これを読んでいるあなたのところにいきなり何人かの人が訪れて車に乗せられ、「今から高層ビルの屋上からスカイダイビングしてもらいますから」とパラシュートを背負わされ、それ以上詳しい説明もないまま、ビルの屋上から背中を押されるような状況だといえばいいでしょうか。それくらい、僕らは「死に向き合う準備」をしないまま、年を重ねているのです。
僕らには、「死」に触れる体験も、知識も、準備もまったく足りません。「身近な人の死に対する備え」という点で、僕らの備えは本当に心もとないものです。そんな状態で身近な人を亡くしてしまったらどうなるか。そういうクライアントを前にしたときのカウンセラーとしての僕の、本当に正直な感想は「申し訳ない、打つ手は何もありません」というものなんです。
教育としてのグリーフワーク
僕らの文化は近年、徹底して「死」を排除してきました。その結果として、僕らは死に対して非常に脆弱になってしまった。もちろん、どんな人間にとっても「身近な人の死」は大きな衝撃をもたらします。だからこそ、僕らは文化の中で「死」になじんでおく必要があるのです。
死になじむための文化装置としてすぐに思い浮かぶのは「お葬式」や「法事」ですが、それだけではありません。例えば「祭り」というのは古来、「死の疑似体験」という機能を担ってきました。お祭りの多くは夜行われますが、あれは、「闇の中での提灯の光」というしつらえが、「死」のメタファーとして機能しているからです。しかし、現在ではそうしたものがどんどん形骸化して、「死のレッスン」としての機能を果たさなくなっているように思います。
「グリーフワーク」という形で、なんとかして「死を受け入れる」プログラムが行われるようになったことは良いことです。しかしそれが「身近な人を失った人」を対象にしている限りは後手に回らざるを得ない。必要なのは、幼いころからの、いわば「基礎教育としてのグリーフワーク」に取り組むことだと思います。
グリーフワークという言葉から、僕らは普通、「大切な人を亡くし、心が傷ついている人」をターゲットとして、「その人たちをどうケアするか」という枠組で問題を捉えてしまいがちです。もちろん、それも取り組むべき課題であることは間違いありません。ただ本来、グリーフワークはそうした「特定の人」に向けるのではなく、すべての人を対象としたものである必要がある。
なぜなら、僕らはみな、必ず死ぬからです。
そういう意味では、グリーフワークの問題は、「教育問題」として捉え直すべきだろうというのが僕の考えです。


その他の記事

|
今週の動画「陰の影抜」(甲野善紀) |

|
変化が予測できない時代(本田雅一) |
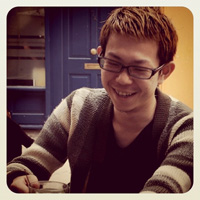
|
『エスの系譜 沈黙の西洋思想史』互盛央著(Sugar) |

|
数年後に改めて観光地としての真価が問われる京都(高城剛) |

|
百田尚樹騒動に見る「言論の自由」が迎えた本当の危機(岩崎夏海) |

|
ヘヤカツオフィス探訪#01「株式会社ピースオブケイク」前編(岩崎夏海) |

|
柔らかい養殖うなぎが美味しい季節(高城剛) |

|
あらゆる気候変動を想定しなければならない時代(高城剛) |

|
米国の未来(高城剛) |

|
コデラ的出国前の儀式(小寺信良) |

|
IoTが進めばあらゆるモノにSIMの搭載される時代がやってくる(高城剛) |

|
衰退する日本のパラダイムシフトを先導するのは誰か(やまもといちろう) |

|
レジームの反撃を受けるベンチャー界隈と生産性の今後(やまもといちろう) |

|
人間の場合、集合知はかえって馬鹿になるのかもしれない(名越康文) |

|
2021年は、いままで以上に「エネルギーと環境」が重大な関心事になる年に(やまもといちろう) |



























