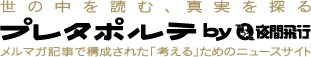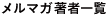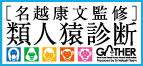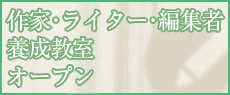ロバート・ハリスメールマガジン『運命のダイスを転がせ!』Vol.016より
『運命のダイスを転がせ!』ご購読の申し込みページはこちら。(「定期購読する」の緑ボタンを押して、各情報を入力すると購読申し込みできます)ご購読から一ヶ月は無料です!
月会費制サロン『人生というゲームを楽しむためのロバート・ハリスによるサロン』が2016年2月よりスタート!公式サイトはこちらです。
1964年の春、FENを流すスピーカーから
不思議な声の歌が聴こえてきた
ボブ・ディランの歌を初めて耳にしたのはたしか1964年の春だったと思います。
横浜のセント・ジョセフ・カレッジに通っていたぼくは放課後、遊び仲間たちと元町のシェルブルーというレストランでハンバーガーを食べながら何かの話で盛り上がっていました。それは、出たばかりのローリング・ストーンズのアルバム『ザ・ローリング・ストーンズ』についてだったかもしれないし、土曜日にYCAC(横浜カントリー・アンド・アスレティックス・クラブ)で開催されるダンスパーティの話だったかもしれないし、だれかのガールフレンドの話題だったかもしれません。何はともあれ、ぼくたちはコークを飲み、ハンバーガーを頬張り、取り留めのない話に花を咲かせていました。
店ではいつものようにFEN(アメリカの駐留軍のラジオ局FAR EAST NETWORKの略)の音楽番組が掛かっていて、ポップソングが次々とスピーカーから流れていました。ボビー・ライデルの「Forget Him」とか、ビートルズの「抱きしめて」とか、メアリー・ウェルズの「My Guy」とか、ディクシー・カップスの「Chapel of Love」とか、そういったポップソングです。
その時、不思議な声をした男性シンガーの歌が耳に飛び込んできました。これが「風に吹かれて」でした。それまでのポップシンガーの甘い歌声とは一線を画した、鼻から抜ける変わった声がぼくたちの会話を一瞬にして止めました。
「何こいつ。変な声」友人の遠藤が鼻で笑いながら言いました。
「歌も下手くそ!」友人の鈴木も呆れたという顔をして吐き捨てるように言いました。
たしかに変な声だなと思いました。鼻から抜けた張り上げ気味の声で、発音もかなり訛っている(どこの訛りだかは分からなかったですけど)。歌もそれほどうまいとは思えない。歌い方が雑というか、その辺の兄ちゃんがその場にあったギターを取り上げて勝手に歌い出した、という感じの歌い方でした。
でも、ぼくにはそのとき、歌の歌詞がものすごい勢いで胸に突き刺さってきました。
ちょっと想像してみてください。ぼくたちがそれまで毎日、耳にタコができるほど聴かされていたのは「愛して、愛して、行かないで」とか「抱いて、抱いて、抱きしめて」とか「君の手が握りたいんだ!」といった、単純極まりない歌詞のポップソングばかりでした。そこへ急に、
「どれだけの道を歩かなければならないのか、
男と呼ばれるまでに。
どれほどの海を渡らなければならないのか、
鳩が砂に身を横たえられるまでに。
どれほどの砲弾が飛ばなければならないのか、
爆弾が永遠に禁止されるまでに。
答えはね、友よ、風に舞っているんだ。
答えは風に舞っている」
という詩的な歌詞がスピーカーから飛び出してきたのです。仲間がどう思ったかはわかりませんが、ぼくは少なからず、この歌詞にちょっとしたショックを受けました。このちょうど1年ほど前、ぼくは初めて小説というものを読み、読書にすぐにハマり、文章というものにどんどん興味を惹かれていた時だったので、この要因も大きかったのかもしれません。
でも、いくら彼のこの歌の歌詞に胸を打たれたとは言え、それからすぐ、ボブ・ディランに夢中になったわけではありません。
『追憶のハイウェイ61』の歌詞に完全にぶちのめされた
時は60年代の初め。当時はブリティッシュ・ロックの風が吹き荒れ、ぼくたちはビートルズやローリング・ストーンズはもちろんのこと、ジ・アニマルズやザ・キンクス、ヤードバーズ、マンフレッド・マン、デイブ・クラーク・ファイブ、ジェリー・アンド・ザ・ペースメーカーズたちに夢中になり、アメリカの白人の歌手にはあまり目が行かなくなっていました。ぼくもイギリスのモッズやロッカーズに憧れ、ミリタリー・パーカや革ジャンを着て街を闊歩し、彼らの奏でるR&Bやブルーズに聞き入っていました。
それでもこの時代、ボブ・ディランはコツコツとヒットソングを生み続け、彼の詩的な歌詞はその都度、ぼくの想像力を掻き立てました。「時代は変わる」然り、「ミスター・タンバリン・マン」然り、「ライク・ア・ローリング・ストーン」然りです。ぼくの仲間たちもこのころになるとディランに注目するようになり、よく元町にあった友人の鈴木の家にみんなで集まり、彼の音楽を聴きながら、歌詞についてあーだこーだ語り合ったものです。
高校2年の初め、ぼくはガールフレンドを追いかけて調布のアメリカン・スクールに転校しました。残念ながら、彼女には転校したその日に振られてしまい、ぼくはそれから数ヶ月、失恋の悲しみに伏していました。学校ではなるべく静かに過ごし、週末には外に遊びに行くのを止め、家でぼんやりと本を読んだり、音楽を聴いたりしていました。ぼくがより近くディランに接近して行ったのはこの時です。
音楽的にはブリティッシュ・インヴェイジョンも収まり、アメリカでサイケデリック・ロックと反戦フォークが流行りだしていたころです。ある週末、ボブ・ディランの新しいアルバム『追憶のハイウェイ61』を買って家で聴いたんですけど、あのときのことは今でも忘れません。「ライク・ア・ローリング・ストーン」を筆頭に、「追憶のハイウェイ61」、「廃虚の街」、「やせっぽちのバラッド」、「トゥムストーン・ブルース」と、全ての曲の歌詞がめちゃくちゃポエティックでシュールでパワフルで、ぼくは完全にぶちのめされました。そして、自分もいつか文章を書いてみたい、彼のような詩を書いてみたいという思いが初めて脳裏をよぎりました。
高校最後の年、失恋から完全に立ち直ったぼくは悪ガキ仲間たちと週末になると六本木に繰り出し、朝まで酒を飲んだりしていましたが、家に帰るとドストエフスキーやランボーやサルトルなどを読む、文学悪ガキ青年でした。ディランの詩をそっくり模倣したような自由詩もそのころ書くようになっていました。今読んでみると、目も当てられないような愚作ばかりですが、当時のぼくはそれらの出来にかなり満足していたように思います。
その内、ぼくは格好までディランの真似をするようになりました。誰にも迎合することなく、己の孤高な道を突き進んでいく彼の姿がぼくの理想像となり、格好からでもいいから彼に近づきたいと思ったのです。髪を梳かすのをやめ、コーデュロイのジャケットの襟を立て、猫背で歩き、勤めて眉間にしわを寄せる努力をしました。
アレン・ギンズバーグを崇拝する詩人でインテリのガールフレンドもできました。黒のタートルネックと黒のスラックスをユニフォームのようにいつも着ていた、ロビンという目の大きな女の子です。そう言えば、彼女も少し猫背でした。ぼくたちは学校を早退しては原宿のカフェ「レオン」でチェーンスモークしながらエスプレッソを啜り、ディランやビート文学について何時間も語り合いました。将来はディランのように吟遊詩人となり、詩や小説を書きながら世界を渡り歩くんだ、とぼくは彼女に豪語しました。実存主義者を名乗っていたロシア系の友人も出来、ぼくたちは学校でもいつも3人で集い、哲学や詩について熱く論議しました。今思うと、かなり充実した日々でした。
高校を卒業する頃にはロビンとは別れていましたが、卒業アルバムにはぼくの詩が何編か掲載されました。友人達からは「我らがASIJのディランへ」とか「将来の吟遊詩人へ」といった寄せ書きが綴られていました。
アメリカのカリフォルニアの大学に入学し、寮に入った時のことは今でも忘れません。廊下を歩いていると、どこからともなくディランが『ナッシュヴィル・スカイライン』でジョニー・キャッシュとデュエットした「北国の少女」が流れてきて、ぼくを迎え入れてくれました。「よう、おれの国へようこそ」と彼が言ってくれているような気がしました。そんな彼に後押しされるように、ぼくはここでヒッピーになり、ベトナム反戦運動に加わり、最初の妻となるゲイルという女性と激しい恋に落ち、詩を書き続け、世界を旅する夢に燃えました。
大学を卒業するとともに、ぼくとゲイルは長い放浪の旅に出ました。二人で、ミスター・タンバリン・マンの魔法の船に乗船したのです。旅の途上、ぼくは精神的に落ち込み、あらゆるヒーローを捨て、ディランとも距離を置くようになったのですが、これはまた別の物語なので、ここでは割愛します。
あれから40年以上たった今、ぼくは日本に帰ってラジオのDJとなり、語り部となり、本を執筆し、自作の詩もたまに書いて朗読しています。ラジオでは以前「ポエトリー・カフェ」という番組をホストし、今もポエトリー・ギャングスタというストリート・ポエットのグループのメンバーでもあります。これも全て、ディランとの出会いがあったからこそのことだと思います。
彼の詩を模倣することは何年も前に止めましたが、彼の「法の外で生きるなら、正直でなきゃだめだ」と「カオスはおれの友達さ」いう言葉は、今でもぼくの指針になっています。
彼がノーベル文学賞受賞に対してクールだということが話題になっていますが、彼のこんな言葉を思い起こせば、みんなも納得いく筈です:
「おれは王様達と食事をした。天使の羽をオファーされた。でも、どれも、どうってことはなかったぜ」
彼は永遠の異端児であり、人に賞賛されることを嫌う、孤高の旅人なのです。
ロバート・ハリスメールマガジン『運命のダイスを転がせ!』
<運命のダイスを転がせ!10月26日Vol.016<少年時代の友達と記憶力:ボブ・ディランとぼく:『セクシャル・アウトロー』:15章守護霊>
既存のルールに縛られず、職業や社会的地位にとらわれることなく、自由に考え、発想し、行動する人間として生き続けてきたロバート・ハリス。多くのデュアルライフ実践家やノマドワーカーから絶大なる支持を集めています。「人生、楽しんだ者勝ち」を信条にして生きる彼が、愛について、友情について、家族について、旅や映画や本や音楽やスポーツやギャンブルやセックスや食事やファッションやサブカルチャー、運命や宿命や信仰や哲学や生きる上でのスタンスなどについて綴ります。1964年の横浜を舞台にした描きおろし小説も連載スタート!
vol.016 目次
01 近況:少年時代の友達と記憶力
02 カフェ・エグザイルス:ボブ・ディランとぼく
03 連載小説『セクシャル・アウトロー』:15章守護霊
お申し込みはこちら!初月無料です。


その他の記事

|
私の出張装備2016-初夏-(西田宗千佳) |

|
コロナが起こす先進国と発展途上国の逆転(高城剛) |

|
『ズレずに 生き抜く』(文藝春秋)が5月15日刊行されることになりました(やまもといちろう) |

|
シンクロニシティの起こし方(鏡リュウジ) |

|
【第2話】波乱の記者会見(城繁幸) |

|
季節の変わり目に江戸幕府の長期政権を支えた箱根の関を偲ぶ(高城剛) |

|
玄米食が無理なら肉食という選択(高城剛) |

|
情報を伝えたいなら、その伝え方にこだわろう(本田雅一) |

|
やっと日本にきた「Spotify」。その特徴はなにか(西田宗千佳) |

|
昨今の“AIブーム”について考えたこと(本田雅一) |

|
冬のビル籠りで脳と食事の関係を考える(高城剛) |

|
Amazon Echoのスピーカー性能を試す(小寺信良) |

|
テレビのCASがまたおかしな事に。これで消費者の理解は得られるか?(小寺信良) |

|
ひとりぼっちの時間(ソロタイム)のススメ(名越康文) |

|
教育にITを持ち込むということ(小寺信良) |