※高城未来研究所【Future Report】Vol.740(8月22日)より

今週は、サンセバスチャンにいます。
ピレネー山脈の西端、フランス国境からほど近いこの街は、ヨーロッパの辺境でありながら、数十年にわたって世界の食と文化を牽引してきました。ラ・コンチャ湾に面したわずか十八万人の都市が、なぜここまで注目を集め続けるのか。その答えは、歴史や地理だけでなく、文化を担ってきた人々の情熱にあります。
1970年代から80年代にかけての「ヌエバ・コシーナ・バスカ(新バスク料理)」の登場は、まさにこの街の転換点でした。フランス料理の技法を学んだ若きシェフたちが、バスクの伝統料理を革新へと見事に昇華させます。その象徴がアルサックのフアン・マリ・アルサック、ペドロ・スビハナやアンドーニ・ルイス・アドゥリスといった錚々たるシェフたちで、彼らがバスク料理を世界のトップへと押し上げました。
しかし、その偉大な世代がいま、次々と引退の時期を迎えています。かつて世界を驚かせた料理人たちの厨房の灯は徐々に消えつつあり、その後を担う若い世代は確かに育ってはいるものの、彼らの背負うものはあまりに大きい。数十年にわたりバスクの「食の黄金時代」を築いた巨人たちの存在感が圧倒的であるがゆえに、その後継は容易ではありません。
こうした若手シェフたちにとっての登竜門となるのが「バスク・クリナリー・センター(BCC)」です。世界中から志願者が殺到するこの学校は、最先端のガストロノミー教育を行う場として脚光を浴びていますが、現実には入学倍率が極めて高く、地元の若者でさえ容易には門を叩けない状況にあります。教育機関が国際化し、世界から才能を集めること自体は歓迎すべき流れですが、同時に「地元の若者が憧れの舞台に立てない」という逆説を生んでいるのも現状です。サンセバスチャンの未来を担うはずの人材育成が、かえってグローバル化の渦の中で遠ざかっていく。これは決して小さくない危機の兆しに他なりません。
同根として、街全体を揺るがしているのが「オーバーツーリズム」の問題です。ミシュラン星付きレストランがもたらした国際的名声、旧市街のピンチョス文化、そして映画祭や音楽祭といった華やかなイベント。これらがすべて合わさり、わずかな人口規模の街に年間数百万人が訪れるようになりました。こうした観光による経済効果は無視できない一方、住宅価格は高騰し、地元の人々が旧市街から押し出されていく現象が進んでいます。
象徴的なのは、旧市街のバルです。
かつては地元の家族経営が中心で、オーナーが常連客と挨拶を交わすような光景がありました。しかし近年、バルの多くが知らないうちに外国人投資家の手に渡り、オーナーが地元から消えていきつつあります。外観やメニューは「伝統的バスク」を装っているものの、実際には資本の流れが変わってしまっている。観光客にとっては大きな違いはわからないかもしれませんが、地元にとっては「自分たちの文化が他者によって換金される」ことを意味します。文化が商品化され、所有の主体が失われていくとき、街の魂はどこに宿るのか、と地元の人たちは嘆きます。
これからのサンセバスチャンを考えると、イビサ同様大きく2つに分かれるだろうと予測します。
ひとつは、バスク人自身のアイデンティティがますます強調される方向です。外資の流入と観光の圧力に抗うように、バスク語教育や伝統的な共同体活動が再評価される可能性があります。
もうひとつは、逆に「バスク」というブランドが完全に観光資源としてパッケージ化され、地元の実態とは乖離していく未来です。伝統舞踊も食文化も、観光ショーとして演出されるだけになれば、サンセバスチャンは「バスクらしさのテーマパーク」に堕してしまうかもしれません。
重要なのは、この二つの流れが必ずしも対立するものではない、という点です。むしろ両者は共存しながら進行していくのがもっとも現実的な未来予測です。
すなわち、観光によって肥大化した「外向けのバスク」と、細々と維持される「内向けのバスク」が並存する未来です。問題は、その二つのバランスがどのように変化していくのか。バルのオーナーシップが外国資本に移るスピードが速ければ速いほど、地元の人々の反発は強まり、その反発が再び政治的運動に火をつける可能性も否定できません。
かつてETAが武装闘争によって訴えた「独立の夢」は、いまや過去のものとなりました。
しかし、新しい形の「文化的独立運動」が生まれる可能性は大いにあります。それは銃ではなく、食や音楽や言語を通じた抵抗です。サンセバスチャンは今後、ヨーロッパにおける「文化自治の実験都市」として機能するかもしれません。
他方、もし世界的観光需要がますます高まり、デジタルノマドやリモートワーカーが大量に流入するなら、この街はバルセロナやリスボンのように「ライフスタイル都市」として再定義されるでしょう。その場合、地元の若者が高騰した家賃のために郊外へ追いやられ、旧市街は観光客と外国人経営者の空間になる。
サンセバスチャンは今、選択の岐路に立っています。偉大なシェフたちの時代が幕を閉じ、次世代がまだ本格的に花開かない中で、街は観光と資本の圧力に揺れています。世界中の都市が同じように直面している課題を、サンセバスチャンは小さなスケールで先鋭的に経験しているのです。
この街がこれからも世界を魅了し続けるためには、単なる「観光地」以上の何かを示し続けなければなりません。文化の本質は所有者が誰であるかではなく、それを日常として生きている人々がいるかどうかにかかっています。
現在、街の様子は、バスクならではのおいしいデザートの甘さより、資本家からの甘いささやきが優位に思われる今週です。
高城未来研究所「Future Report」
Vol.740 8月22日発行
■目次
1. 近況
2. 世界の俯瞰図
3. デュアルライフ、ハイパーノマドのススメ
4. 「病」との対話
5. 大ビジュアルコミュニケーション時代を生き抜く方法
6. Q&Aコーナー
7. 連載のお知らせ
 高城未来研究所は、近未来を読み解く総合研究所です。実際に海外を飛び回って現場を見てまわる僕を中心に、世界情勢や経済だけではなく、移住や海外就職のプロフェッショナルなど、多岐にわたる多くの研究員が、企業と個人を顧客に未来を個別にコンサルティングをしていきます。毎週お届けする「FutureReport」は、この研究所の定期レポートで、今後世界はどのように変わっていくのか、そして、何に気をつけ、何をしなくてはいけないのか、をマスでは発言できない私見と俯瞰的視座をあわせてお届けします。
高城未来研究所は、近未来を読み解く総合研究所です。実際に海外を飛び回って現場を見てまわる僕を中心に、世界情勢や経済だけではなく、移住や海外就職のプロフェッショナルなど、多岐にわたる多くの研究員が、企業と個人を顧客に未来を個別にコンサルティングをしていきます。毎週お届けする「FutureReport」は、この研究所の定期レポートで、今後世界はどのように変わっていくのか、そして、何に気をつけ、何をしなくてはいけないのか、をマスでは発言できない私見と俯瞰的視座をあわせてお届けします。


その他の記事

|
伊達政宗が「食べられる庭」として築いた「杜の都」(高城剛) |

|
「家族とはなんだって、全部背負う事ないんじゃない?」 〜子育てに苦しんだ人は必見! 映画『沈没家族 劇場版』(切通理作) |

|
米豪だけでなく日露も導入を見送る中国通信機器大手問題(やまもといちろう) |

|
ベトナムが暗示する明日の世界絵図(高城剛) |

|
あたらしいライフスタイルのひとつとして急浮上する「スロマド」(高城剛) |

|
高橋伴明、映画と性を語る ~『赤い玉、』公開記念ロングインタビュー(切通理作) |

|
「不思議の国」キューバの新型コロナワクチン事情(高城剛) |

|
中国発・ソーシャルゲーム業界の崩壊と灼熱(やまもといちろう) |

|
幸福度を底上げするためのまちづくり(高城剛) |
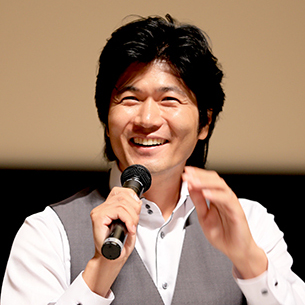
|
「本質を学ぶ場所」を作る(西條剛央) |

|
部屋を活かせば人生が変わる! 「良い部屋」で暮らすための5つの条件(岩崎夏海) |

|
【第3話】見よ、あれがユニオンズの星だ!(城繁幸) |

|
リベラルの自家撞着と立憲民主党の相克(やまもといちろう) |

|
睡眠時間を削ってまで散歩がしたくなる、位置情報ゲームIngress(イングレス)って何?(宇野常寛) |

|
一寸先は、光。自分しかない未来を恐れなければ道は開けるものです(高城剛) |



























