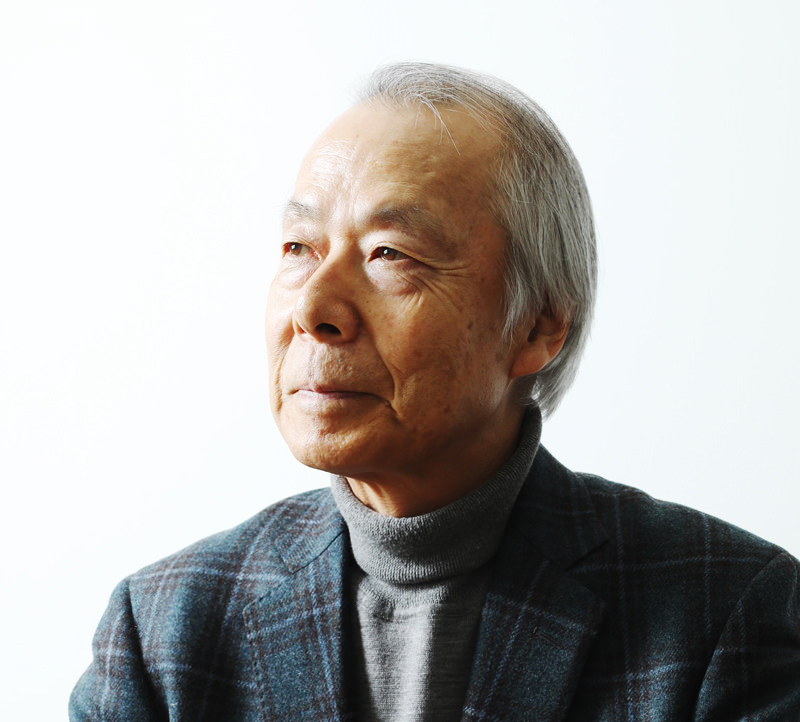「好き嫌いがわからない」のはアイデンティティ障害の兆候
自分のやりたいこと、あるいはやりたくないことがわからない、というのは端的に言えば「好き嫌い」がわからない、ということです。そして「好き嫌い」がわからなくなるということに、僕は「アイデンティティ障害の兆候」を感じます。
コウモリが明るい場所を嫌い、暗い場所へと逃げ込むように、あらゆる生命は、「好き嫌い」を軸に行動し、その命をつないでいます。つまり、「好き嫌いがわからなくなる」というのは、生命としてのアイデンティティが壊れつつあるといってもいいぐらい、危機的な兆候だということです。
アイデンティティ障害に陥っている人間は「やってもいいこと」だけをやり、「やらなくてもいいこと」や「推奨されないこと」には手を出しません。社会もひとつの「生命」です。もし、社会そのものがある種のアイデンティティ障害に陥っているとすれば、その結果として、個々の組織や人々からも創造性が失われることになります。
「言われたことはやるけれど、自分から新しいことに取り組むことを嫌う」新入社員が毎年のように現れるのは、社会全体がアイデンティティ障害に陥っていることの「結果」に過ぎないのかもしれません。
子育てや教育はもちろんのこと、それこそ社会人となった後の新入社員教育の場面においてすら、僕らは「言われたことを素直にやる」ということを手放しに評価しがちです。でも、「これをやりなさい」と言われたことをそのまま素直にやる、ということは「病み」の兆候といっても過言ではないと僕は捉えています。
なぜなら、「言われたことを素直にやる」というのは、別にそれを「やりたい」からではないからです。他人から言われた事を素直にやるのは、「やりたくないこと」が明確でないことの結果に過ぎません。人間というのは、元気であればあるほど人から言われたことに反発するし、病気になって元気をなくすと、人から言われたことに素直に従う。そういう生き物です。