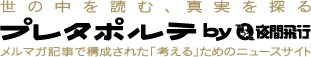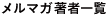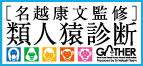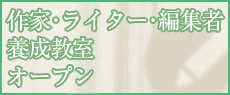言語によって認識が歪められている!?
ピダハンの人々の言語の特徴とは少しずれますが、色彩感覚や、共感覚者が生得的に持つ共感覚に対しても、言語が影響を与える可能性があるという話もあります。共感覚者の岩崎純一さんは、彼の著作である『音に色が見える世界』において、以下のように述べられています。
「外国語をやれば世界が広がると周りの人は言う。ところが私は、人間には、そもそも言語を得た時点で、すでにその脳や体から消滅した感覚と思考があると考えていた。私は自分が、言語よりも手前の感覚世界、共感覚世界に生きているという強い自覚があるものだから、言語を獲得するということは、すなわち共感覚をどれだけ失うかということに等しかった」(『音に色が見える世界』)
生まれ持った共感覚の能力が、言語の獲得と共に「失われていく」ということです。
他にも、言語を習得することによって失われたり、変更を加えられたりする感覚や能力があるのかもしれません。言語はある面、きわめて便利なものです。言語によって人間は大量の情報を交換することが可能になりました。さらに思考する能力が進化し、学問や文学などが生み出されるようになりました。しかし同時に、言語の獲得により、我々が本来持っていた能力、ある意味非常に「原始的」な感覚や能力が失われてしまうということもあるようです。
これは、ある意味言語による「縛り」が与えられるということだと思います。以前引用させていただいた南直哉さんの「無明とは言語のことではないか」という発言とも関係するのではないでしょうか。本来認識されていたものが言語の獲得によって認識されなくなってしまうこともあるということです。実は我々が想像する以上に、言語によって我々の認識が「歪められて」しまうことがあるのかもしれません。
いずれにせよ、人間が本来持つ能力や、原感覚といったものと言語の獲得との関連について考察する際にも、ピダハンの人々のケースは非常に興味深いものであるといえると思います。そしてこれらの事実からも、ピダハンの人々が我々「大人」以前の感覚、人間の赤ちゃんや他の動物と同じような感覚を保持したまま、まさに「今ここ」を生きているということが言えるのかもしれません。そうしたピダハンの人々が、「今ここ」に存在しないもの、直接経験することができないものである「創造神」や「創世神話」などを受け入れないということは、ある意味では必然といえるのではないでしょうか。
「信じる」と「感じる」の違い
しかし同時に、この直接体験の原則のなかで生き、形而上学的な「神」のような存在を受け入れないピダハンの人々が「精霊」の存在を受け入れているということは興味深い事実だと思います。しかし、これはいわゆる「信仰」、少なくともキリスト者などがいう「信仰」とは別のものだと思います。
前回の甲野先生のお手紙のなかでも言及されていることですが、ピダハンの人々は、いわゆる精霊を存在するものとして、ごく当たり前の存在として受け入れています。ピダハンの人々は精霊の存在を、それこそ目の前に木があるかのごとく、「ただある」ものとして受け入れているようです。これは、「自分たちが実在すると感じるものを、ただあると認識している」ということだと思います。ここには「信じる」という心の働きは存在しないのではないでしょうか。
ピダハンの精霊の話とは文脈が異なるのですが、宗教を「信じる」と「感じる」という観点から論じた箇所が、『救いとは何か』という本のなかにあります。そこにおいて山折哲雄氏が「信ずる宗教」と「感ずる宗教」の違いについて、以下のように述べられています。
「何より重要だったのは、イスラエルのような砂漠の地に暮らす一神教の民にあっては、彼らが信ずる「天井の彼方にあるもの」を信じるか否か、ということです。だからこれは「感じる、感じない」という関係ではないと思う。「信ずる宗教」はそこで成立する。キリスト教の根本的な心構えとはそういうものではないかと思う。
これに対して日本列島は気候も温暖で、山の幸、海の幸に恵まれている。そうした豊かな自然によって自分たちの暮らしが支えられているということを骨の髄から知ってもいる。そこから、多神教的な神観念や多元論的な価値観が生まれてくる。「天上の彼方」に価値あるものを求める必要がないため、人間社会と自然の関係が、非常に近しいものになるのですね」
それに対して、対談者の森岡正博氏は以下のような異論を述べられています。
「私にとって、手を合わせたくなるような何かを「感じる」ことはあっても、決してそれは宗教にはなり得ないのですね。あえて言うなら、「感ずる非宗教」になる。山折さんは、実感として分かることと信仰とは紙一重じゃないかとおっしゃいますが、その紙一重はずいぶんと厚い一重なんですよ。大自然の中に何かをありありと感じること、そして遺品を前に手をじっと合わせること、これは私にとってすごくリアルなことなんです。でも、そこから宗教までは無限の距離がある。だからその距離を自覚して、こちら側にとどまろうとする私の立場は「感ずる非宗教」なのです」
森岡氏の言う「感じる非宗教」、すなわち「何かを感じる」ということと、「宗教」とのあいだには無限の距離がある、ということは、「信仰」と「ただあるものとして受け入れる」ということの違いを考えるうえで、そしてピダハンの人々の精霊に対する態度について考える際にも重要な意味を持つのではないかと私は思います。
ピダハンの人々の精霊に対する態度は「信仰」ではない。なぜなら、そこに「信じる」という心の働きが介在していないからです。それは、ただ厳然として、彼らにとっては「ある」ということだけではないでしょうか。それは我々「現代人」から見たら、「物理的には存在しないものを『存在している』と受け止めている」という点で宗教や信仰のように見えますが、彼らにとっては「ただ存在するもの」という感覚があるだけなのではないかと思うのです。
もちろん、これはいわゆる「妄信」とも違うと思います。どこが違うのか、今の私の考えの範囲で申し上げますと、原理主義的な妄信の背後には、それが「実は嘘ではないか」という恐れのようなものが、たえずこびりついて離れていないように思うのです。
信仰には「距離」が必要である
周囲の人間から見て、どう考えても「行き過ぎ」と思われる信仰を持った人間が、自らの信仰を否定されると烈火のごとく怒り狂うという話を、私は何度か耳にしました。彼らがある対象に対してどれほど強い信心を持っていたとしても、それは「ただそこに存在する」という感覚とは別のものでしょう。一方、ピダハンの人々が精霊の存在を受け入れない人間に対して激昂するということはあり得ないと思います。当たり前のものとして「ただある」ものだからです。
そして、前回お送りした文章のなかで触れさせていただいたことと絡めていえば、「信じること」と「あること」の違いは「跳んだ」記憶があるかないか、その「距離感」の感覚があるかないかではないでしょうか。
キリスト者などの、いわゆる信仰者の「深い信仰」とピダハンの精霊に対する「ただある」という感覚は、この点において異なるように思うのです。距離感の感覚が、かつてあったという感覚も含めてですが、あるかないかという点が異なるのではないでしょうか。
つまり、「信じる」という行為には、ある種の距離感、「断絶」が前提となっていると思うのです。
「ただ存在する」と受け入れることができないものを、それでも受け入れていく行為だということです。そして、「信じる」という行為の価値は、その埋まらない断絶を受け入れたうえで、それでもそこで踏み止まり続けるというところにあるのかもしれません。信仰を持たない私がこのようなことを言うことはおこがましいことなのかもしれませんが、ピダハンの人々について考えるうちに、私はそのように考えるようになりました。
この「信じる」ということに関しても、非常に印象深い箇所が『ピダハン』のなかにあります。先日頂いたお手紙のなかで、甲野先生は「本当に深い信仰を持っている人は逆に感銘を受けるのではないかと思います。それは『ピダハン』の人々の精霊に対する思いと、自らが信じる宗教の神や仏に対する感覚に共通したものを感じ取るからだと思います。深い信仰に目覚めた人にとっての神や仏は、きわめて実感があり、現に存在している親戚の人々や知人のように感じられているようですから」と書かれていますが、『ピダハン』のなかにもそのような信仰を持った人物が登場しています。
セウ・アルフレド(ミスター・アルフレド)というキリスト者の老人です。20年以上信仰に生きたセウ・アルフレドの人生の終幕の場面が、この本のなかに描かれています。彼が病気に侵されたと聞いて見舞いに訪れた『ピダハン』の著者エヴェレット氏に対して、セウ・アルフレドは以下のように言い、医者を呼ぶことを拒みます。
「自分が死ぬときはわかるものです。ですが、悲しむことはありませんよ。死をもってこの苦しみを終わらせることができて、わたしはうれしいのです。それに、死ぬことは怖くはありません。イエスの元へ行けるのですから。長い間、ほんとうによい人生を生きることができて感謝しているのです。子どもや孫にも恵まれました。みんなわたしを愛してくれています。みんなわたしのそばにいてくれます。自分の人生と家族に、ほんとうに感謝しているのです」
彼には、イエスという存在が深く深く、内面化されているのだと思います。ここまで内面化されてしまえば、もはや「信じるか信じないか」というよりも、厳然として「ある」といえるほど、その存在がリアルなものとして感じられているのではないでしょうか。そうでなければ、いまわの際で、このような態度を取ることはできないと思います。その信仰者としての姿に、著者のエヴェレット氏もかなりの感銘を受けたのでしょう。エヴェレット氏は最終的にキリスト教を棄てますが、棄教した後に書かれたこの本のなかでこの老人について触れたということは、よほど彼の最後の場面に心を打たれたということではないでしょうか。
ただし、それでもこれはピダハンの人々が精霊に対して持つ「ある」という感覚とは異なるようにも思うのです。それは、信仰対象への「距離」自体の感覚は残っているということかもしれません。「跳んだ」という感覚自体は覚えているということでしょうか。ピダハンの人々は、精霊の存在に対して「跳んだ」という感覚は持ってはいないと思います。それは最初から、「ただある」ものだからです。


その他の記事

|
『「赤毛のアン」で英語づけ』(1) つらい現実を超える〝想像〟の力(茂木健一郎) |

|
「疲れているとついイラッとしたり、怒りっぽくなってしまうのですが……」(石田衣良) |

|
先行投資か無謀な挑戦か ネット動画事業に関する是非と簡単な考察(やまもといちろう) |

|
同じ場所にいつまでも止まってはいけない(高城剛) |

|
日本人の情報感度の低さはどこからくるのか(やまもといちろう) |

|
「日本版DBS」今国会での成立見送りと関連議論の踏み外し感の怖さ(やまもといちろう) |

|
インタラクションデザイン時代の到来ーー Appleの新製品にみる「オレンジよりオレンジ味」の革命(西田宗千佳) |

|
「政治メディア」はコンテンツかプラットフォームか(津田大介) |

|
思い込みと感情で政治は動く(やまもといちろう) |

|
本気でスゴイ!手書きアプリ2つをご紹介(西田宗千佳) |

|
「本当かどうかわからない数字」に左右され責任を押し付けあう日本社会(高城剛) |

|
「ローリング・リリース」の苦悩(西田宗千佳) |

|
成功を導くのは、誰からも評価されない「助走期間」だ–天才を育む「ひとりぼっちの時間」(ソロタイム)(名越康文) |

|
継続力を高める方法—飽き性のあなたが何かを長く続けるためにできること(名越康文) |

|
「スターウォーズ」を占星術でひもとく(鏡リュウジ) |