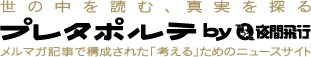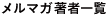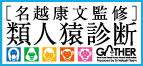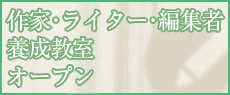古今東西のジャズの名盤の中から、筆者が独断と偏見で選んでご紹介する「馬鹿ジャズ名盤講座」、第3回目である。ちなみに、第1回「彼女を部屋に連れ込んでどうにかしたい時に聴きたいジャズアルバム」はこちら。第2回「パチンコで5万円負けてしまった後に聴きたいジャズアルバム」はこちら。
殺人事件の容疑者になってしまった時に
聴きたいジャズアルバム
藪から棒に尋ねてみるが、殺人事件の容疑者になった事はあるだろうか。
私は、ある。
もちろん完全無欠に無罪であるので疑われただけなのだが、殺人事件の容疑者になるという体験はなかなかに貴重である。私の知り合いを見渡しても同様の経験のある人間は一人としていないので、やはりこれは十分に「貴重な経験であった」というに値するだろう。
私が犯人の疑いをかけられたのは、2007年の1月15日に京都市の岩倉で起きた殺人事件である。現場近くにある精華大学のまんが学部の学生が通り魔的な男に刺殺されたという事件は激しく世間を騒がせたし、私もそのような痛ましい事件が起きた事は知っていた。
それから半年以上経った2007年の8月に私の元へ京都の下鴨警察より電話がかかってきて、「1月15日の殺人事件の容疑者としてあなたがピックアップされている。こちらの警察側としてはあなたが無罪であれば良いと思っているし、それを証明する為に幾つかの質問にきちんと答えてほしい」と言われた。
私は眩暈がしたのを覚えている。
警察は私に対して親切で気安い感じで話しかけてきてはいるが、私を疑っている事は明白であった。むしろその親切さや気安さが私を苛立たせた。「何もしていないのに何故疑われなくてはならないのだ、これはまかり間違うと逮捕まであり得るのか!?何もしていないのに!」そんな風に憤りを感じた、というのも事実。だが、それ以上に「こんなことってあるのか」という非現実感の方が強かった。
即座に私の脳裏に、ドイツの小説家フランツ・カフカの『審判』という小説が浮かんだ。
理由もわからずに逮捕され裁判を起こされたヨーゼフ・K(カー)という男がそのまま裁判にも負けて処刑されるという、理不尽で不条理極まりない小説である。
私もKのようになるのだろうか。
そんなことに怯えながら警察の質問に一つ一つ正直に答えた。質問されながら、警察の「私に関する知識」のあまりの豊富さに驚いた。警察、お前らオレの事を調べすぎだ。さてはオレのファンだな。そう思った。
警察:「2001年に、結構長いこと出国してますね。これはどこに行ってたんですか?」
フクシマ:「あ、インドに……あと、その周辺の国々にも行ってました」
警察:「そうですね、パキスタンにも入国したデータがありますね。これは何しに行ってたんですか?」
フクシマ:(こいつら知ってて聞いてんのか、オレらは何でもお見通しだからつまんねえ嘘をつくなよっていう牽制なんだろうな、良いよ正直に喋ってやるよ)
「パキスタンは……えーと……アニメの『風の谷のナウシカ』の舞台になったって言われる村が山奥にあるって聞いて、それで行ってみたくて……」
警察:「へー、ナウシカの舞台はパキスタンなんですねー」
フクシマ:「という説があります」
などというやり取りをしばらく続けた。
本当に警察は私の事をよく知っていて、「ずっと柔道やってたんですね。あ、○○年の△△の大会では優勝してるし、翌年は3位なんですね、残念ですね」と、私が忘れているような事まで知っていた。先にも書いたが、「全てお見通しなんだから嘘をつくなよ」という牽制である事は明らかだった。そういった会話で追い詰められた後に、核心をつくような会話に入った。
「それで、1月15日の夕方以降は、何をしていましたか?」と。
実は私はそこまでの会話に正直に答えながらも、「1月15日って何かあったなー、何してたっけなー」と記憶を辿っていたのだが、その日には私には極めて明確なアリバイがある事を途中で思い出していた。
実は1月15日というのは、大学の卒業論文の提出日だったのだ。私もその日に論文を提出して、無事に大学を卒業した。無事に、とは書いたが私は少々オツムが弱かったので大学を卒業するのに実に9年間もかかってしまい、世話になった先生方にも「良かったな、やっと卒業出来たな! 卒業したらどうするんだ、そうか、ミュージシャンになるのか! そうかそうか! 勝手にしろ! わははははは!」という心温まるやり取りなどもあり、私がその日のその時刻に大学にいたことは多くの人が証明できる。
私は電話をかけてきた警察官に、その日は大学の卒業論文の提出日であり、大学に論文を提出しに行っていた、そのあとも大学にいた、事件のあった時刻に私が大学内にいた事は多くの人が証明出来るし、そして何よりも大事な事だが私は犯人ではない、という事を伝えた。
それは相手の警察官を納得させるだけの説得力を持っていたようで、私の容疑はそこで晴れた。
今回この原稿を書くにあたり、あの事件は結局どうなったのだろうとインターネットで調べた所、現時点で未解決という事だった。
犯人の特徴をこちらにコピペしておく。
ーーーーーー
年齢:20~30歳位
身長:170~180センチ
髪:センター分け(ボサボサ)
服:上下黒っぽい服装
その他:黒っぽい色の「ママチャリ」風の自転車(軽快車)に乗っていた。
態度:興奮していて顔や上半身を左右に振り、言葉尻に「アホ、ボケ」を連発し、目の焦点が合っていない。
靴の大きさ:28~29センチ(遺留品ではないが、畑に残された足跡で判明)
ーーーーーーー
なかなかにコントのような犯人である。このような不審な人物が未だに捕まっていないのが不思議で仕方がない。特に「態度」の項目のくだり。私がこのような人物に間違えられたとは甚だ遺憾である。
遺族の無念の為にも事件の解決を強く願う。
さて、カフカの「審判」の例を先に出したが、この世の中には道理に合わないことは多数存在する。私の個人的な意見としては、我々人間が跋扈するこの浮き世自体が畢竟不条理そのものだとすら思っている。
不条理こそがこの世の本質であると仮定するならば、私は不条理に対して強い興味を持ちながら日々を生きている。
そうなのだ、私はこれまでずっと不条理に強く心を惹かれながら生きてきた。
不条理系武闘派・エリック・ドルフィー
アルトサックス、バスクラリネット、フルートなどの楽器奏者として知られたエリック・ドルフィーのアルバム群を聴くと、頭の片隅に「不条理」という言葉が浮かぶ。
不可思議なコード進行に乗せられた人を食ったようなフレーズの数々。私は初めてドルフィーのレコードを聴いた時には「何じゃこりゃ?」と、頭にクエスチョンマークが幾つも浮かんだのを覚えている。
一聴して、それは既存の音楽理論から外れたようなデタラメにも聴こえる。ドルフィーの事をフリージャズの演奏家だと思っている人も少なくないようだが、それにも頷ける。しかし、ドルフィーの音楽に対して「何だかヘンテコだけれど面白いな」と思いながら聴き続ける内に、そこにはある種の整合性が存在するように思えてくるのが不思議だ。
エリック・ドルフィーという音楽家の中にある独自のコード理論、スケール理論からすれば、そこにある音楽は極めて自然なものであり、それはつまり「彼の物の言い方」という事なのだなと合点がいく。
たまにドルフィーのレコードを聴くと、初めてドルフィーを聴いた時の「何じゃこりゃ感」が今でも少し残っていて、「いやー相変わらずドルフィーだねえ。ヘンテコだねえ。でもそれがたまらなく良いねえ」という感想を抱く。
また、エリック・ドルフィーという音楽家に対する私の個人的なイメージなのだが、「特攻隊長ないし若頭」というイメージがある。
ドルフィーの音楽性を強く買って自らのバンドに起用したチャールズ・ミンガスという偉大なベーシストがいるのだが、この男、ヤクザで言うところの「組長」といった風情。ミンガスのバンドを「ミンガス組」という一つのヤクザだとするなら、ドルフィーは「イケイケの武闘派の若頭」といった雰囲気なのである。
<ミンガス親分。一緒にバンドをやったら30秒で小便をちびり、45秒で殴られそうなほどコワイ>
ステージの後方にでんと構えたミンガス親分がいて、「おう、エリック、好きに吹きぃや」とベースをぶいんぶいん鳴らすとそれに呼応したドルフィーが「オヤジぃ、ワシに任せてつかあさいや」と、ばりばりぶりぶりがちょーん! とサックスを吹きまくる。後方に控えるピアノのジャッキー・バイアードなどはさながら冷徹なヒットマンのようで、シャキーン! カツーン! と的確に敵を殺してゆく。何だかそんな光景が頭に浮かぶ。
ミンガス率いるバンドは、とてもガラが悪い。北野武監督の『アウトレイジ』に出てきそうな感じの「ミンガス組」という感じなのだ。音楽は凄まじいのだけれど。
『Last Date』/Eric Dolphy
<うまいのかヘタなのかよくわからないようなジャケットの絵も素敵>
さて、エリック・ドルフィーのアルバムを一枚紹介したいのであるが、数あるお気に入りの中から一枚となると悩むのだが、ここでは1964年の作品、『Last Date』を推したい。演奏内容としては他にもっと良いもの(或いはもっとドルフィーらしいもの)もあるのだが、私はこのアルバムが好きなのだ。
「Hypochristmutreefuzz」という謎のタイトルの曲では相変わらずのドルフィー節が堪能できる。一聴してデタラメに聴こえるような音の羅列が、実は確固たる整合性のもとに在るという、先に述べたドルフィーの特徴である。これが聴いている内にクセになるのだ。カラスミやクサヤなどのアクの強いツマミのようで、最初はむむっとなるかも知れないが、聴き続ける内にクセになる。ドルフィーならではだ。
アルバムの中で私が特に好きなのは、ドルフィーがフルートで演奏する「You Don't Know What Love Is」だ。元々はとても綺麗なバラードであるのだが、ドルフィーの演奏のおかげでそれは決して甘ったるくはならない。あくまでも奇妙なドルフィー・ワールドである。
様々なジャズスタンダード曲に関して、「この曲と言えばこの人のこの演奏が最も腑に落ちる」というのがそれぞれあるのだが、私は「You Don't Know What Love Is」と言えばこのドルフィーの演奏である。
『Last Date』には、最後にオマケのような楽しみが隠されている。
最後の曲、「Miss Ann」の演奏が終わった直後に、ドルフィー自身が喋り出すのだ。
When you hear music,after it's over,it's gone in the air.
You can never capture it again.
(あんたが音楽を聴き終わった後、そいつは空中に霧散しちまう。
あんたはそいつを二度とつかまえる事はできない。)
と。
最後までブレないドルフィーの哲学的な姿勢である。
余談であるが、ドルフィーはこのアルバムをレコーディングした直後に36歳の若さで急逝している。筆者の現在の年齢と一緒だ。
そんなことを知っているからなのかどうかはわからないが、最後のこのドルフィーの言葉は、まるで彼岸から放たれた言葉のように私には聴こえるのだ。
末筆になるが、私が疑いをかけられた殺人事件の被害者の冥福を祈ると共に、一日も早く犯人が捕まる事を願う。
『Last Date』/Eric Dolphy
リリース:1964年
録音:1964年6月2日(ニューヨーク)
レーベル:ライムライト・レコーズ
1.Epistrophy
2.South Street Exit
3.The Madrig Speaks, the Panther Walks
4.Hypochristmutreefuzz
5.You Don't Know What Love Is
6.Miss Ann
(執筆者プロフィール)
福島剛/ジャズピアニスト
1979年東京都出身。青春時代のすべてを柔道に捧げた後、京都府立大学在学中の20歳の頃よりピアノを始める。故・市川修氏に師事。2006年より「ボク、ピアノ弾けます」という嘘とハッタリによりプロの音楽家となる。プロとしての初めての仕事は故・ジョニー大倉氏のバンド。07年、活動の拠点を地元、東京江戸川区に移す。各地でのライブ、レコーディング、レッスン、プロ野球(広島カープ)観戦、魚釣り、飲酒などで多忙な日々を送る。
主なアルバム作品に映画作品のサウンドトラック『まだあくるよに』(2012年 ※iTunesの配信のみ)、お笑いジャズピアノトリオ「タケシーズ」による『みんなのジャズ』(2013)、初のソロピアノアルバム『Self Expression』(2015)がある。座右の銘は「ダイジョーブ」。

その他の記事

|
ドイツでAfDが台頭することの意味(高城剛) |

|
東京15区裏問題、つばさの党選挙妨害事件をどう判断するか(やまもといちろう) |

|
暗い気分で下す決断は百パーセント間違っている(名越康文) |

|
統計学は万能ではない–ユングが抱えた<臨床医>としての葛藤(鏡リュウジ) |

|
季節の変わり目の体調管理(高城剛) |

|
ウェブ放送&生放送「脱ニコニコ動画」元年(やまもといちろう) |

|
公共放送ワーキンググループがNHKの在り方を巡りしょうもない議論をしている件(やまもといちろう) |

|
『魔剤』と言われるカフェイン入り飲料、中高生に爆発的普及で問われる健康への影響(やまもといちろう) |

|
ビル・ゲイツと“フィランソロピー”(本田雅一) |

|
「常識」の呪縛から解き放たれるために(甲野善紀) |

|
【告知】1月28日JILISコロキウム『文化資産と生成AI、クレカによる経済検閲問題』のお誘い(やまもといちろう) |

|
「脳内の呪い」を断ち切るには(西條剛央) |

|
ファッショントレンドの雄「コレット」が終わる理由(高城剛) |

|
「いま評価されないから」といって、自分の価値に疑問を抱かないためには(やまもといちろう) |

|
「群れない」生き方と「街の本屋」の行方(名越康文) |