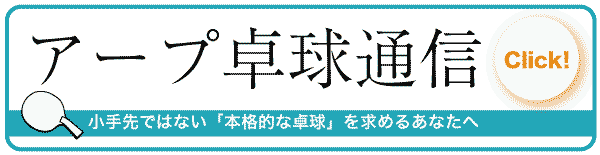なぜゲームという「電車」を途中下車してしまうのか
ゲームを電車に喩えるなら、「電車を降りる」のは本来、終着駅、すなわちゲームセットの瞬間しかないはず。しかし、多くの人は、電車を途中で降りてしまいます。いわば、ゲームを「途中下車」してしまうのです。
ゲームに勝てない、ゲームが苦手だ、という人の話を聞くと、ゲーム中に「負けてしまうかも」「ミスしたらどうしよう」と不安になってしまうとおっしゃるんですね。私からすると「よくそんな暇がありますね」と思うんですが(笑)、実際、そうなってしまう。それは結局、ゲームという電車を「途中下車」してしまっているからではないでしょうか。
もしもゲームを「動き続けている電車」だと捉えていたら、そんなことを考える暇はないと思うんです。ゲームという「動き続ける電車」の中で変化し続ける「景色」を前に、あれこれ計算し、判断し続けるのはかなり忙しいことです。たった一本のラリーであっても、丁寧に見て行けば、分析し、検討しなければならない要素がたくさんあります。サービスのコースをボール何個分ずらせばどうなるか、ということまで考え始めると、とても許された時間では間に合わないぐらい、頭を高速で回転させなければなりません。
本当であれば、ゲームというのは自分と相手とがひとつの電車に乗り、互いにその瞬間ごとの「景色」を前に頭と身体を総動員し、そして「ゲームセット」の声を聞いたら、一緒に電車を降りる、というものであるはずです。ところが現実には、途中でゲームを降りてしまう人がいる。そういう人は、どうやってもゲームに勝つことはできないでしょう。
言い換えれば「ゲーム中に余計なことを考えてしまう」というのは、その時点でゲームという「電車」から降りて、日常に帰ってきてしまっている、ということですね。日常の時間の進み方というのは、電車のように一方向に進んでいるわけではないので、余計なことを考える余裕ができてしまうわけです(笑)。
「負けそうかな」「ダメかな」と不安に思っている時点で、ゲームという電車から降りてしまっている。あるいは、ゲーム中に大声をあげて相手を威圧しようとする人も同じですね。大声を出すたびに、心がゲームから離れていってしまう。ゲームの時間というのは、留まらず、ずっと進んでいくものですからね。一球ごとに声を出して、いちいちゲームから意識を途切れさせている人は、とてもじゃないけれど、トップレベルの「ゲームの時間」についていけないと思います。
そういう視点から見ていくと、「超一流」の選手はみんな、「静か」なんですよ。テニスならロジャー・フェデラー選手を見てください。ほとんどの場面で、スッと静かに落ち着いてプレーをしています。もちろん時々、勝負どころで大きな声を出していることがありますが、自分を奮い立たせようとするあまり、思わず声が出ているのだと思います。少なくとも、相手を威嚇したり、観客にアピールするために騒ぎ回っているわけではない。
「ゲームの時間」という観点から、いろんな種目のゲームを観察してみてください。きっと、発見があると思いますよ。
<第1回ここまで>
【お知らせ】山中教子特別講義「ゲームからひもとく 自分を支える力」
およそ1年振りとなる、元卓球世界王者・山中教子による特別講義を2016年1月30日、アープカレッジすがも(JR巣鴨駅徒歩2分)にて行います!
詳細・お申し込みはこちらから
【お知らせその2】卓球世界王者のレッスンを自宅で受ける「アープ卓球通信」スタート!
小手先ではない、「本格的な卓球」を求めるあなたへ。
初心者からトッププレイヤー、指導者まで。アープ理論に基づく卓球の最先端を映像とテキストでお届けします。

その他の記事

|
インタラクションデザイン時代の到来ーー Appleの新製品にみる「オレンジよりオレンジ味」の革命(西田宗千佳) |

|
今週の動画「切込入身」(甲野善紀) |

|
未来を見据えた働き方 カギは隙間時間にあり(家入一真) |

|
安倍晋三さんの総理辞任と国難級のあれこれ(やまもといちろう) |

|
JAXAで聞いた「衛星からのエッジコンピューティング」話(西田宗千佳) |

|
ナイジェリア政府による誤情報発表とJICA外交政策への影響について(やまもといちろう) |

|
【ダイジェスト動画】名越式仏教心理学を語る(名越康文) |

|
次のシーズンに向けてゆっくり動き出す時(高城剛) |

|
スマートスピーカー、ヒットの理由は「AI」じゃなく「音楽」だ(西田宗千佳) |

|
YouTube広告問題とアドフラウド(やまもといちろう) |

|
本当に大切な仕事は一人にならなければできない(やまもといちろう) |

|
VRコンテンツをサポートするAdobeの戦略(小寺信良) |

|
ヒトの進化と食事の関係(高城剛) |

|
なぜ「正義」に歯止めがかからなくなったのか 「友達依存社会」が抱える課題(平川克美×小田嶋隆) |

|
マジックキングダムが夢から目覚めるとき(高城剛) |