※宇野常寛のメールマガジンほぼ日刊惑星開発委員会vol.531〈猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉 第6回 「もう一つの“体育”で、『身体的知』 (身体を固定しない“知性”)を鍛えたい」 【毎月第1火曜配信】 〉より
今朝のメルマガは、チームラボ代表・猪子寿之さんによる連載『猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉』の第6回です。なぜ猪子さんは平面の表現にこだわるのか。そんな問題提起から始まった議論は、近代の椅子に固定された知性とは異なる、身体を動かしている情報量が多い状況での知性としての「身体知」という概念にたどり着きました。そんな「身体知」を鍛えたいという猪子寿之氏の考える新しい”体育”とは?
▼プロフィール
猪子寿之(いのこ・としゆき)
1977年、徳島市出身。2001年東京大学工学部計数工学科卒業と同時にチームラボ創業。チームラボは、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、絵師、数学者、建築家、ウェブデザイナー、グラフィックデザイナー、編集者など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリストから構成されているウルトラテクノロジスト集団。アート・サイエンス・テクノロジー・クリエイティビティの境界を曖昧にしながら活動している。47万人が訪れた「チームラボ踊る!アート展と、学ぶ!未来の遊園地」などアート展を国内外で開催。他、大河ドラマ「花燃ゆ」のオープニング映像、「ミラノ万博2015」の日本館、ロンドン「Saatchi Gallery」、パリ「Maison & Objet 20th Anniversary」など。2016年はカリフォルニア「PACE」で大規模な展覧会を予定。
[リンク]http://www.team-lab.net
◎構成:稲葉ほたて
本メルマガで連載中の『猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉』配信記事一覧(掲載号)はこちら。
vol.433 第1回 「みんなで「モノ」のなかに入ろう!」
vol.447 第2回 「(僕らのつくる)世界はこんなにもやさしく、うつくしい」
vol.462 第3回 「自然の情報量を生かしたアートを作りたい」
vol.487 第4回 「モナ・リザの前が混んでて嫌なのは、 絵画がインタラクティブ
じゃないから」
vol.509 第5回 「アートには正しさがないから、 人類を新しい方向に“導ける”」
「超主観空間」とこれからの平面
宇野 猪子さんが、よく自分たちの作品のコンセプトを説明するときに使っている「超主観空間」という言葉があるよね。超主観空間という日本的な絵画の平面性が、西洋近代的な意味での二次元のパースペクティブとは違って、コンピュータの作る多次元へのアクセスと親和性が高い、というのはよく分かるし、説得力もあると思う。
そこで聞いてみたいのは、そんな「新しい平面」の像をアートが打ち出すことの意味なんだよね。
猪子 いや、僕は普通に「超主観空間が圧倒的に優れている」とかは思ってないんだよ。ただ、今まで捨てられていて、特に映像的なジャンルだとあまり使われてなかったけど、それがデジタル時代には可能性がある……みたいなことを示したいだけなんだよ。
宇野 だからその先をちょっと聞いてみたいと思うんだよ。要するに西洋近代のパースペクティブは、実際にはピントも合っていなければ統合もされていない人間の、三次元の視覚体験を二次元に整理して共有しやすくする、という意味で「人類を前に進ませた」わけじゃない。同じように超主観空間はどう「人類を前に進ませる」のかなって思うわけ。
猪子 なるほど、宇野さんの質問の意図が分かってきた。
あのね、超主観空間の良いところは、むしろ空間的なものでの体験との相性の良さにあるんだよ。そういう平面を壁に貼ったりすると、その空間における体験が面白いものになるんだよね。
その理由をこれから順番に話していこうと思うのだけど……まずいきなり一つ凄いことを言うと(笑)、パースペクティブで把握された世界には、自分がいないんだよね。
実際、写真や映像のような実写の画面には、そのカメラの視点で眺めている自分は存在できないよね。でも、超主観空間では、自分がその中にいるものとして、その世界を捉えられる。
宇野 そもそもパースペクティブというのは、自己と世界を一度切り離して視点を獲得する発想だからね。
猪子 だから、西洋では客観的な「観察」という発想が生まれて、サイエンスが発達したんだとは思うよ。でも、その代わりに、見えている世界から自分が疎外されているような気分をもたらしてしまった。それに対して、超主観空間と僕らが呼んでいる空間認識の論理構造で近代化以前の日本の人々は世界を見ていたんじゃないかと思っていて、そのように世界が見えることによって、自分は世界の一部であると強く感じていたような気がするんだよね。
とすれば、超主観空間のような認識が広まることで、より人類が自分を世界の一部として見ていくようになるんじゃないかと期待しているんだよ。
宇野 確かに、猪子さんの考える「やさしく、うつくしい世界」というのは、自分と世界が切り離されていないこと、自分が世界の一部であることへの肯定のイメージが打ち出されているよね。
猪子 しかもその一方で、超主観空間の鑑賞者は、絵画の中に入り込みながら、同時に客観的に絵画を見ることができる、つまり、絵画の中に入りながら、現実空間を認識できる性質があるんだよね。そして、視点の移動が自由になる。
たとえば、お台場で巨大な若冲の作品を展示したけど、プロジェクションマッピングみたいにパースを前提とした平面を巨大化すると、視点が固定されるんだよね。それに対して『追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして分割された視点』なんかは、日本でもシリコンバレーでも子供が飛びまわりながら見るんだよ【1】。でも、そのときに子供は壁にぶつからずに動き回れるし、カラスの前で飛び回るくらいに没入もできる。これは空間を活かした現代的な表現と超主観空間の相性の良さだと思うね。
宇野 それも面白いところだよね。これは雑談として聞いてほしいんだけど、30年前に吉本隆明という思想家が『ハイ・イメージ論』という本で、デジタルテクノロジーが発達していくと、人間の視線は地面に立つ自分自身の主観で把握していく視線と、衛星画像のように自分の位置を客観的に把握していく視線の二つを同時に得ていくようになる、ってことを論じているんだよ。
【1】2016年2月6日から7月1日にかけて、チームラボは、Pace Art + Technology(シリコンバレー)のオープニングエキシビジョンとして大規模個展を開催している。新作含む全20作品を展示。
[リンク]http://www.team-lab.com/news/living_digitalspace_and_future_parks2016
[リンク]http://exhibition.team-lab.net/siliconvalley/
 『追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして分割された視点 – Light in Dark』
『追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして分割された視点 – Light in Dark』
[リンク]https://www.team-lab.net/jp/works/crows_dark
[リンク]https://www.youtube.com/watch?v=tjfDZP9YOcs
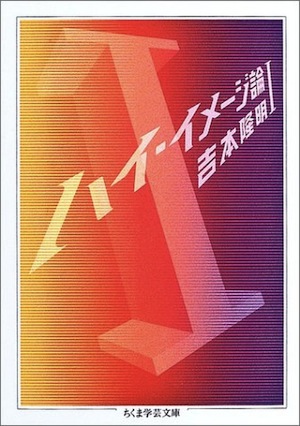
▲『ハイ・イメージ論』吉本隆明
[リンク]http://www.amazon.co.jp/dp/4480088113?tag=wakusei2nd0d-22
猪子 へえー。
宇野 吉本隆明はそれを臨死体験としてよく語られる「自分が肉体から離脱して横たわる自分を眺めている」状態に例えていて、生者と死者の世界の混在というイメージで捉えているけれど、ここもチームラボのモチーフに近いものがあると思う。だから僕は猪子さんの超主観空間の話を聞くたびに、この人の話を思い出すんだよね。吉本隆明という人は80年代に、情報技術が人間の世界の捉え方のようなものを変えていくんじゃないかと論じたんだけど、猪子さんはそれをアートで表現しているように見えるんだよね。だから、今度二人を並べて論じた本を書こうかなと思ってるんだよ(笑)。
猪子さんも同じように、情報技術が世界の見え方を変える、つまり”人間の認識のあり方そのものの変容”に興味があるわけだからね。
猪子 そう。さらに言ってしまうと、超主観空間ではそういう自分の意識を保ちながら没入した人たちが、同時にいろんな場所に存在できるというのが重要なんだよ。というのも、超主観空間の平面は、パースペクティブが固定されてないからね。
宇野 なるほどね。

その他の記事

|
先行投資か無謀な挑戦か ネット動画事業に関する是非と簡単な考察(やまもといちろう) |

|
美食ブームから連想する人間の生態系の急速な変化(高城剛) |
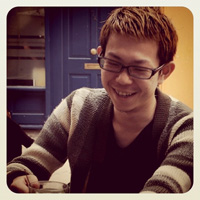
|
『エスの系譜 沈黙の西洋思想史』互盛央著(Sugar) |
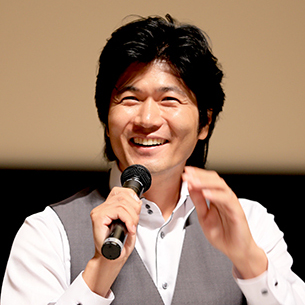
|
孤独と自由との間で、私たちは生きている(西條剛央) |

|
ファミリーマート「お母さん食堂」への言葉狩り事案について(やまもといちろう) |

|
「先生」と呼ぶか、「さん」と呼ぶか(甲野善紀) |

|
「狭霧の彼方に」特別編 その2(甲野善紀) |

|
乱れてしまった自律神経を整える(高城剛) |

|
俺たちのSBIグループと再生エネルギーを巡る華麗なる一族小泉家を繋ぐ点と線(やまもといちろう) |

|
教科別の好き嫌いをなくすには?(陰山英男) |

|
4K本放送はCMスキップ、録画禁止に?(小寺信良) |

|
人は自分のためにではなく、大好きな人のためにこそ自分の力を引き出せる(本田雅一) |

|
人生初めての感動の瞬間(光嶋裕介) |

|
日本の未来の鍵は「日韓トンネル」と「日露トンネル」(高城剛) |

|
ヘッドフォンの特性によるメリットとデメリット(高城剛) |


















