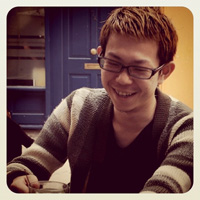先日、臨床心理士、催眠術師、占い師を含む親しい友人たちと会食をしていた時に、誰からともなく「“私”が出てくると施術(セッション)がうまくいかない」という話題になった。それぞれ近いと思われがちだが実際には異なる部分の方が多いジャンル同士だったので、共通項の発見に「お」と一瞬場も盛り上がり、皆自らの経験や伝聞に照らして、その“感じ”について説明しようと試みたが、結局いまひとつ腑に落ちる説明が出てくることもなく、そのままお開きとなった。
これを書いている今現在もうまく言葉にならない掻痒感は消えないままだが、その“感じ”が深まりそうだなと感じた本を、この場を借りて紹介したいと思う。
二つの「自分」
本書『エスの系譜』のキーワードである「エス」は、ドイツ語の代名詞「Es」(英語のIt)であり、何よりも精神分析の創始者フロイトが「暴れ馬のように、手綱を握る自我を振り回す無意識的なもの」を指す名称とした心理学用語としても知られている。が、そもそもこのエスはフロイトの創作物でも、ましてや所有物でもなく、著者も指摘しているように、むしろ人々に突きつけられた一つの謎として、フロイト以前からドイツ圏の思想に通奏低音として脈々と流れ続けてきた。
例えば「彼は具合が悪い」 はドイツ語では「Mit ihm ist es schlecht beschaffen.」と表す。beshaffenは「~(の状態・性質)である」という意味の動詞、schlecht は英語のbadに近い形容詞で、mit ihmはwith him。で、興味深いのは、我々が直接見て取るのはこの「具合が悪い彼」としてのErであるにも関わらず、それとは別に、非人称主語として述語(~である)に対する主体を担っている「Es」が前提とされているという点。
つまり、ここでは異なる二つの「自分」が設定されており、自分の具合が悪いと考えている彼自身の立場に立った時、I thinkの「I=ich」とは別に、そう考えている自分を常に先回りして考えている自分Esがある。「私がある(我あり)」とは、ドイツ語ではich bin ではなく、Es gibt mich(ich)なのだ。(詩人ランボーは「私は一個の他者である」という文言を書き残しているが、その「私」とは言うまでもなく後者の自分Esだろう)。
誰でもない、が自分である。このerやichよりも常に先にあって、矛盾する言明が共存する得体の知れないEs(それ)。コイツはいったい何なんだ? という不可思議に打たれつつも、時にそれから与えられる(というか気付くとポンと置いてある)思いに何らかの確からしさを感じ、耳を傾けてみた。こうした経験は、なにも学者や作家に限らずとも、身に覚えがある人も多いのではないだろうか。

その他の記事

|
ヒトの進化と食事の関係(高城剛) |

|
リアルな経済効果を生んだ「けものフレンズ」、そして動物園のジレンマは続く(川端裕人) |

|
Amazon(アマゾン)が踏み込む「協力金という名の取引税」という独禁領域の蹉跌(やまもといちろう) |

|
「親友がいない」と悩むあなたへ(名越康文) |

|
成功を目指すのではなく、「居場所」を作ろう(小山龍介) |

|
縮む地方と「奴隷労働」の実態(やまもといちろう) |

|
フェイクニュースに騙されないことなど誰にもできない–心理学的メディアリテラシー考(名越康文) |

|
液体レンズの登場:1000年続いたレンズの歴史を変える可能性(高城剛) |

|
学歴はあとから効いてくる?ーぼくは反知性主義的な場所で育った(岩崎夏海) |

|
季節にあわせた食の衣替え(高城剛) |

|
人間は「道具を使う霊長類」(甲野善紀) |

|
「Go To Travelキャンペーン」の正体(高城剛) |

|
光がさせば影ができるのは世の常であり影を恐れる必要はない(高城剛) |

|
「銀座」と呼ばれる北陸の地で考えること(高城剛) |

|
メディアの死、死とメディア(その2/全3回)(内田樹) |