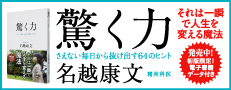驚きとは、システムのほころびを愛でること
驚きとはいわば、「意識と無意識の間に張られた糸が震える音」です。
意識を「システム化された世界」、無意識を「システム化される以前の世界」と言い変えれば、僕らが高度にシステム化された世界を生きる中で「驚き」を失ってきたことがわかります。そもそも、「社会をシステム化していく」というのは、社会から驚きの契機を奪っていく、ということにほかならないのです。
でも、ここがおもしろいところで、どれほど社会をシステム化しようとしても、人間のやることである以上、必ずそこに綻びが生じる。むしろシステム化すればするほど、システムはときに大きく崩れる危険をはらんでいくわけです。
その瞬間、システム化された世界とシステム化される以前の世界の間に張られた糸が「ビィィイン!」と鳴る。その音を耳にした人の心に生まれるのが「驚き」です。
つまり、驚きというのはシステムの崩壊を察知したときに生じる感覚であり、「驚く力」とは、その「音」にどれだけ注意深く耳を澄ませられるかということだといえます。これは、いまの高度にシステム化された社会の中で、僕らがどう生き抜くかを考えるときには避けることのできないキーワードです。
ではどうやって「驚く力」を取り戻していくか。多くの表現者が取り組んでいる課題は、実はそれだと僕はとらえています。そういう目でみると例えばビートたけしさんが『アウトレイジ』『アウトレイジビヨンド』で過剰な暴力を描くのも、松本人志さんが『R100』で、極端なSMの世界を描くのも、極限までシステム化された世界にどう対抗していくかという課題に対する模索であるように僕には思える。
彼らはおそらく、人間の感情の根幹である「共感」までもがシステム化されてしまう社会に息苦しさを感じ、危機感を抱いている。そして、そういうシステムから自由になるためには、「驚く」ということ、すなわち、瞬間的に「心」を崩壊させる必要がある、ということなんだと思うんです。


その他の記事

|
少子化を解消するカギは「家族の形」にある(岩崎夏海) |

|
「お前の履歴は誰のものか」問題と越境データ(やまもといちろう) |

|
アメリカでスクーター・シェアを「見てきた」(西田宗千佳) |

|
中島みゆきしか聴きたくないときに聴きたいジャズアルバム(福島剛) |

|
太陽が死によみがえる瞬間を祝う(高城剛) |

|
iPad Proでいろんなものをどうにかする(小寺信良) |

|
気候変動にまつわる不都合な真実(高城剛) |

|
俺らの想定する「台湾有事」ってどういうことなのか(やまもといちろう) |

|
「戦後にケリをつける」ための『東京2020 オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト』(宇野常寛) |

|
空港を見ればわかるその国の正体(高城剛) |

|
体調を崩さないクーラーの使い方–鍼灸師が教える暑い夏を乗り切る方法(若林理砂) |

|
昼も夜も幻想的な最後のオアシス、ジョードプル(高城剛) |

|
トランプVSゼレンスキー、壊れ逝く世界の果てに(やまもといちろう) |

|
部屋を活かせば人生が変わる! 部屋が片付けられない人の5つの罠(岩崎夏海) |

|
声で原稿を書くこと・実践編(西田宗千佳) |