一人一人の特別なゲーム体験を産むシステムと、遭遇する面白エピソード
現実とリンクしているゲームであるためか、普通のゲームでの目標にあたるものを、自分で決め、そのために努力出来るのも楽しい。僕がやって個人的に達成したものにこんなものがある。
『皇居を全部、自陣営に染める』
皇居の内堀の外をロードバイクで何周もして、ある程度まで成功。ただどうやっても皇居内――しかも通常の参賀では絶対に入れない箇所――に侵入しないと出来ないPortalがあるのだが、これは一体、誰が設置したのだろう? 流石に僕には皇宮警察の目を盗んでまで、二重橋奥のPortalをhackする勇気はなかった。ちなみに首相官邸内のWi-Fiから、Ingressにアクセスしてしまい、その結果、外部には秘密にしているルーターのIPアドレスが漏れ、一悶着という事態もあったらしい。
『隅田川の花火会場を全部緑に染める』
Ingressを初めて2週間目ぐらいに、隅田川花火大会があったため、その時までの隅田側の河畔をつないで自陣営にしようと画策。朝の4時から隅田川に掛かる橋を雨の中、山岳用のゴアテックスのレインコートを着込んで行ったり来たり。これまたある程度までは成功したのだけれども、花火大会が終わったら敵の猛反抗を受けて挫折。
『埼玉スタジアムを攻略する』
これは緑側プレイヤーの間で、都市伝説的に広まっていた話。埼玉スタジアムに、青側の有力エージェントたちの手によって作られたファームがあった(ファームとは、レベルの高いPortalが集まった場所で、強力なアイテムを入手しやすい)。
埼玉スタジアムを落とすことで、都内へ通勤している彼奴らの、首都襲撃の威力を弱めたいのだが、生半可な攻撃ではすべてを壊せないばかりか、あっという間に修復されてしまう。いつかLevelが高い仲間が集ったら、ぜひ埼玉スタジアムの攻略に行こう……というわけだ。「まるでゾウの墓場を探そうとか、ショッカー基地みたいな扱いだなぁ」と感心した記憶がある。

▲レジスタンス(青)側に占拠された埼玉スタジアム
こうした個人的なチャレンジや、不可思議な都市伝説が、街のアチコチで発生している。ガチのエージェントは、自分の庭に、Amazonで買った燈籠(税別7万円)を設置してPortalに申請していたりするとかしないとか。
そんな「自宅Portal」も、眉唾話だと思っていたら、先日、あるエージェントたちが、地方で深夜に寺の敷地内のPortalを攻めていたら、急にお坊さんが登場。門が空いているとはいえ、参拝でもない深夜の進入を怒られるかとビクビクしていたそうだ。と思ったら、「Ingressですか? まあほどほどに」と諭されたとか。僧侶でもIngressを知っているのか、さすがにブームも加熱しているなと思ったら、なんとそのお坊さんは敵側のエージェントだった。
寺を離れるやいなや、たちまちのうちにPortalを奪還されてしまう。ちなみにその坊さんのエージェント名が「アナンダ」(釈迦の弟子)。「坊さん、自宅をPortalにしているのか」「このAgentは聖お兄さん気取りかよ!」とひとしきり話題になったそうな。
架空現実のゲームではありえない巨大さのため、ハマった廃人のエピソードは単に日本に限らず、中には「私有地に電波塔をカンパで建てちゃった」という米国人プレイヤー集団もいるそうだ。
当然、アメリカの沖縄基地内にもPortalが設置されていたりするのだが、ある日本人エージェントがGoogleに「アメリカ基地内のPortalには近づけません、なんとかしてください」とお願いしたところ、「基地内に入れるエージェントの友人を作ってください」と返されたとか。こんな破格なエピソードが、世界中で枚挙にいとまがない。と同時にプレイすればするほど、こんどはエージェント同士の交流の必要性がどんどんと高まってくるのだ。
(参考リンク)
富士山Portalの攻防
http://ingress.blog.jp/archives/13302988.html
侵入不可能、防御力の高いPortal
http://ingress.blog.jp/archives/13232224.html
Ingress地方遠征で分かる、意外な日本の地域性
現実拡張という側面があるからか、とにかく各プレイヤーの地域性、また個々人のバックグラウンドが反映される。高レベルへと成長するには、行ったことのない場所のPortalにまで足を伸ばさなければならないため、Ingressのエージェントは、よく地方遠征をする。
<この後、話題は日本の地域性から「協力プレイで、ゲームから産まれる、地域中間共同体と世界とのネットワーク」「2つのゲーム思想:Googleの進む未来」へと展開! 続きはメールマガジン「ほぼ日刊惑星開発委員会 2014.10.3 vol.171」をご購読ください!
メールマガジン「ほぼ日刊惑星開発委員会」とは?
 評論家の宇野常寛が主宰する、批評誌〈PLANETS〉のメールマガジンです。 2014年2月より、平日毎日配信開始! いま宇野常寛が一番気になっている人へのインタビュー、イベントレポート、ディスクレビューから書評まで、幅広いジャンルの記事をほぼ日刊でお届けします。 【 料金(税込) 】 864円 / 月 【 発行周期 】 ほぼ毎日(夜間飛行では月に1度、オリジナル動画を配信いたします) 詳細・ご購読はこちらから! http://yakan-hiko.com/hobowaku.html
評論家の宇野常寛が主宰する、批評誌〈PLANETS〉のメールマガジンです。 2014年2月より、平日毎日配信開始! いま宇野常寛が一番気になっている人へのインタビュー、イベントレポート、ディスクレビューから書評まで、幅広いジャンルの記事をほぼ日刊でお届けします。 【 料金(税込) 】 864円 / 月 【 発行周期 】 ほぼ毎日(夜間飛行では月に1度、オリジナル動画を配信いたします) 詳細・ご購読はこちらから! http://yakan-hiko.com/hobowaku.html

その他の記事

|
高城剛がSONYのα7をオススメする理由(高城剛) |

|
菅政権が仕掛ける「通信再編」 日経が放った微妙に飛ばし気味な大NTT構想が投げかけるもの(やまもといちろう) |
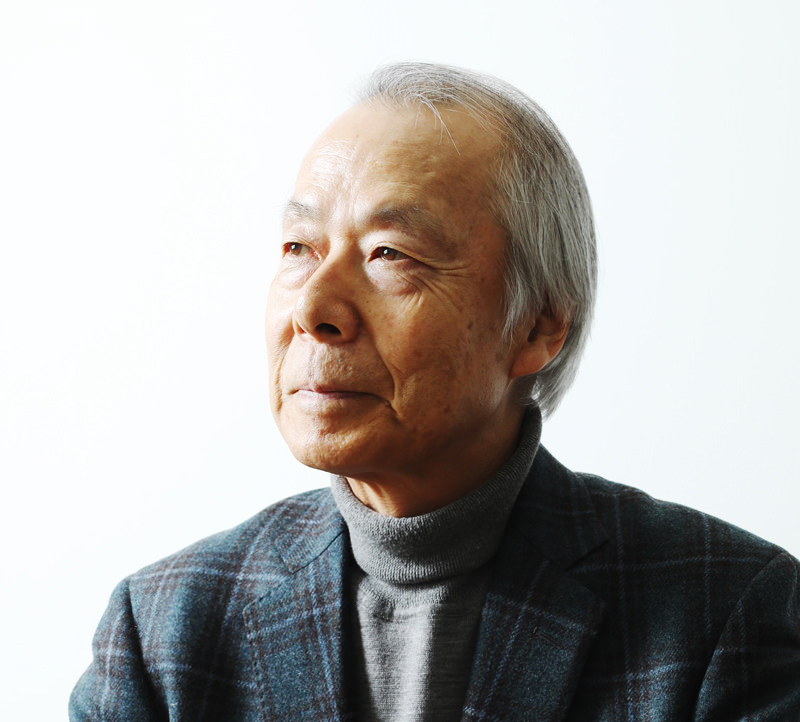
|
トランプは「塀の内側」に落ちるのかーー相当深刻な事態・ロシアンゲート疑惑(小川和久) |

|
家入一真×上祐史浩悩み相談「宗教で幸せになれますか?」(家入一真) |

|
新「MacBook」を使ってみたらーー「ペタペタ」キーボード礼賛論(西田宗千佳) |

|
人生を変えるゲームの話 第2回<一流の戦い方>(山中教子) |

|
レストランからバルへ、大きくかわりつつある美食世界一の街(高城剛) |

|
ふたつの暦を持って暮らしてみる(高城剛) |

|
花粉症に効く漢方薬と食養生(若林理砂) |
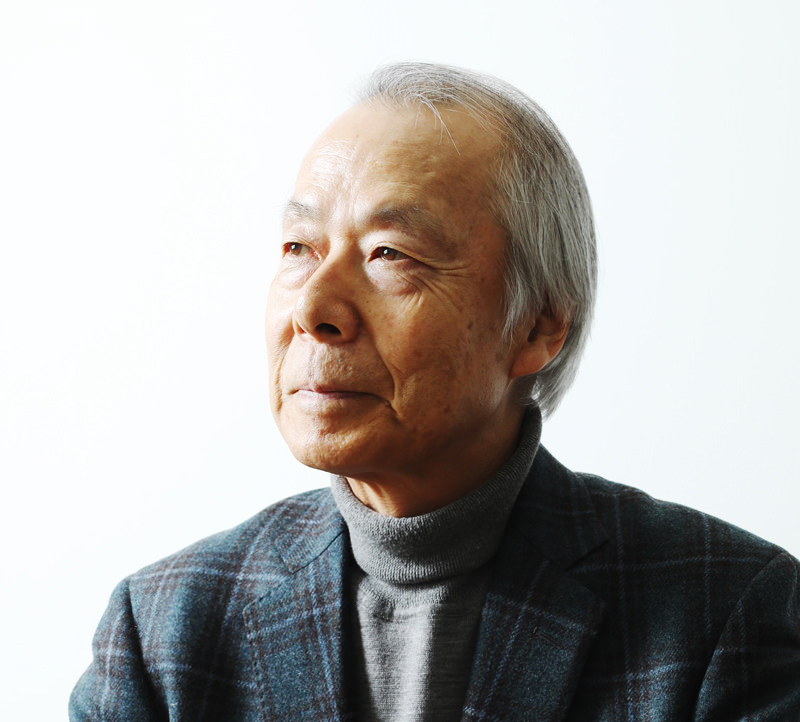
|
会員制サロン・セキュリティ研究所が考える、日本の3つの弱点「外交」「安全保障」「危機管理」(小川和久) |

|
検査装置を身にまとう(本田雅一) |

|
「オリンピック選手に体罰」が行われる謎を解く――甲野善紀×小田嶋隆(甲野善紀) |

|
在留外国人の国民健康保険問題と制度改革への道筋とかの雑感(やまもといちろう) |

|
同調圧力によって抹殺される日本式システム(高城剛) |

|
「新聞を読んでいる人は、政治的、社会的に先鋭化された人」という状況について(やまもといちろう) |

























