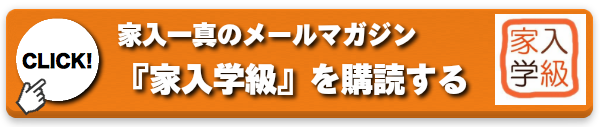「ウィーワーク」と日本のコワーキングの違い
アメリカに「ウィーワーク」という会社があって、そこをモデルにしたビジネスに興味があります。
https://www.wework.com
ウィーワークは、コワーキングスペースをたくさん展開している会社で、今すごい伸びている。フリーランスの人って、普段会社で働くような一体感は得られないもの。けどウィーワークはうまいこと文化を作っていて、そのスペースはフリーランスの集まりなんだけど、会社みたいな雰囲気があるんです。
ウィーワークでは、頻繁にクラブイベントを開催したり、勉強会をしたり、キャンプをしたりしている。だから関わっているみんなが仲がいい。そういう、会社という組織とは別の、新しい仕事場に合った人間関係が、アメリカでは広がっている。これからの日本のモデルにもなるんじゃないかな。
フリーランスで働いている人に、フリーランスならではの不安とか、「こういうのがあったらいいのに」という希望をツイッターで聞いたところ、やっぱり収入に関する不安が最も多く、孤独を感じている人も結構いた。逆にフリーランスが気楽だという人もいたけど、大方は寂しいと思う瞬間がある。
それから、自分だけでは処理しきれない大きい仕事が来たとき、周りにどう仕事をふったらいいかわらないという声もありました。もしフリーランスのネットワークができていたら、「これ一緒にやる奴いない?」と募集したり、仕事をふり合ったりできる。もしかしたら、互助会みたいな仕組みを作って、保険とか、福利厚生とかもまかなえるかもしれない。
ウィーワークがそこまでカバーしているかわからないけど、いずれはそういう方向に進むと思う。今まで会社が担ってきたことを会社が担えなくなるので、一人一人が寄り添い合って生きていくしかない。その仕組みをどうビジネスにするかというのに興味があります。
日本にも、コワーキングスペースはいくつもあります(※メルマガ2時間目で紹介)。それぞれいろいろなスタイルがあるけど、大事なのは適度な距離感。なかにはコワーキングスペースの人間関係に巻き込まれたくない人もいると思うし、普段は話好きな人でも一人で作業したい日だってあると思う。どんな人でも働けるコワーキングスペースが理想的ですね。一度ウィーワークスに視察に行きたいです。
居場所作りはネットワーキングが大事
日本のコワーキングスペースの場合、どうしても自分のブランドで孤立したがるんですよね。例えば地方に行くと、コワーキングスペースを自前でやってます、という人がいるけど、ピンで展開してもうまくいかないと思うんですよね。やっぱりコワーキングスペースはネットワークしていくビジネスなので。
日本人が独立したがる傾向は、リバ邸をやっていても感じました。とあるリバ邸が「違う名前でやりたい」と言い出して、止めなかったけど、「なんでそうなっちゃうかな」と疑問を感じた。僕もリバ邸という名前にこだわっているわけじゃないけど、そう言われたときは、「何も伝わってなかったんだな」と残念な気持ちになりました。
彼らからしてみれば、自分たちが何者でもなかったとき、リバ邸が受け入れてくれる存在だったわけです。それで救われたのだから、次へつなげていくべきないのに、ちょっと自分たちの居場所ができたら、今度は守る方向に動いてしまう。すぐに内輪意識ができてしまうというか。人って悲しいなと思います。居場所ができた途端、自分に居場所がなかった頃のことを忘れてしまうんですよね。
僕はキメラで雇用関係のサービスを作っているけど、コワーキングスペースやフリーランスの働き方についてもすごく考える。相反することではないと思っています。会社という形態はこれからも引き続き必要なものです。でも、そこからあふれる人がこれから増えていくのは明確。望んでフリーランスになるならいいけど、望まずにフリーランスとか非正規雇用になってしまう人については、解決していかなくてはいけない。
採用や雇用についての事業と、フリーランスの人たちの居場所を作る事業は、むしろ両方やって行くべきなんですよね。
<この記事は家入一真メールマガジン「家入学級」Vol.47(2015年10月6日発行)からの抜粋です。続きは下記メールマガジンをご購読してご覧ください!>
家入一真メールマガジン「家入学級」
 Vol.47(2015年10月6日発行)目次
Vol.47(2015年10月6日発行)目次
1時間目:今日の授業「コワーキングスペースから見る居場所作り」
2時間目:日本のコワーキングスペース例
3時間目:「深夜のお悩み相談」一問一答
4時間目:メディア情報・活動予定/学級日誌/次号予告


その他の記事

|
健康寿命を大きく左右する決断(高城剛) |

|
「ふたつの暦」を持って生きることの楽しみ(高城剛) |

|
今週の動画「太刀奪り」(甲野善紀) |

|
先進国の証は経済から娯楽大麻解禁の有無で示す時代へ(高城剛) |

|
「リバーブ」という沼とブラックフライデー(高城剛) |

|
コロナが終息しても、もとの世界には戻らない(高城剛) |

|
誰も無関係ではいられない「メディアの倫理」(小寺信良) |

|
「韓国の複合危機」日本として、どう隣国を再定義するか(やまもといちろう) |

|
新宿が「世界一の屋内都市」になれない理由(高城剛) |

|
「芸能」こそが、暗黒の時代を乗り越えるための叡智であるーー感染症と演劇の未来(武田梵声) |

|
これからのビジネスは新宗教に学んだほうがいい!(家入一真) |

|
先人の知恵と努力の結晶(高城剛) |

|
銀座の通りにある歩道の意味(高城剛) |

|
ブラック企業と奴隷根性(岩崎夏海) |

|
ダンスのリズムがあふれる世界遺産トリニダの街(高城剛) |