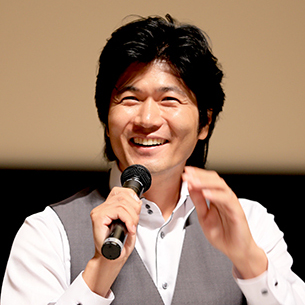中途採用エリートの楽園
さて、そんな弱小織田家だが、信長の出現で一気に勢力を拡大していくことになる。ここで一つの問題が発生する。深刻な人材難だ。もともと中小企業で細々とやっていたのが、突然上場して従業員数が十倍になったようなものだから、家中に人材なんているわけがない。また、織田家は信長以外ロクな人材がいないことでも有名で、一族もまったくあてにはならない。
というわけで、信長は積極的に中途採用をすすめることになる。そして明智光秀、滝川一益、荒木村重といった中途採用者を、代々の家臣以上に重用していく。また、羽柴秀吉のような身分の低い人間であっても、優秀であればどんどん抜擢もする。こんなところにも、彼の型にはまらない価値観がよくあらわれていると言える。
以前も述べたように、織田家というのはスキルを武器に大名家を渡り歩く中途採用者にとってはパラダイスだったはずだ。
職務給型組織への大転換!
ところで、中途採用者にとって天国ということは、裏を返せば年功色が薄いということでもある。近畿を制圧し、安土城を作った後になって、信長は林通勝、佐久間信盛の二名の重臣を突然追放している。いずれも父の代から仕えた老臣で、家中の重鎮的存在だった。理由は、佐久間に出した書状にはっきりと述べられている。
「おまえはこれだけの地位にありながら、ほとんど働いていない。光秀や秀吉を見習ったらどうだ」
ちなみに、佐久間信盛は近畿地方の軍団長的存在だったが、彼の追放後にそのポストについたのは、他でもない明智光秀だ。本能寺の変の2年前のこと。組織の新陳代謝のためには、古い部分を切り捨てなければならないということだろう。
考えてみれば、これは現在の日本企業が直面する課題と同じだ。
どの経営者も腹の中では「もう年功序列じゃいかん、年功によらず抜擢しないと組織は生き残れない」なんてことは痛いほどわかっているが、思い切った人事制度改革には踏み込めていない。
理由ははっきりしている。年功によって最大の恩恵を受けているのが自身であるとよく分かっているからだ。抜本的改革は、自らの権威をも否定することでもあるのだ。日産ルノーのゴーン氏しかり、(企業再建のプロと言われる)日本電産の永守氏しかり、「外からやってきた人にしか日本企業の改革はできない」と言われる理由はこれである。
逆に言えば、弟を殺して当主に就き、そこから叩き上げて天下統一までこぎつけた信長からすれば、心おきなく「いらない奴」をクビにできたわけだ。