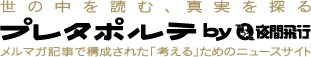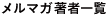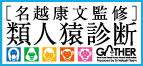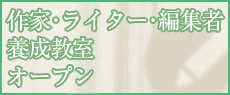アルファベットというテクノロジー
それではそもそもなぜ、本来は無意識のうちに進行するものであった思考の過程に「意識」が介入するようになったのかといえば、その背景には「文字」の登場ということがあった。文字の中でも特に、音声的な言語の世界を空間の中にすっかり写しとってしまう「アルファベット」の登場が大きかった。
アルファベットとは、聴覚的体験としてのことばを、視覚的な文字の世界に射影するテクノロジーである。紀元前1500年頃にセム語族の人びとによって発明されたアルファベットがフェニキア人を介してギリシアに伝わり、紀元前8世紀頃にギリシア人の手によってそこに母音文字が導入されたとき、このテクノロジーはその完成をみる。アルファベットが子音文字と半母音文字からなっていた当初は、読む者が文脈を考慮し、自ら母音を補って読まなければならないという意味で、文字はいまだにことばが発せられた文脈からの自由を獲得していなかったが、ギリシア人による母音文字の導入によって、ことばははじめて、その発せられた文脈からの完全な自由を手にしたのである。
このようにして、本来は聴覚的に観得されるものであった世界を、視覚的に「把握」されるべきものへと変質させていったのがアルファベットというテクノロジーであった。(こ のあたりについては、以前甲野善紀氏のメルマガの中で詳しく議論した)
私たちはもはや「アルファベット以後」の世界を生きている。ことばが常に声の響きとともにあり、文字というものを持たなかった人の思考というのを想像することは容易ではない。
しかし本書『声の文化と文字の文化』の中で、ウォルター・オング氏はその困難と正面から向き合い、文字の文化を生きる者が、文字以前の世界をなんとか思い出してみよう、という難題に挑戦する。それももちろん、文字を使って、である。
文字を知ってしまった人が、文字の世界を前提として、文字以前の世界を想像しようとすると、オートバイを知ってしまった人が「タイヤのないオートバイ」として馬を想起しようとするような、間抜けな事態にもなりかねないから、現在を出発点として遡ることはやめて、そもそもの「おおもと」に一度立ち返ってみようではないかとオングは提案する。
そうして、そもそも聴覚的体験と視覚的な体験の差異はなんであろうか、という問いを手がかりに、様々な研究成果を引用しながら、徐々に「声の文化」の輪郭を炙り出していく。文字で書かれた百数十ページのこの本を読み終わったときには、なぜか「文字以前」の世界の一端に触れてきたような感覚がするから不思議である。
私は本書を読み終えたとき「なるほど、僕がダンスに興味を持つのはそこに文字が介入しないからかもしれない」と思った。私たちが文字というテクノロジーにすっかり依存するようになる以前、thinkingはもっとはるかにdancingに似たものだったのかもしれない。
だとすれば、文字をすでに知ってしまい、文字の文化にどっぷりつかって数学をしている私が、一見数学とは対極にあるように見えるdancingということと真剣に向きあってみることで、そこに新しいthinkingのかたちが立ち上がる可能性があるのではないかと、うっすら期待が膨らむのである。
<森田真生氏は甲野善紀氏メルマガ『風の先、風の跡』にて、「この日の学校」を連載中です。もしよろしければ、ご一読ください>

その他の記事

|
デトックス視点から魚が現代人の食生活に適しているかどうかを考える(高城剛) |

|
うざい店員への対応法(天野ひろゆき) |

|
岸田文雄政権の解散風問題と見極め(やまもといちろう) |

|
脳と味覚の関係(本田雅一) |

|
「報道されない」開催国ブラジルの現在(宇都宮徹壱) |

|
真っ正直に絶望してもいいんだ(甲野善紀) |

|
日本は経済活動の自由がある北朝鮮(高城剛) |

|
「英語フィーリング」を鍛えよう! 教養の体幹を鍛える英語トレーニング(茂木健一郎) |

|
親野智可等さんの「左利き論」が語るべきもの(やまもといちろう) |

|
真夏にひとときの春を感じさせる大西洋の楽園(高城剛) |

|
「GOEMON」クランクインに至るまでの話(紀里谷和明) |

|
カメラ・オブスクラの誕生からミラーレスデジタルまでカメラの歴史を振り返る(高城剛) |

|
「蓮舫代表辞任」後の民進党、野党、ひいては反自民について考える(やまもといちろう) |

|
教養の価値ーー自分と世の中を「素直に見つめる」ということ(岩崎夏海) |

|
オリンピックという機会を上手に活かせたロンドンは何が違ったのか(高城剛) |