※「競争考」はメルマガ「ハックルベリーに会いに行く」で連載中です!
岩崎夏海の競争考(その18)夕陽的とは何か?(前編)
「絶対的な価値」
自然と怒れるようになるためには、物事の正誤の判断が必要だ。しかし、正誤の判断を誤ると、重大な禍を招く危険性がある。そこで、正しく正誤を判断しなければならないのだが、このとき、物差しとなるのは「絶対的な価値」だ。
では、「絶対的な価値」とは何か?――といえば、いくつかあるが、そのうちの重大な一つが「夕陽」である。夕陽の美しさは絶対的な価値なのだ。だから、夕陽の美しさに鑑みて正誤の正しさを判断すれば、誤りが少なくなる。ある事象を見て「夕陽的か否か」が分かれば、その判断がつくのである。
では、「夕陽的」とは何か? 今回は、そのことについて考えてみたい。
「夕陽的」とは何か?
「夕陽的」とは何か? それは、言い換えれば「夕陽はなぜ美しいのか?」ということになる。では、なぜ夕陽は美しいのか? なぜ、誰も夕陽の美しさを否定できないのか? その答えの一つは、夕陽が「昼」と「夜」の両方をはらんでいる――ということだろう。
夕陽は、昼と夜の両方をはらんでいる。そして昼と夜は、「ポジティブとネガティブ」といった二元論の象徴的存在でもある。人間は二元論が好きだ。だから、すぐ「昼と夜のどちらが好きか」といった話になる。多くの人は昼が好きだろうが、しかし夜が好きという人もけっして少なくない。このバランスが、どちらかに完全に傾くということは永遠にないだろう。人類が存続する限り、昼が好きな人と夜が好きな人は、両方存在し続ける。
夕陽は、そのどちらをもはらんでいるのである。夕陽は、昼でもあれば夜でもある。いやむしろ、昼より昼っぽい側面があり、夜より夜らしい側面がある。これは、昼好きも夜好きも否定できないのである。夕陽を否定すると、自分が好きな昼や夜までをも否定することになるからだ。はっきり言って、夕陽はずるい。両者のいいとこ取りだからだ。
しかしそれゆえ、夕陽は強い。二元論の両方をいいとこ取りしているところが、夕陽の美しさの一つの理由――つまり夕陽的であるということだ。


その他の記事

|
驚き呆れるしかないセイシェルの変貌ぶり(高城剛) |

|
これからの日本のビジネスを変える!? 「類人猿分類」は<立ち位置>の心理学(名越康文) |
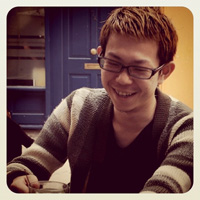
|
『ご依頼の件』星新一著(Sugar) |

|
仮想通貨(暗号資産)相場は何度でもバブり、何度でも弾ける(やまもといちろう) |

|
「芸能」こそが、暗黒の時代を乗り越えるための叡智であるーー感染症と演劇の未来(武田梵声) |

|
東京オリンピックに縁のある体育の日に気候変動のことを考える(高城剛) |

|
歴史に見られる不思議なサイクル(高城剛) |

|
秋葉原の路上での偶然の出会いこそが僕にとっての東京の魅力(高城剛) |

|
小笠原諸島の父島で食文化と人類大移動に思いを馳せる(高城剛) |

|
ネットも電気もない東アフリカのマダガスカルで享受する「圏外力」の楽しみ(高城剛) |

|
注目のスーパーフード、食用大麻で腸内環境の改善を目指す(高城剛) |

|
いわゆる「パパ活」と非モテ成功者の女性への復讐の話について(やまもといちろう) |

|
AirPodsから考えるBluetoothの「切り換え」問題(西田宗千佳) |

|
資源がない国から徐々にリセッションの足音が聞こえてくる(高城剛) |

|
「苦しまずに死にたい」あなたが知っておくべき3つのこと(若林理砂) |




























