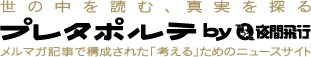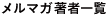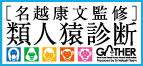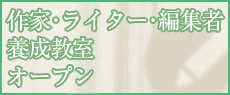敬虔な伝道師が信仰を捨てるまで
これから田口さんと信仰について様々にお話しを続けるにあたって、今回は、まずこの『ピダハン』の中に記されている、その信仰を捨てるに至った告白部分を引用紹介させて頂きたいと思います。
ピダハンと共にいようとするわたしなりの理由づけは、自分の人生と生き方とをかけてきたメッセージがピダハンの文化にそぐわないということで、根底の部分で困難に突き当たっていた。ひとつ言えるのは、ピダハンのところにもってきた神聖なメッセージが世界のどこに行っても通じるものだと決め込んでいたわたしの自信には、じつは根拠などまったくなかったということだ。
ピダハンは、新規な世界観を受け入れる市場ではなかった。人の手など借りずとも、自分のことは自分で守れるし、守りたい人々だ。初めてピダハンの村を訪れる前にかの人々に関する文献を読んでいたなら、伝道者たちがかれこれ二世紀以上も彼らを改宗しようと骨折っていたことがわかっただろう。ピダハンとその近親のムラという人々が西洋社会に最初に出会った十八世紀、彼らは「偏屈」の異名をとった――それ以後の歴史で、いかなる時代にも「回心」したピダハンの存在は知られていないのである。それを知ったからといって、わたしがくじけたとは思えない。新米伝道師の例にもれず、わたしも瑣末な事実など笑い飛ばし、自分の信念をもってすればいかなる障害も最後には乗り越えられると信じたはずだ。けれどもピダハンは迷ってはいなかったし、「救い」を求める必要も感じてはいなかった。
直接体験の原則とは、直に体験したことでないかぎり、それに関する話はほとんど無意味になるということだ。これでは、主として現存する人が誰もじかに目撃していない遠い過去の出来事を頼りに伝道をおこなう立場からすれば、ピダハンの人々は話が通じない相手になる。実証を要求されたら創世神話など成り立たない。
驚いたことに、これらすべてにわたしは心を揺さぶられてしまったのだった。わたしが信じたほうがいいと言ったというだけの理由では信じようとしないピダハンの態度は、必ずしも予期しないものではなかった。伝道の仕事が楽なものだと考えたことは一瞬たりともない。けれども自分が受けた衝撃はこれだけではなかったのだ。ピダハンに福音を拒否されて、自分自身の信念にも疑念を抱くようになったのだ。それがわたしには驚きだった。わたしは決してひよっこではなかった。ムーディ聖書研究所を首席で卒業し、シカゴのストリートでの説話もこなしたし、救援活動でも話をした。戸別訪問もやり、無心論者や不可知論者とも論争した。信仰弁護論や個人伝道の訓練も積んでいた。
しかし同時にわたしは、科学者としての訓練も積んでいた。大事なのは実証であり、ピダハンがいまわたしに実証を求めているように、科学者としてのわたしなら、何らかの主張には実証を求めて当然だった。ピダハンが求める実証を、いまわたしは手にしていなかった。あるのはただ、自分の言葉、自分の感覚という補助的な傍証だけだった。
ピダハンが突き付けてきた難問のもうひとつの切っ先は、わたしのなかに彼らに対する敬意が膨らんでいたことだった。彼らには目を見張らされることが数えきれないほどあった。ピダハンは自律した人々であり、暗黙のうちに、わたしの商品はよそで売りなさいと言っていた。わたしのメッセージはここでは売り物にならない、と。
わたしが大切にしてきた教義も信仰も、彼らの文化の文脈では的外れもいいところだった。ピダハンからすればたんなる迷信であり、それがわたしの目にもまた、日増しに迷信に思えるようになっていた。
わたしは信仰というものの本質を、目に見えないものを信じるという行為を、真剣に問い直しはじめていた。聖書やコーランのような聖典は、抽象的で、直観的には信じることのできない死後の生や処女懐胎、天使、奇跡などなどを信仰することを称えている。ところが直接体験と実証に重きをおくピダハンの価値観に照らすと、どれもがかなりいかがわしい。彼らが信じるのは、幻想や奇跡ではなく、環境の産物である精霊、ごく正常な範囲のさまざまな行為をする生き物たちだ(その精霊をわたしが実在と思うかどうか別として)。ピダハンには罪の観念はないし、人類やまして自分たちを「矯正」しなければならないという必要性ももち合わせていない。おおよそ物事はあるがままに受け入れられる。死への恐怖もない。彼らが信じるのは自分自身だ。わたしが自分の信仰に疑いをはさんだのはじつはこれが初めてではなかった。ブラジルの知識人や、ヒッピー暮らし、それにたくさんの読書のせいで亀裂が入ってはいたのだ。ピダハンはその最後の一石になった。
そんなわけで一九八〇年代の終わりごろ、わたしは少なくとも自分自身に対しては、もはや聖書の言葉も奇跡も、いっさい信じていないと認めるにいたっていた。わたしは隠れ無神論者だった。胸を張れることではなかった。愛する者に気づかれはしないかとひやひやしていた。いつかは打ち明けなければならないと思う一方、打ち明けた結果が恐ろしくもあった。
伝道団やその財政的支援者たちには、伝道活動は尊いチェレンジだという感覚がある。イエスに奉仕するために危険な世界の果てに自ら赴くのは、自分の信仰を体現しようとしているのだという感覚だ。伝道すべき土地に着くなり、利他精神に満ちた冒険の暮らしを始められるものとされている。あきらかにそれは、自分の真実に合せて人々を回心させたいという伝道者本人の欲求が支えになっているのだが、それ以外の思惑が潜んでいる場合もあるし、改宗が人に集団に及ぼす影響も一言では語り切れない。
わたしがようやく事態を受け入れ、自分が「脱信仰」したことを人に知られてもいいという心境になれるまでには、信仰に初めて迷いが生じてから二〇年が経っていた。そして予想はしてたものの、とうとう自分の変節を公にしたとき、結果は無残なものだった。親しい友人や家族に、みんなの人生の基盤にもなっている信仰を―血肉となっている信念を―自分はもう共有していないと告げるのは生易しいことではない。ひょっとしたら、こちらが異性愛者であることを露ほども疑っていない相手に、ゲイであるとカミングアウトするのに、似ているかもしれない。
結局、わたしが信仰を失い世界観が揺らいでしまったことで、わたしの家族は崩壊する羽目になった。わたしが最も避けたかった結果だ。
ファオラニ族の人々に伝道をおこなった殉教者ジム・エリオットは、読んだあとわたしの心に何年も響きつづけた一文を残している。「失うことができないものを得るために自分がもちきれないものを差し出す者は、おろかではない」もちろんエリオットが言いたかったのは、この世界――わたしたちが永遠にもちつづけることはできない――を諦めるということなど、神を知り、失うわけにいかない天国に住まうためであれば小さな代償だということだ。
わたしは、自分がもちきれない自分の信仰を、失うことのできないものを得るために諦めた。わたしが失うことができなかったのは、トマス・ジェファーソンが「精神の専制者」と呼んだもの――自分自身の理性よりも外部の権威に従うこと――から、自由になることだった。
ピダハンに出会いわたしは、長い間当然と思い、依拠してきた真実に疑問をもつようになった。信仰心を疑い、ピダハンと共に生活していくうちに、わたしはもっと深甚な疑問、現代生活のもっと基本の部分にある、真実そのものの概念も問い直しはじめるようになっていた。というより、わたしは自分が幻想のもとに生きていること、つまり真実という幻想のもとに生きていると思うに至ったのだ。神と真実とはコインの表裏だ。人生も魂の安息も、神と真実によって妨げられるのだ―ピダハンが正しいとすれば。ピダハンの精神生活がとても充実していて、幸福で満ち足りた生活を送っていることを見れば、彼らの価値観がひじょうに優れていることのひとつの例証足りうるだろう。……後略『ピダハン』 p373~377


その他の記事

|
間違いだらけのボイストレーニング–日本人の「声」を変えるフースラーメソードの可能性(武田梵声) |

|
大麻によって町おこしは可能なのか(高城剛) |

|
バーゲンプライスが正価に戻りその真価が問われる沖縄(高城剛) |

|
スターウォーズとレンズとウクライナ紛争(高城剛) |

|
結局「仮想通貨取引も金商法と同じ規制で」というごく普通の議論に戻るまでの一部始終(やまもといちろう) |

|
「データサイエンスと個人情報」の危ない関係(やまもといちろう) |

|
失ってしまった日本ならではの自然観(高城剛) |

|
集団的自衛権を考えるための11冊(夜間飛行編集部) |

|
ヘヤカツオフィス探訪#01「株式会社ピースオブケイク」後編(岩崎夏海) |

|
リフレ派の終わりと黒田緩和10年の総括をどのタイミングでやるべきか(やまもといちろう) |

|
英国のEU離脱で深まる東アフリカ・モーリシャスと中国の絆(高城剛) |

|
あらためて「アメリカ放題」を解説する(西田宗千佳) |

|
オランウータンの森を訪ねて~ボルネオ島ダナムバレイ(1)(川端裕人) |

|
「人を2種類に分けるとすれば?」という質問に対する高城剛の答え(高城剛) |

|
揺れる情報商材 違法化、摘発への流れが強まる(やまもといちろう) |