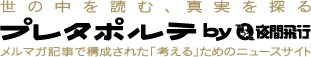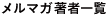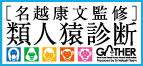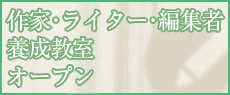切通理作メールマガジン『映画の友よ』Vol.53に掲載された「狂気と愛に包まれた映画『華魂 幻影』佐藤寿保監督インタビュー!」(はないゆい)の再編集版をお届けします。

(本文中写真より)©華魂プロジェクト
取材・構成 はないゆい
4月30日(土)に公開初日を迎えた『華魂 幻影』は、華魂に憑依された人間の爆発した狂気の中で、エロスとタナトスが混沌とする世界を映し撮っている。「映画は生き物」と熱く語る佐藤寿保監督に、『華魂 幻影』に込めた思いをインタビューしました。

写真:佐藤寿保監督 手前は撮影用に使われた「華魂」
――前作『華魂 誕生』は学校が舞台でしたが、『華魂 幻影』は、なぜ閉館する映画館を舞台にされたのですか?
佐藤 『華魂』は10年前に構想を練り、それぞれ話が完結している春夏秋冬編を四部作で作ろうとしたんです。第一弾は学園ものをやろうと決めていたわけではなく、当時、いじめに関する事件が話題になっていたこともあり、学園ものは起点(取っ掛かり)としてやりやすかったというのがあった。その時代の象徴や危機感というものを表したいと思っていて、俺はピンク映画出身なんだけど、ピンク映画館もどんどんなくなりつつあるなかで、第二弾は今この映画を撮っておかなければ、映画館という場所自体がなくなってしまうという一つの危機感があった。
――確かに、今の時代は映画館そのものがなくなっていく危機感が増していますね。
佐藤 この『華魂』シリーズは、大手ではできないテーマ性を持っていると自負しています。前作は学園ものという若者に焦点を当てた映画だったけれども、映画館というのは老若男女が集まる場所。それぞれが色んな人生を抱えた生き方をしているわけで、そういう遊び場所もなくなってしまうという部分と、映画館で映写技師として働く主人公の沢村貞一(大西信満)という男も、フィルムからデジタルに代わり映写技師として消えていく存在。どちらかというとアウトロー的な部分に焦点を当てたかったという部分がある。
それと、映画館と劇中劇、これを『華魂』というひとつのキーワードで繋げ、華魂に憑依されることによって抑圧された欲望、隠された欲望が表出し、華魂によって上映されている映画のストーリーさえも変わってしまうという。
この映画は公序良俗に反する映画かもしれないけれど、「臭い物に蓋をしろ」ではなく、「臭い物を見させない、見ようとしない」今の世の中に対して、俺が今まで作ってきたものと同じようなアンチテーゼが込められている。
時代に染まらない、時代と対峙していく。タイミング的に、「今、この映画をやらなければダメだ」という、監督として作り手としての義務感というか衝動に駆られて、今回の『華魂 幻影』に至ったわけです。
――「今」という時代性を反映し、佐藤監督の熱く強い思いが込められているのですね。
佐藤 現在でもフィルム映画館は存在するし、俺自身は、フィルムそのものはなくならないと思っている。ただ、つまらない映画ばかり上映し、テレビで満足してしまったら、観客はますます映画館に来なくなる。作り手として、映画館そのものがなくなるという不幸、テレビではお目にかかれない面白い映画も映画館がなくなったら観られなくなるという見手側の不幸が生まれるわけで。
だからそのためにも、『華魂』のように自分にしか作れない映画を撮らなければダメだなと。映画というのは永遠に残る。時間が経って観ることによって見え方も変わってくるし、『華魂 誕生』も今見たら、自分にとっても観客にとっても感じること、感覚が違ってくる。「映画は生き物。生き物を殺されてたまるかよ!」という熱い思いがあるわけです。
――映画そのものに対する熱い思い……閉館日に支配人が行ったスピーチからも映画愛を感じました。
佐藤 三上寛さんが演じる映画館の支配人というのは、監督と観客の間のちょうど中間地点というか、映画の作り手は観客との接点がそれほどないが、映画館主は映画を提供する側と観客の接点にいる。そうした部分で、まさしく映画というのは自分のすべてであるという支配人のキャラクター性もあって、あのセリフに至った。映画そのものの中では、受付嬢の若いお姉ちゃんと思わぬ「愛の形」に向かっていくんだけど(笑)。
――支配人だけでなく、あの映画館には、訪れた観客の、年齢差や性差を超えた愛が渦巻いていますね。
佐藤 『華魂』の撮影にあたり、前作から出てくださっている役者さんもいて、「華魂隊」という華魂のためのワークショップもやった。それぞれが持っているトラウマや抑圧されたものが、華魂のキーワードによって解き放たれるというのがテーマなわけで、台詞がない役が大人数いるシーンでも、何人かの役者さんには「こういう形で」とある部分で指示を出して、それが上乗せされるから場面として生きてくる。役者さんは手取り足取り指示されて演じるわけじゃなく、それぞれの感受性で動く職業というか、それを持っていないと役者としての面白味がない。
劇中劇『激愛』の男役を演じた川瀬陽太さんはピンク映画時代から知っていて、端役で出演してもらったことはあるけど、本格的に出演してもらったのは今回が初めてなんです。
――誰もが少なからず持っているであろう超越した愛の欲求や性癖、普段は理性で抑圧しているものの、それが表面的にはちょっと出しても受け入れてくれる人はいるよね、っていう部分から、華魂に憑依されたことで、人間の奥底にある感情が剥き出しにされてしまう。表層心理ではなく深層心理が炙り出されてカオスになっていくのを感じました。
佐藤 それは、まさしく狙いの一つでもあります。人間というのも一つの動物なわけで、社会的にお利口さんになっているけど、「あなたたちは本来それで満足してるの?」っていう感覚はあるじゃない? 自分は密かにほくそ笑んでる感じなので、作り手として、そうした心理部分でキャッチボールしたいなと思っている。世の中自体が、あまりにもテレビと大差ないような映画が多いので、俺はもっと、映画の中で遊んでいる、頭の中で遊んでるような映像があってもいいんじゃないかなというのがあってさ。ガキ的感覚、動物的な映画があってもいいと思うんだよね。
――秩序の箍(たが)が外れたときの愛の噴出、人間本来の姿のような?
佐藤 表層的な「好きだ」という表現は世に溢れ出ている。俺は、映画というのは非日常の世界だという捉え方をしているんだけど、非日常の空間の中で、「さらに刺激的な非日常を垣間見せたい、見せつけたい」という部分があって、それが日常を描いている映画よりもより日常に近付くんじゃないかなと。その人間にとっては。それは「本人が抱えている欲望なり、抑圧された心理。本来、自分自身でも見えない蓋をしている部分なんじゃない?」というこちらからの問いかけでもあるんだけどさ。
愛は年代差を超えても起こりうるわけで、愛の表現としてなかなかできないことを描いた。性差を超えた愛の描写もあるし、スクリーンの向こう側で、過去の自分のトラウマに関わっている少女との思春期のトキメキも映している。映画に対する愛情という部分もあるんだけど、すべての愛という部分でのダルマ(魂)の噴出を見せたかったというのもある。


その他の記事

|
「いままで」の常識が通じない「宇宙気候変動」について(高城剛) |

|
新陳代謝が良い街ならではの京都の魅力(高城剛) |

|
米大統領選に翻弄されるキューバのいま(高城剛) |

|
『「赤毛のアン」で英語づけ』(4) 大切な人への手紙は〝語感〟にこだわろう(茂木健一郎) |

|
「春のイライラ」東洋医学の力で解消しよう!(若林理砂) |

|
“YouTuberの質”問題は、新しいようでいて古い課題(本田雅一) |

|
音声で原稿を書くとき「頭」で起きていること(西田宗千佳) |

|
少ない金で豊かに暮らす–クローゼットから消費を見直せ(紀里谷和明) |

|
身近な日本の街並みが外国資本になっているかもしれない時代(高城剛) |

|
大手企業勤務の看板が取れたとき、ビジネスマンはそのスキルや人脈の真価が問われるというのもひとつの事実だと思うのですよ。(やまもといちろう) |

|
YouTube広告問題とアドフラウド(やまもといちろう) |

|
ビッグマック指数から解き明かす「日本の秘密」(高城剛) |

|
人工呼吸器の問題ではすでにない(やまもといちろう) |

|
「疑り深い人」ほど騙されやすい理由(岩崎夏海) |

|
「大テレワーク時代」ならではの楽しみ(高城剛) |