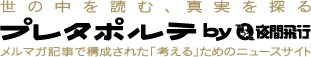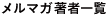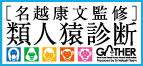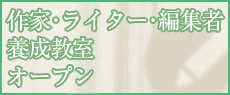「信じる」と「疑う」
「ピダハン」について書かせていただいた後、「ほんとうの信仰」とは何か、何が「信じる」を支えるのか、考えました。そのとき、私は「信じる」と「疑う」の関係について考えるようになりました。そして、「信じたい」の裏には「疑う」があり、「疑う」の裏には「信じたい」があるということ、「疑う」と「信じない」は異なるものであり、「疑う」は「信じる」の消滅を意味しない、ということを考えるようになっていきました。
<2012年8月配信分より>
ここからは、もうひとつのテーマである「ほんとうの信仰」について考えたことを書かせていただきます。さきのお手紙で、甲野先生は浄土真宗の信仰者のなかで妙好人と呼ばれる人々のことを書かれていました。甲野先生が仰る通り、私も、彼らのような「信」の境地には、努力によって辿り着けるものではないと思います。浄土真宗と言えば、以前どこかで甲野先生が書かれていたエピソードも印象深いものです。たしか監獄におけるエピソードであったと思いますが、ある真宗の僧侶が、多くの囚人の前でひと言「浄土で会おうよ」と言い放って去って行き、その僧侶が去った後その場にいた囚人がみんな泣いていたというエピソードです。妙好人の人々とはタイプが異なるのかもしれませんが、この真宗の僧侶が持つ信仰者としての力といいますか、存在感のようなものも、努力などで到達できるものではないと私は思います。
この「縁」ということに関して、前回のお手紙のなかで引用させていただいた森岡正博氏の「信じる」と「感じる」に関する文章を読みながら、改めて考えたことがあります。それは、「紙一重」と我々は良く言いますが、それは実は「無限の距離」なのかもしれないということです。紙一重は、実は絶対に埋められない断絶のことでもあるのではないでしょうか。
これは信仰の話に限らないことだと思います。たとえば、戦場でどの兵士が死ぬのか、客観的に見れば、それは確率の問題にすぎません。誰が死に、誰が生き残るのかは、単なる「紙一重」の問題です。しかし、「私」がこの戦場にいて死ぬか否かは「絶対的」な問題です。目の前の兵士が死に、私が生き残った場合、その二人の人間のあいだには「紙一重の差」であると同時に「絶対的な差」、絶対的な断絶が存在します。
親鸞の『歎異抄』の「人を千人殺せるか」の部分にしても、あれは「誰もが人を千人殺す可能性を持っている」という連続的な、「平等悪」のような思想でもあるのかもしれませんが、「縁のない人間は絶対に人を殺すことはできず、縁のある人間は絶対に人を殺す」という、離散的な、絶対に埋めることができない差を表す思想でもあるのではないでしょうか。
おそらく、さまざまなところにこうした紙一重であり、絶対的な断絶でもあるものが存在するのだと思います。そして、信仰のなかにもそれがあるということではないでしょうか。どれだけ努力を重ねたとしても、妙好人の人々のような信心や、『ピダハン』のなかのセウ・アルフレドのようにイエスが「ただある」と感じるまでに内面化された信仰を持てるかどうかはわからないということです。それは、傍から見ればほんの少しの差、紙一重の差のように見えたとしても、実際には生涯埋まることがないかもしれない絶対的な差であるかもしれないということです。
では、セウ・アルフレドや妙好人の人々のような、信じるという言葉が必要ないくらいの信仰以外は価値がないということになるのでしょうか。私はそのようには思いません。信仰を持たない私がこのようなことを言うことはおこがましいことだと思うのですが、迷い、考え続けること、適切な言葉かどうかわかりませんが、「疑い続けること」もまた、「ほんとうの信仰」のひとつの姿なのではないかと思うのです。
「疑い続ける」という行為は、狂信にはありません。ピダハンの人々が精霊に対して抱いているであろう「ただある」という感覚にもありません。前回のお手紙のなかで、私は「断絶を受け入れることが信じるという行為の価値ではないか」と書かせていただきました。断絶を受け入れるとは、「疑い」を受け入れるということでもあるはずです。
そして、疑っても疑っても、それでも絶えず戻ってくる何かが、その人にとっての「ほんとう」ということなのかもしれません。「否定の連続」が行われてもなお、残る何か、立ち現れる何かが、その人にとっての「真実」なのではないかということです。それは、キリスト者にとってはイエス・キリストなのかもしれません。仏教者にとっては「無常」なのかもしれません。疑えば疑うほど、考えれば考えるほど、その「何か」は絶えず戻ってくるのではないでしょうか。その切実さの度合いに応じて。
そもそも、何の関心もない対象を「疑い続ける」ということは、我々には出来ないと思います。「突発的に」疑うということはあるかもしれません。しかし、何度も何度も疑いを持ち、疑い続けるためには、それに応ずるだけの「関心」がこちらになければできません。これは信仰に限りません。前回のお手紙のなかで、甲野先生は「何かの宗教を信仰し始めたとしても、基本的に恋愛と似た心理状況で始まったものであれば、恋愛が続くことの方が少ないのと同じで、やがては冷めてしまうか、続いたとしても単なる生活習慣のように日常の中に埋没化してしまうかでしょう」と仰いました。醒めてしまえば、そもそも「疑う」ことすらできなくなってしまうのではないでしょうか。迷い続けること、疑い続けることができるということの裏には、その対象への醒めることのない関心があるのだと思います。自分自身の未来や将来についてもそうかもしれません。自分のこれからの進路や生き方について迷い、疑うということは、それだけ自分の将来について真剣に、切実に考えていることの反映ではないでしょうか。私自身、かつて生きることについて、自分の将来について何の関心も無くなっていた時期がありました。そしてそのときには、自分の将来に対する不安のようなものもなかったのです。まさに「どうでもいい」と思っていたからです。ところが、自分自身の生き方をあらため、少しずつ生きることと向き合い始めたとき、はじめて自分の将来についての不安のようなものが生まれてきました。これは「疑い」といってもいいものだと思います。真剣に向き合うことによって、はじめて「疑い」が生まれてくるということではないでしょうか。
もちろん、度が過ぎた「疑い」は恐ろしい結果を生むことがあります。恋愛ではストーカー行為に発展することもあるでしょう。「疑い」によって破滅的な結果が起こるということもあり得ます。それは「疑う」ことに耐えきれなくなった結果として起こることだと思うのです。そのような破滅的な結果に至ることなく、耐え続けること、「疑い続ける」ということが大切なことなのではないでしょうか。そして、それは「信じ続ける」ということと表裏一体のことであるような気がするのです。
妙好人の人々やセウ・アルフレドの信仰における「信じる」とは異なる意味での「信じる」なのでしょうが、迷い続ける、疑い続けるという信仰のなかでの「信じる」においては、「信じる」という行為と、「疑う」「疑い続ける」という行為は不可分のものなのではないでしょうか。その意味では、適切な表現かわかりませんが、「疑う」という行為は、決して「信じる」という行為に「対立」するものではないのではないかと思うのです。「信じる」という行為のなかには既に「疑う」という行為が含まれており、「疑う」という行為のなかには既に「信じる」という行為が含まれているということなのかもしれません。「疑う」ことによって「信じる」が消えてしまうわけではないのです。繰り返しになりますが、「ただある」と感じる対象に対しては「信じる」という心の働きは生じません。それと同時に、「疑う」という心の働きも生じません。また、信仰を棄ててしまった人が「疑い」を持つこともないのではないでしょうか。信仰を棄ててしまえば、棄てる前の信仰対象を「疑う」ことはないでしょう。それは、ただ単に「信じない」というだけのことです。『ピダハン』の著者のエヴェレット氏が、棄教後にキリスト教の教義や、神の存在を「疑う」ことはないはずです。自分とは切り離されてしまったものだからです。「疑う」と「信じない」は別の心の働きだと思うのです。
疑い続けること、それでも信じたいと思い続けることそのものに価値がある。それは、妙好人の人々のような信心や「ただある」と感じるレベルに達するまでの「途中経過」ではないということです。また、「完全に信仰を棄てる」という段階に達するまでの「途中経過」ではないということです。「信じる」ということは、「疑う」ことも同時に引き受けるということ。その二つは不可分であるということです。そうであれば、「疑う」こともまた、「信じる」ことと同じだけの価値を持つことになります。ある人物にとって、その信仰が切実であればあるほど、「疑い」の強さも大きくなるということもあるのではないでしょうか。「疑う」ことは、決してその人の信仰の「浅さ」を表すものではないと思うのです。むしろ、本気で「疑う」ことができるということは、それだけの「疑い」を引き受けることができるということは、凄いことだと思います。それは、その人の信仰への「切実さ」を反映するものでもあるのではないかと、私は思うのです。
以上のように考えれば、迷い続けること、疑いを持ち続けることは、ある面ではきわめて真摯な姿勢だと思うのです。少なくとも、強引に「疑い」を剥ぎ取ってしまったような狂信に比べれば、遥かに真摯な態度ではないでしょうか。セウ・アルフレドのようなキリスト者の信仰にも、妙好人の人々の信心にも、私は深く心を打たれます。しかし、迷い続ける人の信仰もまた、「ほんとうの信仰」のひとつの姿ではないでしょうか。
(その3へつづく)
<田口慎也氏プロフィール>
1984年生まれ。長野県出身。14歳で強迫性障害を発症後、不安や恐怖について、病や死について考えるようになる。20代前半の頃に、甲野善紀氏の「矛盾を矛盾のまま矛盾なく扱う」という言葉に出会い、甲野氏の活動に関心を持つ。
メールマガジンのご購読はこちら
http://yakan-hiko.com/kono.html



その他の記事

|
観光客依存に陥りつつある日本各地の地方都市の行き着く先(高城剛) |

|
フィンテックとしての仮想通貨とイノベーションをどう培い社会を良くしていくべきか(やまもといちろう) |

|
「おじさん」であることと社会での関わり方の問題(やまもといちろう) |

|
「日本の労働生産性がG7中で最下位」から日本の労働行政で起きる不思議なこと(やまもといちろう) |

|
「直らない癖」をあっという間に直す方法(若林理砂) |

|
カビ毒(マイコトキシン)についての話(高城剛) |

|
年内に来る? Wi-Fi Awareとは(小寺信良) |

|
季節の変わり目に丹田呼吸で自律神経をコントロールする(高城剛) |

|
音声入力とAIによる「執筆革命」(高城剛) |

|
『ズレずに 生き抜く』(文藝春秋)が5月15日刊行されることになりました(やまもといちろう) |

|
画一化するネットの世界に「ズレ」を生み出すということ(西田宗千佳) |

|
『我が逃走』は日本版ハードシングス?(家入一真) |

|
感性のグローバリゼーションが日本で起きるのはいつか(高城剛) |

|
週刊金融日記 第280号 <Instagramで女子と自然とつながる方法 〜旅行編、米朝核戦争に備えビットコインを保有するべきか他>(藤沢数希) |

|
バーゲンプライスが正価に戻りその真価が問われる沖縄(高城剛) |