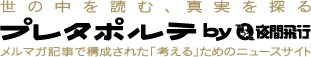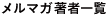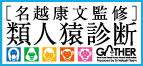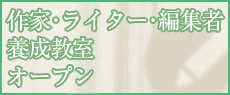その人は立っていた
あれは、確か、私が学生の頃だったのか、酒を飲むことを覚えた時期だったと思うが、新宿の西口を歩いていて、その人を見つけた。
「私の詩集」。そんな風に書かれた小冊子を持ち、その人は立っていた。
ちょっと可憐な感じのする若い女性は、柱か何かの前に凛とした佇まいでいて、その周囲を、通行人の流れが取り巻いていた。どんなにあたりが騒がしくても、そんな俗世間を受け付けない超然とした美しさが、その人にはあったのである。あるいは、そんな風に、私は思い込んでしまったのである。
「私の詩集」という冊子を持って立っている、その女性を見たとき、まだ高校を卒業したばかりくらいの私は、とにかくドキンとしてしまって、実は目が離せなくなってしまった。と言っても、それは心の中の見えない目であって、現実の眼球は、彼女に惹かれていることを隠すかのように、あたりを落ち着きなくさまよっていたのである。
しかも、その時、私は友人の太っちょの哲学者と歩いていたのであって、彼に、そんなおセンチな私の心の動きを悟られることは、何があっても避けなければならないことだった。彼の、温かくはあるが鋭敏で冷笑的なものの見方の前に、私の心の中に芽生えていたファンタジーの種が、砕けてしまうのではないか、そのことを恐れたのである。
それは淡い恋のようなものだったかもしれない
薄幸な文学少女が、自分の作った詩集を、なにがしかのお金で売って生活する。そこには、なんと美しい思いがあったことだろう。「私の詩集」を持って立っている彼女の姿は、私の心にしっかりと焼き付けられた。それは、淡い恋のようなものだったのかもしれない。
それから、駅のその場所を通るたびに、「私の詩集」を持って立っている彼女の姿を、無意識のうちに探してしまう私がいた。ところが、いつも見つかるとは限らないのだった。ふわっと林間から姿を現しては消えてしまう可憐な蝶、アサギマダラのように、彼女が私の世界に現れるときにはどうやら一定の法則があって、その理路を私は完全には理解していない、そんな感じがした。
そして、時たま「私の詩集」の彼女に出くわすことがあっても、なぜか、私は何らかのアクションを起こす、ということができないでいた。「私の詩集」は、売り物には違いない。だから、その対価を払いさえすれば、彼女と何らかの言葉を交わすことは可能であるはずなのに、なぜか、そのような気持ちになれなかったのである。思うに、私はあまりにもシャイだったのだろう。
最初に「私の詩集」の彼女に声をかけたのは、大学院を出て、脳科学の研究を始め、自分の給料をもらうようになってしばらく経ってからのことではなかったか。その日、確か、私は仲間たちとお酒を飲んで騒ぎ、少し落ち着いたところで駅を歩いていたら彼女がいた。なぜか、その日に限って私は大胆になれた。「一冊下さい」と言い、お金を出して詩集を求めた。手にとってみると、手書きで文章を綴った紙がホチキスで留められた、質素なものだった。肝心の彼女とは、一瞬目が合ったものの、言葉もほとんど交わさずにそそくさと歩き去ったのではなかったか。
電車の中で、その詩集をリュックにしのばせた私は、たった今起こったちょっとした冒険に満足していた。そして、どうやらそれで充たされてしまったらしく、せっかく買ったその「私の詩集」を、読むこともなく、やがてどこかに紛失してしまったのである。


その他の記事

|
未来を見据えた働き方 カギは隙間時間にあり(家入一真) |

|
対人関係の9割は「自分の頭の中」で起きている(名越康文) |

|
日本の音楽産業が学ぶべきK-POP成功の背景(高城剛) |

|
れいわ新選組大石あきこさんの懲罰動議とポピュリズム(やまもといちろう) |

|
父親が次男に事業を継がせた深~い理由(やまもといちろう) |

|
「自信が持てない」あなたへの「行」のススメ(名越康文) |

|
アメリカ大統領選はトランプが当選するのではないだろうか(岩崎夏海) |

|
米国の変容を実感するポートランドの今(高城剛) |

|
なぜ若者に奴隷根性が植えつけられたか?(前編)(岩崎夏海) |

|
21世紀、都市の未来は「空港力」にかかっている(高城剛) |

|
総裁選とかイベントとかいろいろあるけど粛々と進めて参る感じの告知と考え(やまもといちろう) |

|
新陳代謝が良い街ならではの京都の魅力(高城剛) |

|
「支持政党なし」の急増が示す政治不信の本質(やまもといちろう) |

|
負け組の人間が前向きに生きていくために必要なこと(家入一真) |

|
日本が抱える現在の問題の鍵はネアンデルタール人の遺伝子にある?(高城剛) |