「食べない辛さ」よりも「食べた後の不快感」
週に1回くらい夕食を抜く生活を2、3か月にわたって続けていると、「食べないことの辛さ」よりもむしろ、「食べた後の不快感」が、これまで以上にはっきりと認識できるようになります。
それ以前も、満腹まで食べた後の身体や頭の重さというものは感じてきましたが、夕食抜きを始めると、それが何ともいえない身体的な不快感であるということがわかる。
はっきり出るのは、四肢のだるさです。たくさん食べた後は、脛の外側の筋肉やふくらはぎ、あるいは前腕、肩甲骨の周囲が重く、だるくなります。
もちろん、人間は食べずに生きていくわけにはいかないので、だるくなるとわかっていてもいつかは食べなくてはいけません。そういう意味では、食との付き合い方に「最終解決」は存在しない、ということでしょう。上り坂、下り坂を繰り返すように、食べている最中の満足感、食べ終わった後の身体的不快感を繰り返すしかない。
ただ、「食べた後の不快感」というものをはっきりと認識できるようになってくると、食欲に関することだけではなく、総合的な身体感覚が開かれてきます。
実はこのことが、「夕食抜き断食」がもたらしてくれる、最大の恩恵だと僕は考えているんです。
感覚複合体から自由になるレッスンとしての「夕食抜き断食」
心を落ち着かせる上でいちばん障壁となるものは何かといえば、一般論としては「対人関係」です。実際、医学書院から出した『自分を支える心の技法 対人関係を変える9つのレッスン』では、対人関係のコツについて、かなりの紙幅を割いています。
しかしながら、もっと時間軸を短くとって、「いま、この瞬間に心を落ち着かせるためにどうしたらいいか」ということを考えるのであれば、「感覚」にフォーカスをあてざるを得ないんです。なぜなら、いまこの瞬間に僕らの心を乱し、集中力を出す妨げになっているのは、実は感覚(複合体)だからです。
僕は風邪を引きやすいタイプで、季節の変わり目ごとに体調を崩し、ひところは年間90日ぐらい風邪を引いていたくらいなんですが、年間90日も風邪を引いて、身体がだるく、寒気がひどい日々を過ごしていると、そういう不快な身体感覚が、いかに人間のやる気や集中力、心の落ち着きを奪うかということが骨身にしみてわかります。
人間は感覚(複合体)に対して徹底的に弱者です。それゆえ、感覚(複合体)を少しでもコントロールできるようになると、自分の心の状態、引いては人間関係は、劇的に改善するんです。
「夕食抜き」は、こうした感覚による支配から自由になるための方法論として、非常に優れた側面を持っていると思います。夕食抜きをとおして、自分たちが“純粋感覚”だと信じているものから、思考や感情を腑分けすることができるようになると、空腹感や食欲以外のさまざまな感覚(感覚複合体)についても、同じように腑分けし、解体していくことができるようになってきます。
例えば、「さびしさ」って、涙が出たり、身体の震えが止まらなかったりすることからもわかるとおり、きわめて高い身体的リアリティを伴う感覚ですが、丁寧に腑分けしてみれば、これもやはり、思考や感情との感覚複合体であることがわかってきます。
現実には、「さびしさ」は一瞬にして心の深いところに根を張ってしまうので、純粋感覚としか思えないわけですが、じっくりと腑分けしていくと“純粋感覚としてのさびしさ”なんて、ほんの少ししか残らないんです。そして、最後まで残ったその純粋な「さびしさ」は、もしかするとそれほど、その人を苦しめる存在ではなくなっているかもしれません。
「夕食抜き」が、こうした「感覚の腑分け」作業に有効なのは、「空腹感」や「食欲」が、さまざまな感覚複合体のなかでもかなり強力な支配力を持つものだからでしょう。
「食欲ほど強力な感覚複合体はない」
実はこれこそが、ダイエットが失敗する、本質的な理由ともいえるでしょう。
また、これとは逆にさまざまな怒り、不安といった感情が、「食欲」の姿を借りて表れることは少なくありません。過食や拒食といった症状が精神科で一般的であることからもわかるとおり、さびしさや怒り、不安といったさまざまな欠乏感は、容易に「食欲」という1つの感覚複合体に結びついてしまうんです。
いずれにしても、「食欲の制御」自体を目的とするのではなく、ひとつの手段として、「感覚複合体から自由になる」ことに取り組むことに、僕は可能性を感じます。それは食欲という、強力な感覚複合体を解体し、感覚と思考と感情とを弁別できるようになれば、人は想像以上に自由になれると考えるからです。
※本稿は名越康文メールマガジン「生きるための対話」2011年11月7日 Vol.015「ダイエットが必ず失敗する理由」および2012年6月4日 Vol.029「「夕食抜き断食」はじめました」を基に再構成したものです。
好評発売中!
驚く力―さえない毎日から抜け出す64のヒント 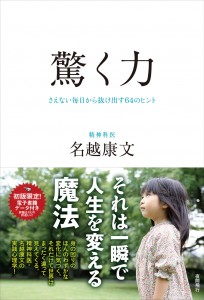
現代人が失ってきた「驚く力」を取り戻すことによって、私たちは、自分の中に秘められた力、さらには世界の可能性に気づくことができる。それは一瞬で人生を変えてしまうかもしれない。
自分と世界との関係を根底からとらえ直し、さえない毎日から抜け出すヒントを与えてくれる、精神科医・名越康文の実践心理学!
amazonで購入する


その他の記事

|
週刊金融日記 第289号<ビットコイン・ゴールド 金の雨が天から降り注ぐ、自民圧勝で日経平均未踏の15連騰か他>(藤沢数希) |

|
ひとりの女性歌手を巡る奇跡(本田雅一) |

|
俺たちが超えるべき103万円の壁と財源の話(やまもといちろう) |

|
「ローリング・リリース」の苦悩(西田宗千佳) |

|
「日本の労働生産性がG7中で最下位」から日本の労働行政で起きる不思議なこと(やまもといちろう) |

|
“日本流”EV時代を考える(本田雅一) |

|
ロシアによるウクライナ侵略が与えるもうひとつの台湾有事への影響(やまもといちろう) |

|
「iPad Proの存在価値」はPCから測れるのか(西田宗千佳) |

|
今村文昭さんに聞く「査読」をめぐる問題・前編(川端裕人) |

|
パー券不記載問題、本当にこのまま終わるのか問題(やまもといちろう) |

|
中国バブルと山口組分裂の類似性(本田雅一) |

|
古いシステムを変えられない日本の向かう先(高城剛) |

|
成功を導くのは、誰からも評価されない「助走期間」だ–天才を育む「ひとりぼっちの時間」(ソロタイム)(名越康文) |

|
猛烈な不景気対策で私たちは生活をどう自衛するべきか(やまもといちろう) |

|
なぜ若者に奴隷根性が植えつけられたか?(後編)(岩崎夏海) |



























