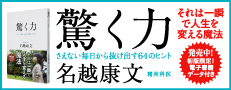好評発売中!
驚く力―さえない毎日から抜け出す64のヒント 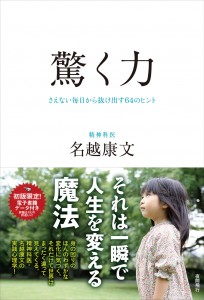
現代人が失ってきた「驚く力」を取り戻すことによって、私たちは、自分の中に秘められた力、さらには世界の可能性に気づくことができる。それは一瞬で人生を変えてしまうかもしれない。 自分と世界との関係を根底からとらえ直し、さえない毎日から抜け出すヒントを与えてくれる、精神科医・名越康文の実践心理学!
amazonで購入する
社会がシステム化することで「共感」の力が失われる
 ――新刊『驚く力 さえない毎日から抜け出す64のヒント』。インパクトのあるタイトルですね。
――新刊『驚く力 さえない毎日から抜け出す64のヒント』。インパクトのあるタイトルですね。
名越 「驚く力」というのは確かにインパクトのある言葉で、読み手によっていろいろと想像力がかきたてられるキーワードですよね。
僕自身は、「驚く力」ということを考える中で、以前よりもずっと深く、「共感」というテーマについて考えることができました。
相手の痛みを知る、もしくは喜びをわかちあうという意味での共感は、人と人とがコミュニケーションする上での基盤といってもいいものです。また、大自然の美しい景色や素晴らしい芸術に触れたときに僕たちの心が揺さぶられるのは、僕らが「モノ」や「コト」に感応、あるいは共感する力を持っているからです。
共感はごく最近まで、僕らの感覚世界の中核を占めるものとして機能していました。例えば、夕陽に感動して一時間立ちつくしてしまう人、たまたま入った蕎麦屋の味に感動して、頼まれもしないのに何倍もの御代を支払う人が、少なくとも前近代までは確実に残っていた。
ところが、そうした本能レベルの「共感」は、僕らの社会が高度にシステム化される中でどんどん失われてきました。社会がシステム化されるときには、そこに生きる僕らの感情や感覚もどんどんシステムの中に組み込まれていってしまう。その結果、あらゆる感覚はパターン化し、形骸化し、力を失っていく。共感も例外ではありませんでした。
特に日本は諸外国に比べて、学校に行き、就職し、結婚し、子育てし……といった社会制度が高度にシステム化され、整備された。そのこと自体は本当にすばらしい、得難いことではあるんですが、その中で「共感」から力が失われてしまったのだと思うんです。


その他の記事

|
「おじさん」であることと社会での関わり方の問題(やまもといちろう) |

|
死をどのように受け止めるか(甲野善紀) |

|
Ustreamが残したもの(小寺信良) |

|
迷路で迷っている者同士のQ&A(やまもといちろう) |

|
「常識」の呪縛から解き放たれるために(甲野善紀) |

|
成功する人は群れの中で消耗しないーー「ひとりぼっちの時間(ソロタイム)」のススメ(名越康文) |

|
「芸能人になる」ということ–千秋の場合(天野ひろゆき) |

|
蕎麦を噛みしめながら太古から連なる文化に想いを馳せる(高城剛) |

|
「死にたい」と思ったときに聴きたいジャズアルバム(福島剛) |

|
「大阪でも維新支持急落」で第三極の未来に何を見るか(やまもといちろう) |

|
「見るだけ」の製品から「作ること」ができる製品の時代へ(高城剛) |

|
ポスト・パンデミックの未来を示すように思えるバルセロナ(高城剛) |

|
なぜ今? 音楽ストリーミングサービスの戦々恐々(小寺信良) |

|
アナログ三題(小寺信良) |

|
南国滞在を引き延ばすもっともらしい言い訳(高城剛) |