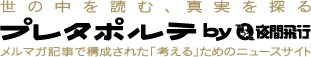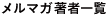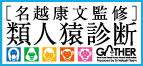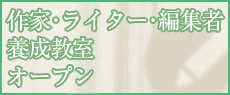――グローバル化や機械化の影響で、企業が今後も、終身雇用・年功序列に代表される戦後日本の雇用形態を維持することは、どうやら難しい。われわれ個人は、あるいは日本は、そうした時代に向けてどんな「準備」をしなくてはならないのか。
2014年6月に新刊『「10年後失業」に備えるためにいま読んでおきたい話』を出版した城繁幸さんと、海外取材の豊富な竹田圭吾さんに、「10年後の働き方」についてじっくりと語っていただきました。初回は日本の30代以上だけが気づいていない「ノーリスクのリスク」について。就活生をふくむすべての「働く人」必読の未来予想図です。
※城繁幸さんメルマガ「『サラリーマン・キャリアナビ』★出世と喧嘩の正しい作法」も好評配信中!
世界的に「反流動化」の流れがある
竹田圭吾:城さんが本に書かれていたことにまったく異論はありません。確かに、年功序列・終身雇用に代表される日本型雇用は、もうもたない。グローバル化、ボーダーレス化していく中で、企業レベルでも個人レベルでも「これまで」にしがみつくのではなくて、新たな雇用のかたちを探っていかなければならないのは、そのとおりだと思います。
ただ一方で、「日本の雇用はどういう方向へ向かうべきなのか」という問題については、なかなか答えを出すのは難しい気がしています。例えば、フランスやドイツのように、解雇規制が強い国では若年層の高い失業率が問題になっているわけですが、一方で、ギリシアやポルトガルのようにすでに雇用が流動化されている国では、頭脳流出が大問題になっています。
世界中のどこへでも行って働ける時代においては、グローバルに評価される能力を持っている人は、出身国にとどまっている必然性がない。もちろん優秀な個々人にとっては、素晴らしい時代になったと言えるでしょう。でも、国の立場から考えれば、国力を維持するためにも人材流出は何としても避けたいでしょうし、「中間層にいる人たちにとって魅力的な職場を維持したい」という企業の立場から考えても、手放しで喜べる状況とは言えないはずです。
このように雇用政策は国際的な環境との絡み合いもあって、道を定めるのが非常に難しい。日本に限らず、ヨーロッパやアメリカでも迷走していると感じています。
 竹田圭吾 ジャーナリスト/編集者/コメンテーター。名古屋外国語大学客員教授。1964年東京生まれ。慶応義塾大学文学部卒。2001年から2010年までNewsweek日本版編集長を務める。フジテレビ『とくダネ!』『Mr.サンデー』レギュラーコメンテーター。J-WAVE『Jam The World』木曜日ナビゲーター。出演番組はほかに読売テレビ『かんさい情報ネットten.』、テレビ東京『未来世紀ジパング』、BS朝日『いま世界は』、テレビ西日本『土曜ニュースファイル CUBE』など。
竹田圭吾 ジャーナリスト/編集者/コメンテーター。名古屋外国語大学客員教授。1964年東京生まれ。慶応義塾大学文学部卒。2001年から2010年までNewsweek日本版編集長を務める。フジテレビ『とくダネ!』『Mr.サンデー』レギュラーコメンテーター。J-WAVE『Jam The World』木曜日ナビゲーター。出演番組はほかに読売テレビ『かんさい情報ネットten.』、テレビ東京『未来世紀ジパング』、BS朝日『いま世界は』、テレビ西日本『土曜ニュースファイル CUBE』など。
城繁幸:確かにヨーロッパにおいて雇用が流動的な国では、人材流出が起きています。これはこれで国として対策を考えていかなければならない問題だと思います。ただ、イタリアにしてもスペインにしても、雇用規制が厳しかった国が今後も「雇用規制の強い国」であり続けることはできないわけです。これらの国では、経済が後退したことで、企業が雇用を維持できなくなり、どうにも切羽つまった中で、雇用の流動化に急激に舵を切らざるを得なくなってしまった。そうした急激な方向転換を受けて、労働組合や左翼が急進化して、国内で軋轢を生んでしまっているんですね。これは多少の頭脳流出などよりも、よほど国の経済にとって悪影響を与えていると思います。
ただ、ヨーロッパ全体を俯瞰するならば、移民に対する排斥運動が活発になっていることを見ても、大きな流れとして「反流動化」が起きているのは間違いないと思います。雇用流動化の本家本元であるアメリカに目を移しても、やはり「最低賃金の引き上げ」法案がシアトルで可決されるなど、行き過ぎた流動化からの「ゆり戻し」が起きています。景気が行き詰まる中で、世界中の先進国で「前近代的なものが緩やかに復活してきたな」という気はしています。
日本が考えなくてはいけないのは、こうした「ゆり戻し」の部分だけの影響を受けてしまっていいのだろうかということです。ヨーロッパやアメリカは、基本的には流動化の流れがあった上で、「ゆり戻し」が起きたりして、それぞれの国の状況に応じて最適化するように調整しているわけですが、日本はまだ流動化の入り口に立ったに過ぎません。その状態で「オバマだって最低賃金を引き上げたのだから、日本も雇用規制をどんどん強めていくべきだ」という話に乗っていいのかどうか……。
竹田:なるほど。日本は「雇用制度」については周回遅れなのだから、世界の先進国と横並びで「○○という国が今こうしているから、われわれも参考にしよう」と考えるのではなくて、まずは周回遅れの分を取り戻すのが先ではないかということですね。
城:そうですね。私はそう考えています。


その他の記事

|
僕たちは「問題」によって生かされる<前編>(小山龍介) |

|
ビッグマック指数から解き明かす「日本の秘密」(高城剛) |

|
グリーンラッシュ:合法な大麻ビジネスがもたらす大いなる可能性(高城剛) |

|
「ローリング・リリース」の苦悩(西田宗千佳) |

|
「人を2種類に分けるとすれば?」という質問に対する高城剛の答え(高城剛) |

|
「意識のレベル」を測る手技を学ぶ(高城剛) |

|
ゲンロンサマリーズ『海賊のジレンマ』マット・メイソン著(東浩紀) |

|
怪しい南の島が目指す「金融立国」から「観光立国」への道(高城剛) |

|
「まだ統一教会で消耗しているの?」とは揶揄できない現実的な各種事情(やまもといちろう) |

|
20代のうちは「借金してでも自分に先行投資する」ほうがいい?(家入一真) |

|
東京新聞がナビタスクリニックの調査を一面で報じたフェイクニュース気味の事態の是非(やまもといちろう) |

|
米豪だけでなく日露も導入を見送る中国通信機器大手問題(やまもといちろう) |

|
中国激おこ案件、でも日本は静かにしているのが正解な理由(やまもといちろう) |

|
「英語フィーリング」を鍛えよう! 教養の体幹を鍛える英語トレーニング(茂木健一郎) |

|
まだ春には遠いニュージーランドでスマホ開発の終焉とドローンのこれからを考える(高城剛) |