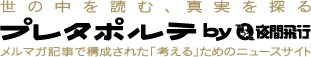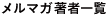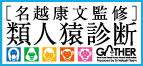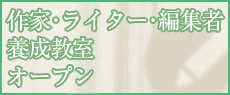ぐるぐる回るのが好き
内田:この話は僕もしたいんだけれど、贈与経済というのは大ネタだから、また今度ゆっくりやろうね。
「交換から贈与へ」という大きな趨勢があると思う。最初に贈与がある。ところが贈与による交換というのは、すごくゆっくりしか進まない。場合によっては円環して「歴史のない社会」になってしまうこともある。けれども、どこかの段階で貨幣をかませるとすごく速くなる。人間というのは、スピードに対して抗し切れない欲望があるんだよね。
ぐるぐる回る。そしてそれが速く回るとなると、もうどうにもならない。そういう人間の傾向も見てあげないと気の毒だけどね。商取引とか市場経済は人間性に悖るわけじゃない。人間性のある部分にフィットしてもいるんだよ。ものがぐるぐる、高速度で回るのが好きで、それに巻き込まれるとくらくらしてくるっていう。ある種の嗜癖なんだ。
マリノフスキーのトロブリアンド諸島のクラ交易(※)があるじゃない? あれも何十年もかかってぐるぐるぐるぐる貝が回るんだけどさ、あれを超高速でやるとF1レースになる(笑)。
※パプア・ニューギニアのトロブリアンド諸島などの民族によって行われる交易。貝の首飾りや腕輪をカヌーによって長い時間をかけて交易圏内で流通させる。圏内を1周するまでに、2年から10年ほどを要する。贈り物と奉仕の相互交換を生み出し、何百キロも離れた人間を結びつけ、義務のやりとりで複雑な規則を課すことによって部族間に網目状の関係が作られる。人類学者のマリノフスキーによって研究された。
クラとは、ニューギニア島南東岸に隣接する諸島群で見られる儀礼的贈物交換の体系を言う。人類学者マリノフスキーが最初に記述した。トロブリアンド、トゥベトゥベやミシマ島などの,広範囲にわたる慣習や言語の異なる部族社会を閉じた環として、その圏内を時計回りに赤色の貝の首飾(ソウラバ)、逆方向に白い貝の腕輪(ムワリ)の2種類の装身具が贈物として、リレーのバトン、あるいは優勝旗のように回り続ける。
平川:なるほど。
内田:やっていることは一緒なんだと思うよ。どっちもまったくの無駄でしょ、F1レースなんか。ぐるぐる回って、とんでもない量のガソリンを使って、大変なお金を使って、人がどんどん死んでいく。でも、人間はそれを我慢できない。クラ交易もぐるぐる回っているもの自体には意味がないんだけど、ぐるぐる回すためには、航海技術や気象学、海洋学を身に付けたり、人的ネットワークを構築しないといけない。
F1もそうだと思うよ。車がぐるぐる回るのは無意味なんだけど、それを成立させるためには膨大な水面下の「それ以外の活動」が必要でしょう。流体力学とか材料工学とかコンピュータ制御とか、あるいは広告とかファッションとかドライバーのメンタル管理とか意味のあるものがないと無意味なぐるぐる周りができない。
平川:それは形を変えてF1レースになっているんだ。何の役にも立たないけどぐるぐる回してる、というのはたくさんあるわけだ。
内田:実はあると思うな。ものがぐるぐるぐるぐる回っているのを、人が見ていることが。
平川:そこに人が集まって、ツイッターみたいに、次から次へと繋がっていく。なにか別のものが起動していくということはあるだろうね。
この話は続けたいと思います。とりあえず今回はここまで。ありがとうございました。
内田:また来月お会いしましょう。
<終わり>
<この文章は内田樹メルマガ『大人の条件』から抜粋したものです。もしご興味を持っていただけましたら、ご購読をお願いします>

その他の記事

|
米国大統領とテカムセの呪い(高城剛) |

|
音楽生成AI関連訴訟、Napster訴訟以上の規模と影響になりそう(やまもといちろう) |

|
テープ起こしの悩みを解決できるか? カシオのアプリ「キーワード頭出し ボイスレコーダー」を試す(西田宗千佳) |

|
参政党「梅村みずほVS豊田真由子」紛争勃発が面白すぎる件について(やまもといちろう) |

|
「スポンサードされた空気」のなかでどのように生きて行くべきなのか(高城剛) |

|
絶滅鳥類ドードーをめぐる考察〜17世紀、ドードーはペンギンと間違われていた?(川端裕人) |

|
「定額制コンテンツサービス」での収益還元はどうなっているのか(西田宗千佳) |

|
マイナンバーカードについて思うこと(本田雅一) |

|
カタルーニャ独立問題について(高城剛) |

|
自然なき現代生活とアーユルヴェーダ(高城剛) |

|
突然蓮舫が出てきたよ都知事選スペシャル(やまもといちろう) |

|
「海賊版サイト」対策は、旧作まんがやアニメの無料化から進めるべきでは(やまもといちろう) |

|
川端裕人×荒木健太郎<雲を見る、雲を読む〜究極の「雲愛」対談>第2回(川端裕人) |

|
「群れない」生き方と「街の本屋」の行方(名越康文) |

|
私的録音録画の新しい議論(小寺信良) |