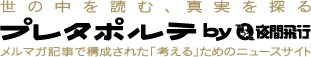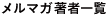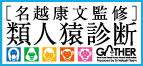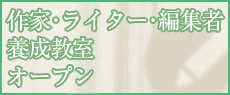「宗教」というイメージ
さて、こうやって書き始めますと、途方もないほど多くのことを貴兄に語りたくなってきて、私自身収拾がつきかねるほどです。ですから、ここでちょっと一息ついて、世の中の人の「宗教」というイメージに近い世界のことについて、貴兄と共に考えてみたいと思います。
私は今まで様々な人に、いわゆる「宗教」を考える上で「是非読んだらいいですよ」と言って勧めている本に、戦前の日本で一世を風靡した新宗教「大本」について、その開祖出口直の一生と、直を世に出し、「大本」を日本中に知らしめた出口王仁三郎の半生を書いた実録大河小説『大地の母』(全12巻)があります。
私がなぜこの本を多くの人達に勧めているかというと、この本は、出口王仁三郎大本教主の孫に当たられる故出口和明先生が、本当に事実をそのまま書かれたもので、大本に関係して随分悲惨な目に遭ったり、人生を棒に振ったりした人の姿を隠すことなく、そのまま描かれているからです。
私がこの本と出合ったのは、私が親しくしている武術の先輩の家に泊まりがけで出かけて、そこで偶々この『大地の母』の11巻目を見つけた時で、先輩は偶然古本屋でこの本を見つけ、私から大本のことを聞いていた事もあり、そのうち読もうかと思って買ってきておいたとの事でした。
その夜は、殆ど徹夜して私はこの本を読みました。なぜそれほど惹き込まれたかというと、いまもちょっとこの本の内容について触れましたが、この本は普通なら、この「大本」にとって隠しておきたいと思うであろうことも、実に詳しく書いてあったからです。
これだけ悲惨なことを書いてある、この本を読んで、大本に惹きつけられるという人もあまりいないかと思いますが、私にとってこの本は実に大きな出合いでした。
この本は、今も言いましたが全12巻という大部なものなので、田口さんのみならず、是非多くの方々に読んで頂きたいところは何ヶ所もありますが、今回は、人間は時にまるで見当外れなことで相手を評価し、その自分の中に起こった勝手な思い込みから、ある宗教も信じてしまう事が起こるのだという一つの例を知っていただきたいと思い、11巻目の「背教者」を引用紹介させていただきます。これを読まれての田口さんの御感想など楽しみにしております。
それにしても、この往復書簡は膨大なものになりそうですね。この先長い道のりになりそうですが、よろしくお願い致します。
(『大地の母』第11巻「背教者」より)
再び桑の葉が茂り、暗紫色の桑の実が熟した。宮飼正慶が綾部の土を踏んで以来もう一年有余になる。雑誌『神霊界』を発行してからは、その編集に参加して、やたらに多忙な時が過ぎた。この頃、しきりに大本を去ることを考える。
小沢惣祐の切腹事件は、宮飼に自分の二度の自殺未遂を思い起こさせた。「曲津にやられた」と小沢は叫んで死んだそうだが、うかうかすると自分もやられかねない危険を感じる。浅野和三郎の鎮魂によって、自分にも良からぬ霊が守護していることを、あばき出された。
今になって宮飼は、飯森正芳が鎮魂を拒否し、大本を去った心境が分かる気がする。
「ぼくに何者が憑いていようと、ほっといてくれ。ぼくはそいつとうまくやっているんだから、鎮魂なんかいらぬお世話だ」と宮飼は叫びたい。
生まれてこの方馴れなじんだ、いわばとけ合った憑霊である。今まで通り仲良くすれば、別に仇をする気づかいはあるまい。
もともと良からぬ霊と言うのも艮の金神の側に立ってみた表現で、反対の側から見れば、艮の金神一派こそ実に良からぬ霊ということになろう。現に世間では、鬼門の金神、祟り神として、昔から忌み嫌い続けてきたではないか。少数に加担して大勢に楯つく不利を思えば、今こそ真剣に考え直すべき時であった。
大本に馳せ参じた人たちは、浅野和三郎はじめ社会にあればそれ相応の地位も財産も得られる人たちだのに、粗衣粗食に耐え、労働に見合うだけの俸給をもらおうともせず、朝夕駆けずり回っている。彼らは、立替え立直しに意義を感じるから、それもよかろう。が、宮飼には、ひどく空しく思える。否、『神霊界』誌上でそれを叫びながら、内心ではその実現を恐れてさえいた。
立替えの時は人類三分になると言うではないか。生き残る三分の側に入れるかとなると、宮飼には全く自信がない。とすれば、これ以上、自分を滅ぼす側に力を貸す愚行は避けよう。
大本へ来て、神霊の実在はどうやら疑い得なくなったが、だからと言って、良からぬ霊を追い出し、艮の金神に服して改心を誓う気になどなれなかった。大本の中に今なお燻っているのは、世間に出て改めて生きるのが億劫なのと、「いや待て、もう少し先まで見届けておけ」という、良からぬ霊の好奇の囁きかも知れなかった。
大体、『神霊界』の編集にたずさわってからの宮飼は、本来の自分ではなかった。どうしたことか、自分でも分からぬ衝動につき動かされて、ただやたらに働きすぎた。ろくなものも食わせられず、しかもほとんど無報酬で。もし世間にあれだけ働いていたらどれほどの報酬が得られただろう。その報酬でまかない得る、どれだけの快楽をふいにしたろう。そう思うと、過ぎ去った一年有余が惜しまれさえする。
大本退去を思う理由は、もう一つあった。動物が本能的に危険を予知するあの感覚である。立替えを叫ぶ大本が、その前に立て替えられる側から押し潰されはしないか、という不安である。宮武外骨の下にいて、政府の言論弾圧は、いやと言うほど思い知らされていた。が、宮武外骨の叛骨とは比較にもならぬ大叛骨が、ここには埋もれている。神や憑霊問題に振り回されていた宮飼も、やがてそれに気づき始めていた。
艮の金神を奉ずる大本は、筆先の指令のままに日本及び世界の現状を否定し、根本的大変革を目ざす思想団体であることに間違いない。かつて王仁三郎と浅野に宮飼は吃りながら言ったことがある。
「た、た、立替えは、た、た、た、単純に精神的方面だけのことにしぼった方が、よ、よいのではありませんか」
浅野は、即座に断言した。
「君、立替え立直しはもちろん精神界においてもだが、現界的には、世界の国々の支配階級が変わり、世の中の仕組みが変わることだよ。筆先をよく拝読すれば、分かることじゃないか」
「そ、そんなこと言って、よ、よいんですか。こ、こ、国家の弾圧が…」
「弾圧を恐れていて、立替え立直しができるものか。ぼくたちはそのために、命を投げ出して参加しているんだ。ぼくは、もう時機は切迫していると信じとる」
議論したくても、円滑に出ぬ言葉がもどかしく、助けを求めるように王仁三郎を見た。茫漠とした表情で煙草をくゆらしている王仁三郎。その目の先にみつめているのは何か、宮飼には、見当がとれなかった。
(中略)
京都駅の山陰線ホームに降り立った宮飼正慶は、思いがけず見覚えのある青年の後ろ姿をとらえていた。一年ほど前までは薄汚れた大本長髪族の仲間だったのが、今は断髪を櫛目正しく左右に分け、すらりとした長身に洋服を着こなしている。が、少々前歯の出た、顎の張った肉づきの薄い青白い顔は、やはり昨年の秋大本を捨てて去った宇佐美武吉にちがいない。ふだんつき合ったことはなかったが、大本を去ったというその一事だけで、妙に親愛の情を感じた。
宇佐美武吉は、わずかの間であったが、管長王仁三郎の秘書役を務め、青竜隊初代の隊長にも選ばれた男だ。神宮皇学館を卒業し一年間伊勢神宮に出仕したというから、当時の大本青年としてはインテリである。第一回目の神島開きに吉田一を背負って従ったのが、印象的であった。昨年(大正五年)の十月二十一日号の『敷島新報』に「世人、祭の意義を知らず」と題して小論文を載せていたが、同年十月四日の教祖・管長夫妻ら一行八十一名の神島参拝の折には参加していなかった。
どういう理由で大本を見限ったか、その真相を知ってみたいものだ。宮飼は、歩調を早めて追いついた。
「う、う、宇佐美君、しばらくですね、お、覚えていますか」
足を止めた宇佐美は、呼びかけた相手が『神霊界』の宮飼だと知って、どきっとした顔をした。
「お、大本へ御参拝でしたか、ちっとも知らなかった」
わざと宮飼が鎌をかけると、宇佐美は気弱く目をそらした。
「私は背教者ですからね、とてもそんな気持ちには…ただ西の方へ行く用事があったので…綾部は素通りでした」
その言葉には、自嘲的な響きがあった。もしかすると大本へ帰る気になったのではないかと懸念していたが、そうでないと知って、宮飼は嬉しくなった。
「ぼ、ぼくもこの頃、大本を去ることを、か、考えているんですよ。い、今も大阪へ、げ、原稿とりかたがた就職の依頼に行くところです。よろしかったら、大本を去られた、ほ、ほ、本当の理由を聞かしてくれませんか」
「さあ、私は大本を否定したのではなくて、大本の神業に落伍したのです。参考になるかどうか…」
ちょうど昼飯時であった。宮飼は宇佐美の背を押し、
「よかったら、うどん屋へでも入りましょうか」と駅前のうどん屋の暖簾をくぐった。
宇佐美は、つかえていたものを吐き出すように、話し始めた。
「結論から先に言いましょう。私の求めるものを大本は与えてくれず、大本は私の性格に合わぬものを押しつけた。私がもう少し辛抱すれば、お互いの希望が一致したのでしょうが、できなかったのですね。それでも大本は、私の人生の旅路の方角を決めてしまったようです。今はそんなゆとりもないが、年をへて振り返って見れば、綾部は私にとって懐かしい思い出深い土地になるでしょう」
「ま、まず入信の経路から聞かせてくれませんか」
宮飼の、記者らしい執拗な聞き方に答えながら、まだ二十三歳の若さに似ぬ分別くさい調子で、宇佐美は語り出した。
宇佐美は、三重県三重郡朝上村田光(現在は菰野町)の宇佐美太郎右衛門の次男。家代々の百姓で、家の宗旨は浄土宗であった。太郎右衛門は五十一歳で神主になったが、その発心の理由が風変わりである。
(中略)
そんな父をもつ宇佐美は、子供の頃から、神仏の世界に憧れを持って育った。小学校を出ると、滋賀県の神職養成部を経て、神宮皇学館に入学した。父母や自分の体験から神霊の実在を深く認識していた宇佐美は、古今の文献からその例証を得たかった。
寸暇をさいて神宮文庫(当時宇治山田市館町、現在は伊勢市倉田山)の門をくぐり、目新しい神秘的な書を読みあさった。天佑記聞・稲生物怪録・嘉津間問答・再生奇聞・日本霊異記・仙界真語・霧島山幽界真語・薩藩神変奇録・幸安物語・兎園小説外篇・怪談老の杖・月見堂見聞集・元禄宝永珍話・享保日記北陸杖・耳袋・今昔物語・甲子夜話・当代記・山境異聞…それらはすべて神霊の実在を基礎に、それから起こる霊象の記録であるが、後にはそれを否定する立場で書いた井上円了の『妖怪学講義録』も読みふけった。
井上円了は哲学者で、世間から化物博士と呼ばれる神霊問題の研究家である。今までの宇佐美の認識をつくがえすほど理路整然とした論文であった。『妖怪学講義録』を何度も読み、「それでもなお自分は神霊の実在を信ずる」と呟くまでには、疲弊しきるほどの研鑽を積まねばならなかった。
この病的なほどの研究に加えて、餓鬼が憑いているとしか思えぬまでの暴食が祟り、宇佐美は胃をこわして見る影もなく痩せ始めた。医薬で治らぬとなると、憑霊の仕業ではないかと思い込むほど憑霊党になっていた宇佐美は、父に相談の手紙を出した。
父は早速、綾部の王仁三郎に問い合わせ、「肉体が疲労しているだけだから、やがて全快するが、息子さんの体質は霊感的にできているので、用心しないと低級霊にもてあそばれる危険がある。一度綾部に来てみてはどうか」と言った返信を得て、宇佐美に知らせて来た。
大正元年冬、宇佐美は、やはり神霊問題に興味を持つ学友の塩月清司を誘って、初めて綾部の土を踏んだ。僅か二日間の滞在であったが、感化は大きかった。
大本から次々に送られる出版物は、二人の心を激しく揺さぶった。
「今の世は体主霊従の悪の世だから、霊主体従に立替え立直さねばならぬ。霊の中には邪神もあれば善神もある。邪神を見破るためにも霊学を勉強して魂をみがかねばならぬ」と言う王仁三郎の主張は、神霊好きの二人をいっそう夢中にさせた。
大正三年、宇佐美と塩月は皇学館卒業と同時に伊勢神宮に奉職した。塩月は大神宮史編纂部、宇佐美は神宮出仕として儀式課に入った。しかし、塩月は単調な事務に飽きたか、大本への魅力が強すぎたか、奉職後三月で神宮を辞し、綾部の大本へ走った。
言霊学と霊学を学びたさに宇佐美が大本へとび込んだのは、翌大正四年春のこと、一年早く大本入りした塩月清司は、心境の変化でもあったのか、国幣大社の多度神社(三重県多度町)の主典として、すでに大本から去っていた。
「そ、そ、それでは、大本は、き、期待したものを与えてくれなかったのですね」と宮飼は、これぞ聞きたい正念場だ、と言うように身を乗り出した。
宇佐美は、蒼白い顔に苦笑を浮かべた。
「大本は忙し過ぎるのです。何もかも混沌としていたのですから」
「それは、い、今もそうです。浅野さんが来てから、いっそう、ひ、ひどくなるばかり…」
「そうです。立替え立直しに向かって驀進する。無我的狂熱的集団です。この中に巻き込まれると、個人的な願望など擦り切れてしまう。昼は御存じのように神苑建設のための重労働です。池を掘る人夫たちの素性を、四方平蔵さんから説明されて驚きましたね。『あれが京都西陣のお召問屋の息子はん、これが京都の大きな材木屋のぼんぼん、あの女の人は松島のお茶屋の女将、あの土運びしている人が海軍予備機関中佐の飯森さん…』と言った調子です。私も決然としてスコップを握りましたよ。でも夜は疲れて鎮魂の勉強どころではありません。言霊学の講習を受けてみましたが、受講者はほとんど学問したことのない人たちばかりで、その人たちに合わせて進む講義が、まどろっこしくてなりません。はじめの間は、それでも満足でしたよ。私もまた立替え立直し熱にうかされていたからです。直霊軍が結成されると、私も勇んで街頭にとび出した。小沢惣祐さんと二人で、綾部から京都まで街道演説しながら一週間かけて歩いたのも、懐かしい思い出ですよ」
「お、小沢さんですって。あ、あの人は、最近、じ、自殺しましたよ。十文字に腹を切って…」
「切腹…」
ぎくりとした目で、宇佐美は宮飼を見た。宮飼が小沢の自殺の模様を語ると、宇佐美は、ほっと溜息をついた。
「そうですか。あの人は冗談の通じぬ人でした。外に現れる行動は無茶苦茶のようでも、性格は生一本でしたからね。自己を燃焼し尽くして消える流れ星のようですね。私には、それができなかったのです」
「お、お、大本が小沢さんを殺したようなものですよ」と憎しみをこめて、宮飼は言った。
が、宇佐美は、宮飼の言葉に同調しなかった。
「さあ、そうでしょうか。大本だからこそ、今まで小沢さんを生かしていたとも言えるんじゃないですか。良い人でしたが、性格が激し過ぎて、社会の枠には入らない所がありました」
宮飼は、飯に入った砂利をかんだような顔をした。


その他の記事

|
週刊金融日記 第279号 <ビットコインはバブルなのか、トランプvs金正恩チキンレースで米朝開戦の危機他>(藤沢数希) |

|
過疎化する地方でタクシーが果たす使命(宇野常寛) |

|
ライカのデュアルレンズを搭載したスマートフォンの登場(高城剛) |

|
ガースーVS百合子、非常事態宣言を巡る争い(やまもといちろう) |

|
世界を息苦しくしているのは「私たち自身」である(茂木健一郎) |

|
迂闊に「学んで」はいけない–甲野善紀技と術理 2017「内腕の発見」(甲野善紀) |

|
幻冬舎、ユーザベース「NewsPicks」に見切られたでござるの巻(やまもといちろう) |

|
資源がない国から徐々にリセッションの足音が聞こえてくる(高城剛) |

|
住んでいるだけでワクワクする街の見つけ方(石田衣良) |

|
影響力が増すデジタルノマド経済圏(高城剛) |

|
憂鬱な都知事選(やまもといちろう) |

|
脱・「ボケとツッコミ的会話メソッド」の可能性を探る(岩崎夏海) |

|
気候変動がもたらす望まれない砂漠の緑地の皮肉(高城剛) |

|
なぜ人を殺してはいけないのか(夜間飛行編集部) |

|
普遍的無意識を目指すあたらしい旅路(高城剛) |