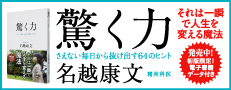社会のシステム化が「うつ」を呼ぶ
共感ですらシステム化されていく社会の中で、「驚く力」は、本当の意味での「共感」を呼び覚ますスイッチになりうると僕は考えています。
そこに取り組まない限り、僕らの社会全体を取り巻くある種の「うつ」状態から抜け出すことは難しいと僕は思う。というのも、「うつ」の根底には、自分の人生が「システム」に支配されているという思い込みがあるからです。
システムは、あらゆることは予測可能であり、予定調和であることを求めます。それは確かに安全・安心な世界かもしれませんが、社会がそちらに向かえば向かうほど、僕らは抑うつ状態から抜け出しにくくなっていきます。
システムがよくできていればできているほど、うつは強くなる。そういう意味では、3.11のような天災によってシステムが一時的に崩壊したときは、僕らが驚く力を取り戻し、うつ状態から抜け出すという点では「チャンス」でした。
しかし実際には、少なくとも社会全体としては、より強固なシステム、より間違いない予定調和を求める方向に進み、さらに社会の抑うつの度合いは増しているように思います。
おそらく、東北で実際に被災した方々の中には、そういう「システムをより強化する方向性」に疑問を抱き、違う方向に舵を切ろうとした人も少なからずいたはずです。しかし、多くの日本人は、結果的にはシステムを強化する方向を選んだ。
それくらい僕たちは、システム化されることを、自ら望んでしまう傾向を持っている。その一方で、世界を完全にシステム化することは不可能であることもまた、どこかで気づいてもいる。


その他の記事

|
ゲンロンサマリーズ『海賊のジレンマ』マット・メイソン著(東浩紀) |

|
「どこでもできる仕事」と「そこじゃなきゃできない仕事」(高城剛) |

|
思考や論理と同じぐらいに、その人の気質を見よう(名越康文) |

|
日本の未来の鍵は「日韓トンネル」と「日露トンネル」(高城剛) |

|
「映画の友よ」第一回イベントとVol.033目次のご案内(切通理作) |

|
「親しみの空気」のない論争は不毛です(名越康文) |

|
いじめ問題と「個人に最適化された学び」と学年主義(やまもといちろう) |

|
石破茂さん自由民主党の新総裁に選任、からのあれこれ(やまもといちろう) |

|
Spotifyでジョギングするとめっちゃ捗る件(小寺信良) |

|
自分の身は自分で守るしかない世界へ(高城剛) |

|
日本が抱える現在の問題の鍵はネアンデルタール人の遺伝子にある?(高城剛) |

|
週刊金融日記 第307号【確定申告の季節ですがこれから事業をはじめる人にアドバイス、出口戦略言及で日本円が大躍進他】(藤沢数希) |

|
ロバート・エルドリッヂの「日本の未来を考える外交ゼミナール」が2017年8月上旬にオープン!(ロバート・エルドリッヂ) |

|
ドイツでAfDが台頭することの意味(高城剛) |

|
参院選で与党過半数割れしたら下野を避けるため連立拡大するよという話(やまもといちろう) |