※メールマガジン「小寺・西田の金曜ランチビュッフェ」2018年2月9日 Vol.162 <Old School New Rules号>より

最近、歩いている最中に原稿を書くことがある。
といっても、歩きスマホで画面をタッチして……というわけではない。音声入力で書くのだ。音声入力の質は、もはや問題ない。ヘッドセット(主に使うのは、AirPodsなどのBluetoothヘッドホンマイクだ)で入力できるのであれば、誤認識は一割あるかないか。タッチやキーボード入力よりも、音声の方がセンテンスレベルでいえば入力速度は速い。効率は決して悪くないのだ。
最近は健康のために2〜3駅歩くことも多く、その際、時間の有効活用も兼ねて、ブツブツとしゃべりながら原稿を書いている。周囲から見れば多少、ヘンな人に見えるかもしれないが、別に大きな声で話すわけでもなく、街道沿いを歩いても、すれ違う人の数はたかが知れている。電車の中など、人が密集した場所での音声入力はちょっと度胸がいるが、歩きながらだと意外なほど、自分にとっては負担ではなかった。30分から1時間歩くと、その間にちょっとしたコラムが出来上がっていたりもする。
とはいうものの。
ぶっちゃけ、キーボードで書く時とは、原稿の書き方を変えなければいけなかった。というか、少なくとも私には、普通にはとても書けない。
というわけで、ちょっとその方法の話を書いてみたいと思う。
普通にタイプで原稿を書くとき、短い原稿であれば、最初から順に書いていく。あとの方で触れるべきことを思い出したらそこを書き、あとからつなげるようなことはするし、書き上がった後で順番を変えたり直したりすることもある。が、まあだいたい、そう長い原稿でなければ「頭から順のが早い」ものだ。2000字くらいまでなら、すぐに脳内である程度の構成が出来上がるので、頭から書いていっても問題はない。
だが、音声入力だとこれができない。奇妙なものなのだが、タイプだと「2000文字先までにどんな内容があるのか」がなんとなく見える気がして楽に書けるのだが、音声入力だと、200文字くらい先までしか、脳の中にイメージを作ることができない。だから、霧の中を進んでいるようで、どうにも書きづらいのである。
これは私だけのことかも知れない。単に音声で原稿を書く回路ができていないからなのかも知れないが、やってもやっても、この違和感は拭えない。だからあることに気付くまで、原稿を音声入力で仕上げるのは無理だ……と、ある意味諦めていたところがある。
しかし、である。
あるとき、やり方を変えてみた。そうすると、原稿をかなり快適に書けるようになり、一気に効率が上がってきたのである。
そのやり方とは。単純なことだ。「完成原稿を書くことを放棄した」のだ。
音声ではあくまで「その行でなにを書くか」という骨子だけを話す。その骨子の積み重ねだけを、まず音声で書くのだ。短文の箇条書きだから、これはできる。そうやって、原稿の最後までになにを書くかを書き出す作業を音声で先にやってしまう。
そして、さらに時間があれば、そこから一行ずつ「肉付け」を音声で書く。これもフレーズが短いから、先を見通さなくても書ける。
これを繰り返していくと、「完成原稿ではないが、原稿の大半が出来上がったもの」が音声だけでできてくる。
今度は、きちんとPCやスマホ、タブレットに向き合う番だ。そうして出来た「粗い原稿」を精査し、きちんとした原稿にする。このブラッシュアップにはさほど時間はかからないので、PCに向かっている時間は節約できる計算になる。
実はこの原稿も、そんな風にベースが作られているのだが、どうだろう? 時間の節約には悪くないやり方だ。
もちろん、この方法には欠点が多数ある。
一番大きいのは、粗原稿の段階で「資料を見ながら作りたい」時には向かない、ということだ。なにしろ、歩いている最中なのだから。歩いていないなら、最初からキーボードに向かった方が早い。
内容をまったく思いついていない時は、当然、キーボードに向かう時と同じように辛い(笑) 中身がぼんやりと見えていて、書かなくては……と思っているような時にはとても効率がいい。
考えてみれば、書籍レベルの長さの原稿を書くときは、頭から順番にかいたりはしない。構成が重要であり、それを自分に可視化することが、まず最優先の作業になる。だからひたすらマインドマップを書いたり、概要のメモを書いたりする。
音声入力での「先が見えない」というのは、書籍レベルの長さの原稿を書く時の「先が見えない」に似た性質がある。だから、構成から組み立てていけば「書けた」のだろう。
みなさんにこのアプローチが有効かはわからない。でも、ちょっとしたヒントとして、実践してみていただけると幸いだ。
小寺・西田の「金曜ランチビュッフェ」
2018年2月9日 Vol.162 <Old School New Rules号> 目次
01 論壇【小寺】
HLG編集、現時点でのまとめ
02 余談【西田】
声で原稿を書くこと・実践編
03 対談【西田】
Cerevo・岩佐さんと語る「出展する人のためのCES講座」(1)
04 過去記事【小寺】
PTA広報紙を電子化したった (4)
05 ニュースクリップ
06 今週のおたより
07 今週のおしごと
 コラムニスト小寺信良と、ジャーナリスト西田宗千佳がお送りする、業界俯瞰型メールマガジン。 家電、ガジェット、通信、放送、映像、オーディオ、IT教育など、2人が興味関心のおもむくまま縦横無尽に駆け巡り、「普通そんなこと知らないよね」という情報をお届けします。毎週金曜日12時丁度にお届け。1週ごとにメインパーソナリティを交代。 ご購読・詳細はこちらから!
コラムニスト小寺信良と、ジャーナリスト西田宗千佳がお送りする、業界俯瞰型メールマガジン。 家電、ガジェット、通信、放送、映像、オーディオ、IT教育など、2人が興味関心のおもむくまま縦横無尽に駆け巡り、「普通そんなこと知らないよね」という情報をお届けします。毎週金曜日12時丁度にお届け。1週ごとにメインパーソナリティを交代。 ご購読・詳細はこちらから!

その他の記事

|
東大生でもわかる「整形が一般的にならない理由」(岩崎夏海) |

|
グルテンフリー食について個人的に思うこと(高城剛) |

|
こ、これは「スマート」なのか? スマートカメラ「IPC-T3710-Q3」が割とやべえ(小寺信良) |

|
あるといいよね「リモートプレゼンター」(小寺信良) |

|
高いエステはなぜ痛いのか――刺激と退屈の心理学(名越康文) |

|
「分からなさ」が与えてくれる力(北川貴英) |

|
上野千鶴子問題と、いまを生きる我らの時代に(やまもといちろう) |

|
季節の変わり目はなぜ風邪をひきやすい?(若林理砂) |

|
アップル暗黒の時代だった90年代の思い出(本田雅一) |

|
カバンには数冊の「読めない本」を入れておこう(名越康文) |

|
格闘ゲームなどについて最近思うこと(やまもといちろう) |
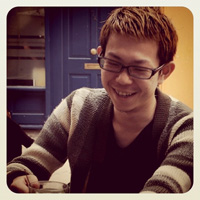
|
『時間の比較社会学』真木悠介著(Sugar) |

|
津田大介×石田衣良 対談<後編>:「コミュニケーション」が「コンテンツ」にまさってしまう時代に(津田大介) |

|
「奏でる身体」を求めて(白川真理) |

|
突然蓮舫が出てきたよ都知事選スペシャル(やまもといちろう) |


















