※メールマガジン「小寺・西田の金曜ランチビュッフェ」2018年10月26日 Vol.194 <変化は常に予兆がある号>より
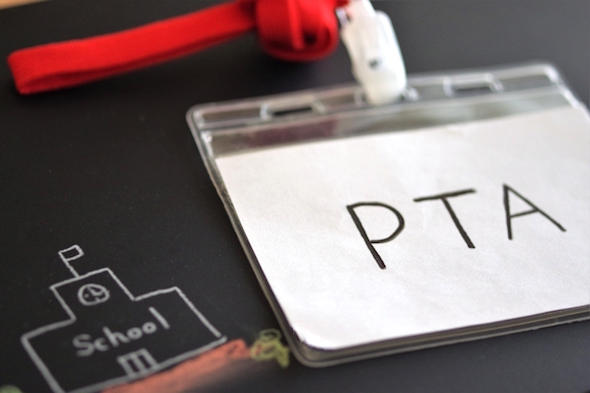
筆者はシングルファーザーになって以来、学校のPTA活動には積極的に参加してきたほうであろう。本部役員こそやってないが、広報委員長や成人教育委員会副委員長などを歴任し、花壇の植え替えや校内清掃などのボランティアにもほぼ参加している。そんな中でも、やってない活動がある。ベルマーク集計だ。
あればかりはどうしても、コストに見合うとは思えないからだ。筆者がPTA広報紙を電子化して予算を浮かせることにしたのも、ベルマーク集めのような非効率的な作業を辞めてしまえるようにという目的があった。だが現実には、なかなか辞められない。60年近くやってきた事を、大鉈をふるって辞めるという気骨のある人がいないのだ。
ベルマーク運動の限界
ベルマーク運動は、1960年、教育環境が整っていない地方の学校を援助するために、協賛企業が売り上げの一部を学校に寄付するためのシステムとして誕生した。
協賛会社の製品パッケージにベルマークを印刷し、それを集めて、希望する商品名と数量とともにベルマーク財団に送る。財団はそれを集計し、各企業にベルマークの量に応じた寄付金を集める。
その寄付金を、財団が協力会社(文具や遊具、スポーツ用品メーカーなど)に送り、メーカーから直接学校に希望商品が納入される仕組みだ。
かつて協賛企業には、ベルマーク運動を通して自社製品を買ってもらえるという、ベルマーク非協賛の競合製品に対する競争力があった。また学校側は、無尽蔵とも言える子供たちとPTAのお母さん方の労力を使えば、自治体からの予算では賄えない必要備品を購入する事ができた。
加えてリサーチやPOSシステムなどが満足に働いていなかった時代では、ベルマークのリターン率で市場調査も可能であった。協賛企業のベルマークに対する寄付金は、調査費用として処理されたのだ。
だが今となっては、誰もベルマークの有無で商品を選んだりしない。ましてや主婦も、暇ではない。専業主婦率が17%程度しかいない小中学校の保護者は、ベルマークを集めるために、半日仕事を休むしかない。起業としても、もはやベルマークによるマーケティングデータよりも、POSやWEBアンケートのほうがよっぽどマトモにデータが取れる。誰も得してない。
そうして10人ばかりが仕事を休んで集計したベルマークが、1,000円分にも満たないことは珍しくない。時給換算すると、保護者1人あたり100円程度。500円玉投げつけて放棄して帰りたいと嘆く保護者もでてくるはずだ。
固着するPTAというシステム
こんな非効率な事が辞められないのは、PTAが平等負担の幻想に囚われすぎているからだ。ベルマークや資源回収のように、誰にでも出来る作業を負担させて余剰金を稼がせる仕組みは、もうとっくに割に合わないものとなっている。じゃあベルマークを辞める代わりに寄付を集めよう、という事になっても、誰も協力しない。「寄付」の文化が、日本にはない。
強制的に徴収すれば、事実上のPTA会費値上げということになる。たかだか年間で100円程度会費が上がったからといって、生活に支障が出るような家庭もないだろう。
実際にPTA会費を値上げするとなると、会費を会則で規定してしまっているところも少なくない。すなわち、そうそう会費なんていじることを考えて組織作りがされていないし、事実昭和時代が会費が同じというところも珍しくないのではないか。
これをいじるとなると、会則の改変が必要となり、PTA総会を開いて決議しなければならない。そこまでのエネルギーを使ってまで、ベルマークを辞めなければならないかといえば、まあ大変だけど今年もこのままで…となるわけだ。
企業が利益の中から、公平に学校に貢献したいという気持ちは、今もあるだろう。ただ、その仕組みとしてのベルマークは、もう終わっている。これ以上延命しても、食品産業以外の企業が貢献できる仕組みにはならない。
必死の思いで学校に行かせた時代は、終わった。校庭に遊具もなければボールもないような学校も、もはや存在しない。PTAの役割も、変わるべきだ。
小寺・西田の「金曜ランチビュッフェ」
2018年10月26日 Vol.194 <変化は常に予兆がある号> 目次
01 論壇【西田】
Computational Photographyの時代
02 余談【小寺】
PTAがベルマーク回収を辞められないわけ
03 対談【西田】
準備中につき今号はお休み
04 過去記事【西田】
XP利用者へ、1年後移行の「最終警告」
05 ニュースクリップ
06 今週のおたより
07 今週のおしごと
 コラムニスト小寺信良と、ジャーナリスト西田宗千佳がお送りする、業界俯瞰型メールマガジン。 家電、ガジェット、通信、放送、映像、オーディオ、IT教育など、2人が興味関心のおもむくまま縦横無尽に駆け巡り、「普通そんなこと知らないよね」という情報をお届けします。毎週金曜日12時丁度にお届け。1週ごとにメインパーソナリティを交代。 ご購読・詳細はこちらから!
コラムニスト小寺信良と、ジャーナリスト西田宗千佳がお送りする、業界俯瞰型メールマガジン。 家電、ガジェット、通信、放送、映像、オーディオ、IT教育など、2人が興味関心のおもむくまま縦横無尽に駆け巡り、「普通そんなこと知らないよね」という情報をお届けします。毎週金曜日12時丁度にお届け。1週ごとにメインパーソナリティを交代。 ご購読・詳細はこちらから!

その他の記事

|
ドラッカーはなぜ『イノベーションと企業家精神』を書いたか(岩崎夏海) |

|
「モノ」と「場所」に拡張していくインターネット(高城剛) |

|
デトックス視点から魚が現代人の食生活に適しているかどうかを考える(高城剛) |

|
「群れない」生き方と「街の本屋」の行方(名越康文) |

|
「私、寝袋で寝ようかな」と奥さんが言った(編集のトリーさん) |

|
言葉と、ある相続(やまもといちろう) |

|
古い常識が生み出す新しいデジタルデバイド(本田雅一) |

|
アマゾンマナティを追いかけて〜赤ちゃんマナティに授乳する(川端裕人) |

|
統計学は万能ではない–ユングが抱えた<臨床医>としての葛藤(鏡リュウジ) |

|
YASHICAブランドのスマホ向け高級レンズを試す(小寺信良) |

|
中国資本進出に揺れるスリランカ(高城未来研究所【Future Report】より)(高城剛) |

|
古くて新しい占い「ルノルマン・カード」とは?(夜間飛行編集部M) |

|
総務省家計調査がやってきた!(小寺信良) |

|
気候変動や環境毒のあり方を通じて考えるフェイクの見極め方(高城剛) |

|
テープ起こしの悩みを解決できるか? カシオのアプリ「キーワード頭出し ボイスレコーダー」を試す(西田宗千佳) |

















