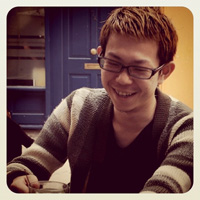読書の原点
子供の頃に星新一のショートショートにお世話になったという人は、ずいぶん多いのではないかと思います。典型的なじっとしていられない子供だった自分にとっても、星新一ははじめて本というものに没頭させてくれた読書の原点でした。
彼の読者だった者なら誰しも、記憶に焼き付いて離れない“特別なお話”というのが一つはあると思いますが、自分の場合、特に本書に収録されている『夜の会話』がそれでした。内容は、一見するとある平凡な男のUFOそして宇宙人との遭遇を描いた軽いSFものという風なのですが、その実「現実はどうやって作る(作られる)のか?」「そもそも人がなにかを見るということとはどういうことなのか?」といった、唯識論的なテーマを扱ったお話になっているんです。
ここのところ、ますます時勢の変化が激しくなり、「現実」をきちんと「見る」ということが難しくなってきたという気がしています。そうした状況のなか、改めて“見通し”というもののありようを問う意味でも、この場をかり先のお話を紹介したいと思います。

その他の記事

|
国が“氷河期世代”をなんとかしようと言い出した時に読む話(城繁幸) |

|
アーミテージ報告書の件で「kwsk」とのメールを多数戴いたので(やまもといちろう) |

|
「HiDPIで仕事」の悦楽(西田宗千佳) |

|
東京新聞がナビタスクリニックの調査を一面で報じたフェイクニュース気味の事態の是非(やまもといちろう) |

|
「代替」ではなく「補完」することで「統合」する医療の時代(高城剛) |

|
4月4日自民党党内処分云々の是非と今後(やまもといちろう) |

|
【号外】「漫画村」ブロッキング問題、どこからも被害届が出ておらず捜査着手されていなかった可能性(やまもといちろう) |

|
意外に簡単に見られる新4K放送。だが課題も…(小寺信良) |

|
季節の変わり目の体調管理(高城剛) |

|
大麻ビジネス最前線のカナダを訪れる(高城剛) |

|
廃墟を活かしたベツレヘムが教えてくれる地方創生のセンス(高城剛) |

|
ソフトキーボード、ほんとうに「物理キーと同じ配列でいい」の?(西田宗千佳) |

|
「歳を取ると政治家が馬鹿に見える」はおそらく事実(やまもといちろう) |

|
広大な地下空間で考える東京再活性化の秘訣(高城剛) |

|
なぜ汚染水問題は深刻化したのか(津田大介) |