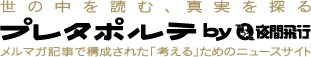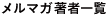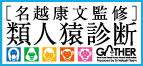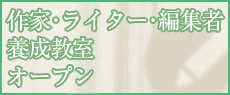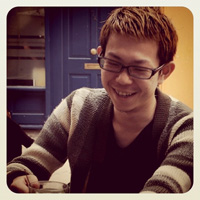沈黙を課しながら語る
したがって、エスの歴史は必然的に茫然自失の連続でもあった。時にエスは「人種」といった一般名詞や、「ヒトラー」のような固有名詞へと実体化され、いつの間にか、それが置き換えであることが忘却されることで、多くの狂信者が生み出されてきた。そうした狂信者は忘却によって真理の感覚を味わう代わりに自らを疎外し、エスをよりもっともらしい姿へ擬人化していくに従い、「考える」という述語さえも喪失していく。「自己を疎外し、エスを擬人化する」なんていうと抽象的だけど、それは「他者」とのコミュニケーションを限りなく困難にすることを意味し、前後不覚をのっぴきならないものにしてしまう。
ニーチェはこうしたケースを言語の虚構に基づく「原因および結果の誤った本物化」とした上で、<主語「私」は、述語「考える」の前提である>と述べるのは事態の捏造であり、述語こそ主語の真理であると喝破した(『善悪の彼岸』)。「それesが考える」と言うのさえ言いすぎ、とまで言ったのだ。
このように精神が行う「考える」や「思う」という働きは、得てして「私」をめぐる誤った信仰に閉じ込められがちであり、述語の喪失を避けるためには、沈黙を課されたエスと、それでもエスの言葉を聴こうとする私の「あいだ」で、矛盾と分裂に目を背けずそれでも立ち続けるしかないのだろう。
沈黙を課しながら語る、分からないものを分からないままに分かろうとする。
「うまくいく」というのは、そういうギリギリのバランスの中で、ポンとつながるパスのようなものなのかなあ、というのが当座の「考え」の粗描である。
ちなみに、本書ではエスのすり替え例として、上記の他に「遺伝」や「心霊」なども挙げられている。また、フロイトと弟子の確執を基点に、ニーチェ、シュタイナー、ブーバー、レヴィ=ストロースなど普段あまり結び付けて考えることのない人物をエスという縦糸で結んでいく著者のスリリングな手腕にも、幾度となくハッとさせられるはずだ。
エスという言葉の得体の知れなさに少しでも引っ掛かった方は、ぜひ一度本書を手にとってみてほしい。

その他の記事

|
ライター業界異変アリ(小寺信良) |

|
IR誘致に賭ける和歌山の今が象徴する日本の岐路(高城剛) |

|
新型コロナウイルスのデマに立ち向かう方法、我が家の場合(本田雅一) |

|
心身や人生の不調対策は自分を知ることから(高城剛) |

|
コロナで変わる観光客とビジネス客の流れ(高城剛) |

|
どうせ死ぬのになぜ生きるのか?(名越康文) |

|
「春のイライラ」東洋医学の力で解消しよう!(若林理砂) |

|
季節の変わり目に丹田呼吸で自律神経をコントロールする(高城剛) |

|
それ「悲報」でもなんでもないから――化粧品はお肌に浸透しません!(若林理砂) |

|
【高城未来研究所】「海外に誇る日本」としてのデパ地下を探求する(高城剛) |

|
想像もしていないようなことが環境の変化で起きてしまう世の中(本田雅一) |

|
「50歳、食いしん坊、大酒飲み」の僕が40キロ以上の減量ができた理由(本田雅一) |

|
歴史が教えてくれる気候変動とパンデミックの関係(高城剛) |

|
ラスベガスは再び大きな方向転換を迫られるか(高城剛) |

|
ワクチン接種の遅速が招く国際的な経済格差(高城剛) |