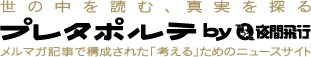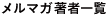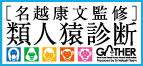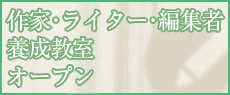信じることへの違和感
先日のお手紙の中で、甲野先生は信仰を持つことに対して「何かを信じるという事をしなければならないわけですが、その事に対して私はどうしても自分自身を欺いているような気がしてならなかったのです」と仰っています。
その感情は、現在の私にも存在しています。であるからこそ、悩みに悩んだ挙句、私は3年前の時点ではキリスト者になることをあきらめたのです。
「信仰への強い憧れ・欲求と拒絶感」という「矛盾」について考えるときに、いつも私が思い起こす一人の人物がいます。それは遠藤周作です。
「物心ついたときには『信仰の内側』にいる人間になっていて、その信仰を完全に受け入れることが出来ずに、信仰の『内側』にいたままもがき続けるひと」もまた、存在するのだと思います。その一人が遠藤周作だと思うのです。
遠藤周作とイエス・キリスト
私はキリスト者ではありませんし、遠藤周作を専門に研究したり、彼に関する研究書や論文を読んでいるわけではありません。あくまで私が彼の作品から得た考えであることをさきにお断りした上で、私の考えを書かせていただきます。
私自身は洗礼を受けるか否か悩みぬいていた時期に遠藤周作の作品に触れました。そして遠藤周作の「カトリックの教義を受け入れ切ることができない苦しみ」に、もの凄く強い共感を覚えました。
「信じきれるものなら信じてしまいたいが、それができない」人間の葛藤と苦しさが、彼の作品の中に強烈に描き出されていたからです。3年前の私には、彼の作品を読むことが途中で辛くなるくらい、その痛みや苦しみが痛切に胸に迫ってきました。
遠藤周作という人は少年時代にカトリックの洗礼を受けていますが、「正統な」カトリックの教義を心の底から信じきることは最後までできなかったのだと思います。
それは、「信仰の思索は、だぶだぶの洋服を和服に仕立て直す作業」という彼の発言にも表れています。キリスト教(一神教)の持つ、ある種の「他を排斥する・削ぎ落とす」側面に、どうしても馴染むことができなかったようです。
また、イエス・キリストの「奇跡」についても、それが実際に起こったと信じきることはできなかったのではないでしょうか。
たとえば『イエスの生涯』に描かれるイエスは、「奇跡を起こすことはできなかったが、弱き者たちの側に『同伴者』として存在するイエス」というものだからです。
そして、「全ての宗教は根本的には同じことを言っている」「他の宗教にも『神』は顕れている」「自然や動物にも『神』は宿っている」といった考え方を持っていたようです。
この考え方はカトリックの教義からみれば、「異端」です。しかし、遠藤周作はカトリックの「正統」な教義を全面的に受け入れることはどうしてもできなかったのでしょう。そして遠藤周作自身、自分の考え方が「異端」であるということを、深く認識していたのだと思います。
であるからこそ、『イエスの生涯』や『沈黙』におけるユダや、キチジローやロドリゴ司祭といった「背教者」たち、イエスを裏切った人物、司祭を裏切った人物、踏み絵を踏んだ司祭を、あれほどの「深さ」で、「深い共感をこめて」描き出しているのだと思います。
そして、そうした「神を裏切らざるを得なかった人間たち」、人間としてある意味「最も弱い存在」である彼らのそばにこそ、イエス・キリストは共におられるのだ、という物語が描かれているのだと思います。それこそ、彼自身のイエス・キリスト像そのものであったのではないでしょうか。
「あの人の人生におけるユダの役割というものが、彼には本当のところよくわからなかった。なぜあの人は自分をやがては裏切る男を弟子のうちに加えられていたのだろう。ユダの本意を知り尽くしていて、どうして長い間知らぬ顔をされていたのか。まるでそれではユダはあの人の十字架のための操り人間のようなものではないか。それに……それに、もしあの人が愛そのものならば、何故、ユダを最後は突き放されたのだろう。ユダが血の畠で首をくくり、永遠に闇に沈んでいくままに棄てておかれたのか。」
「司祭は足をあげた。足に鈍い重い痛みを感じた。それは形だけのことではなかった。自分は今、自分の生涯の中で最も美しいと思ってきたもの、最も聖らかと信じたもの、最も人間の理想と夢にみたされたものを踏む。この足の痛み。その時、踏むがいいと銅板のあの人は司祭にむかって言った。踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生れ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ」
「主よ。あなたがいつも沈黙していられるのを恨んでいました」
「私は沈黙していたのではない。一緒に苦しんでいたのに」
「しかし、あなたはユダに去れとおっしゃった。去って、なすことをなせと言われた。ユダはどうなるのですか」
「私はそう言わなかった。今、お前に踏み絵を踏むがいいと言っているようにユダにもなすがいいと言ったのだ。お前の足が痛むようにユダの心も痛んだのだから」
(『沈黙』より)
遠藤周作は、「正統な」カトリックの教義そのものを「全面的に」受け入れることは、生涯できなかったのだと思います。しかし、それでも彼は「イエス・キリスト」という存在に対する「信頼」もまた、捨てることができなかったのだとも思います。
「教義を丸ごと受け止めることはできないが、イエス・キリストという存在を『信じる』ことはできる」。奇妙な言い方になりますが、イエスという存在が「薄皮一枚」、彼をキリスト教につなぎとめていたのではないでしょうか。
イエスへの信仰を自分なりに受け入れるためにのた打ち回り、苦しんで苦しんで、それでも、「そういう『弱い人間』のそばにこそ、イエスは共におられるのだ」という考え方に彼は至ったのだと思うのです。
遠藤周作の最晩年の作品である『深い河』のなかに、とても印象深い台詞があります。「大津」というキリスト者の台詞です。彼は「美津子」という女性から「神を棄てる」ように迫られたときに、以下のように述べます。
「ぼくが神を棄てようとしても……神はぼくを棄てないのです」
この台詞に、私は遠藤周作のキリスト教、いやイエス・キリストへの「想い」の全てが込められていると思っています。
遠藤周作の作品を読む限り、彼はいわゆる「宗教多元主義」、すなわち「全ての宗教は根本的に同じことを言っている」という考えに至っているわけですが、彼の場合は「安易なる宗教多元主義」ではないと思います。
本当にのた打ち回り、考えに考え抜いて、その考えに至った、至らざるを得なかったのだと思います。
おこがましい言い方かもしれませんが、私は彼のその姿に痛々しさと、強い共感と、深い敬意を覚えます。私はキリスト者になりかけてならなかった人間であり、今でも信仰の「外側」にいる人間です。
しかし、遠藤周作は子どものときに洗礼を受け、キリスト者として、信仰の「内側」にいる人間として生きることを運命づけられていた人でした。だからこそ、彼の苦しみは、
私が洗礼を受けるか否かで悩み、惑っていた時の苦しみとは比較にならないほど強いものだったのではないでしょうか。
その中で、自らの「信仰」を生き抜き、数々の作品を残してくれた遠藤周作を、私はひとりの人間として、深く尊敬しています。


その他の記事

|
タワマン税制の終わりと俺たちの税務のこれから(やまもといちろう) |

|
個人の情報発信で考えていること(やまもといちろう) |

|
「減りゆく日本人」出生数低迷と政策的手詰まり(やまもといちろう) |

|
食欲の秋、今年は少しだけ飽食に溺れるつもりです(高城剛) |

|
少林寺、そのセックス、カネ、スキャンダル(ふるまいよしこ) |

|
「狂信」と「深い信仰」を分ける境界(甲野善紀) |

|
人口減少社会だからこそこれからの不動産業界はアツい(岩崎夏海) |

|
「控えめに言って、グダグダ」9月政局と総裁選(やまもといちろう) |

|
画一化するネットの世界に「ズレ」を生み出すということ(西田宗千佳) |

|
目下好調の世界経済にバブル崩壊のシナリオと対処法はあるのか(やまもといちろう) |

|
9月は世界や各人の命運が分かれる特異月(高城剛) |

|
『赤毛のアン』原書から、アイスクリームの話(茂木健一郎) |

|
幻の絶滅鳥類ドードーが「17世紀の日本に来ていた」という説は本当なのか(川端裕人) |

|
岸田文雄さんが増税判断に踏み切る、閣議決定「防衛三文書」の核心(やまもといちろう) |

|
世界経済の混乱をどう生き抜くか(やまもといちろう) |